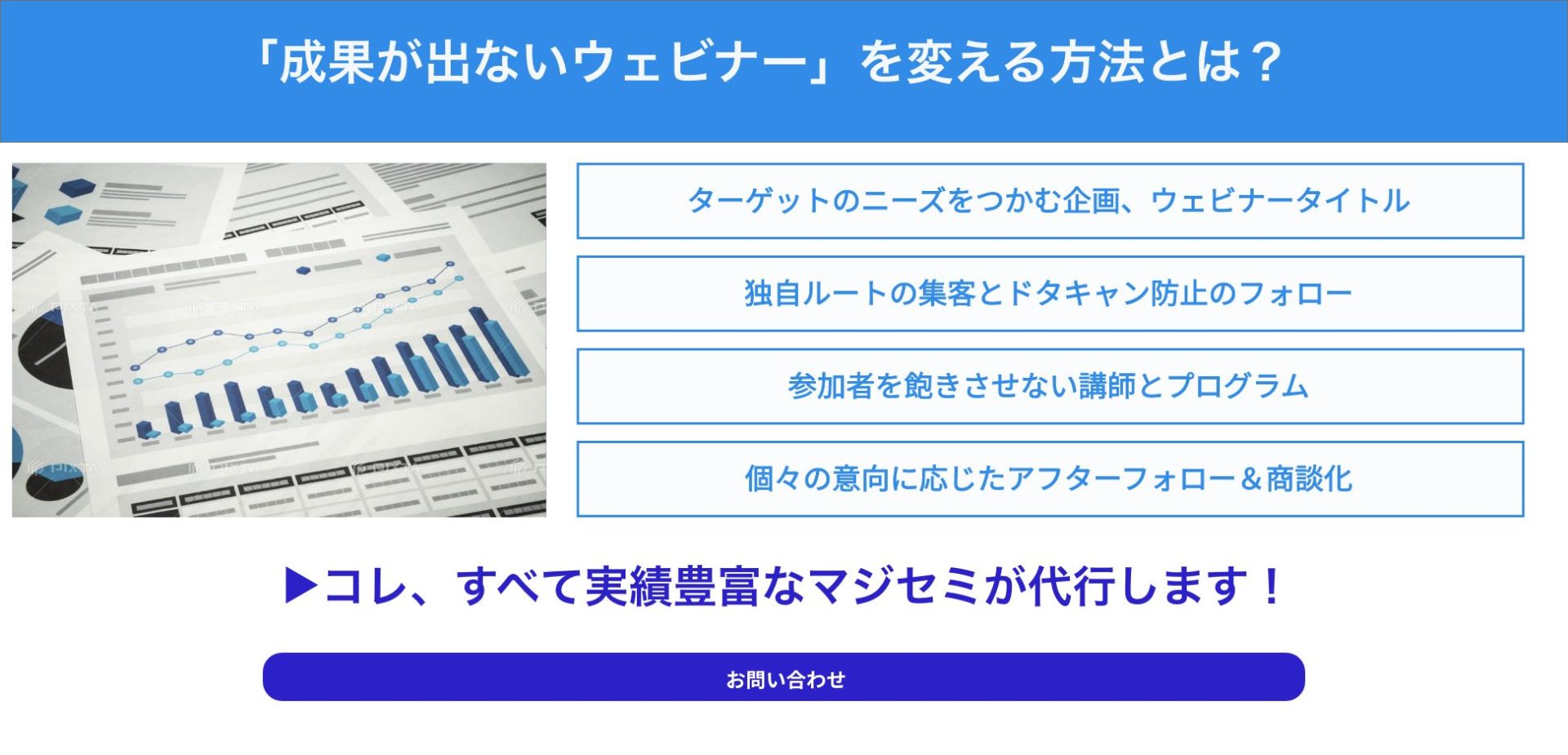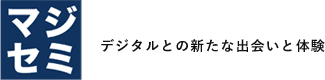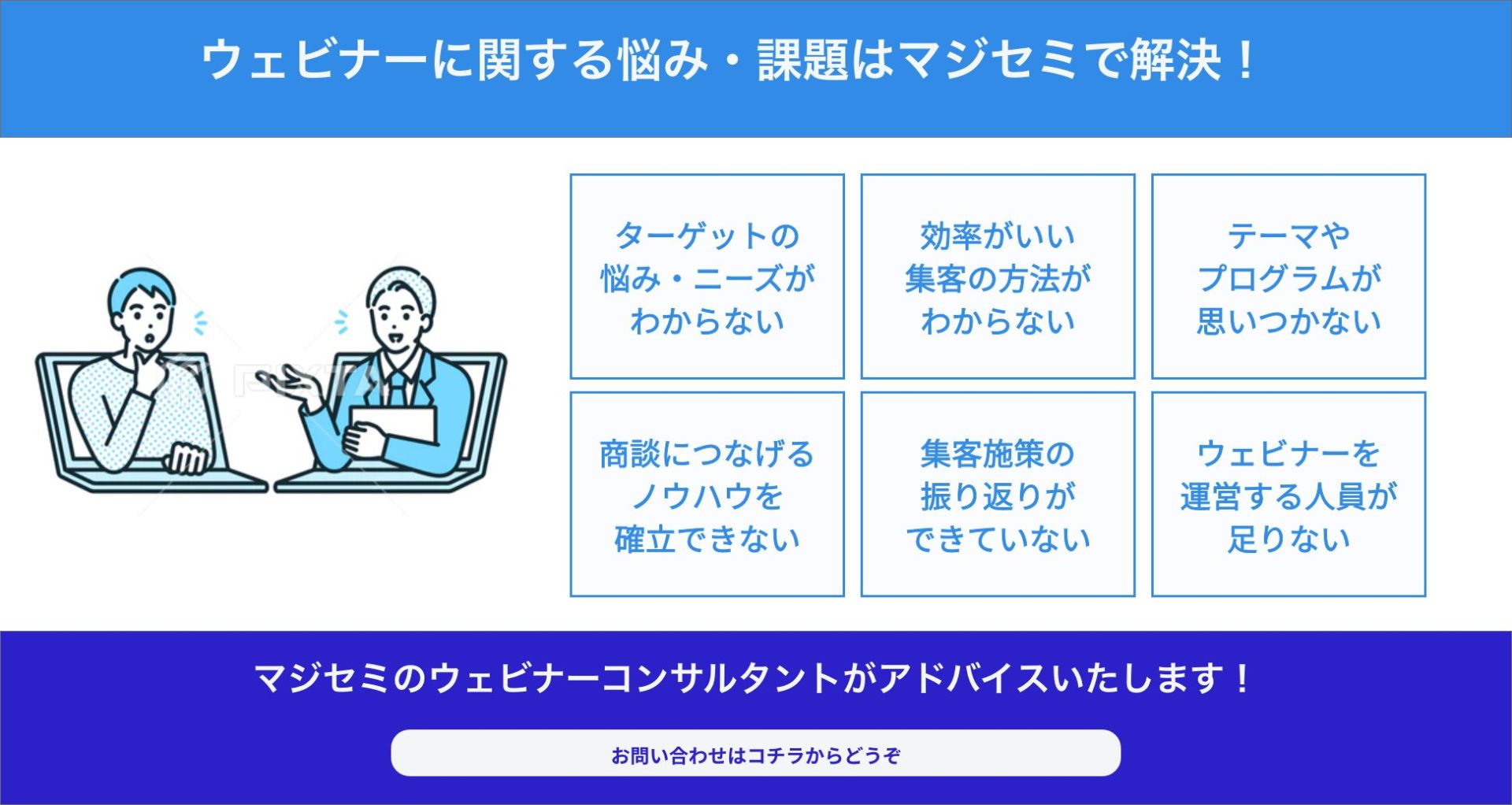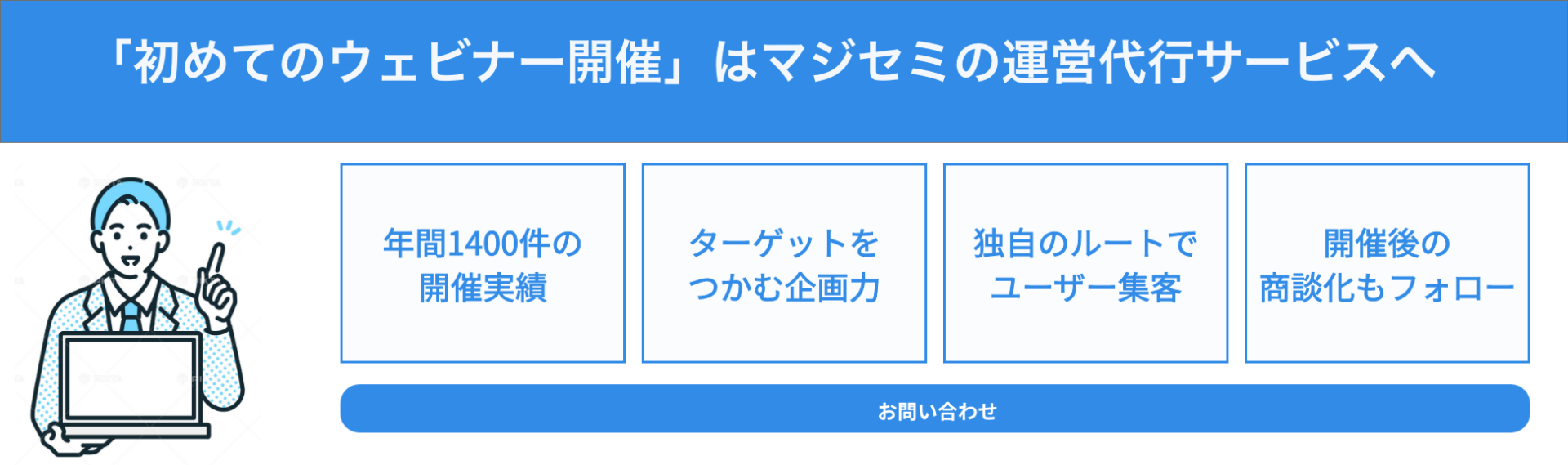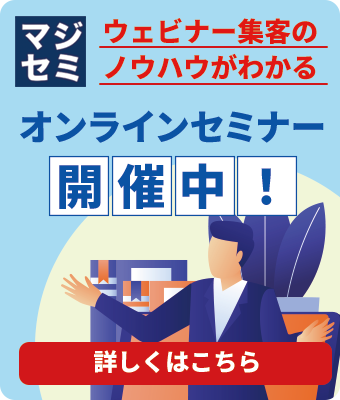BtoBマーケティングの手法として、いま注目度が高まっているのが「オンラインカンファレンス」です。
オンラインカンファレンスは複数の企業が集まって、共催で開催するオンラインイベントのひとつ。効果的・効率的に新規リードを獲得できる集客施策として、ここ最近、多くの企業が導入を進めるようになりました。
しかし、一社単独のウェビナーと比較したメリット・デメリットや、開催のために必要な準備がわからないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、オンラインカンファレンスの特徴や開催メリット、必要な準備を一挙紹介。オンラインカンファレンスの開催を検討している方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
オンラインカンファレンスの特徴とメリット
カンファレンスはもともと、医療業界で大小さまざまな規模の「会議」「打ち合わせ」を意味する言葉です。一方、ビジネスの文脈では「専門家が登壇する外部に開かれた大規模イベント」を指して使われます。
一社での開催が一般的なセミナーとは異なり、カンファレンスは複数の企業・専門家が一堂に会するのが特徴。多いときには15社以上が共催するケースもあります。それだけに発信される内容は信頼性・専門性・新規性が高く、高品質な情報を求める参加者が数多く集まる傾向にあります。
これまでカンファレンスの開催は、会場に数百名の参加者が集まるリアルイベントの形式が一般的でした。
オンラインカンファレンスは、このカンファレンスをオンライン上で実施。会場のキャパシティや場所に制限されることなく、全国・海外から専門家や参加者を招待することが可能です。
オンラインカンファレンスの需要が高まった背景には、Zoomをはじめとする「オンライン会議ツール」や「ウェビナー配信ツール」の技術的な発展があります。働き方改革やコロナ禍などの影響によりこれらのオンラインツールが普及したことで、会議やイベントがオンライン完結で実施できるようになりました。
いまではリアルイベントよりも、気軽に参加できるオンラインイベントを優先的に選ぶ顧客も少なくありません。オンラインカンファレンスも、このような顧客ニーズに応えたイベントのひとつといえるでしょう。

忙しい講師・専門家も、海外や遠方から移動時間をかけずに登壇できます。結果として参加の承諾を得やすいのもメリットです。オンライン形式を採用したことで高齢のゲストをカンファレンスに招致でき、イベント全体の権威性が高まったという事例もあります。
また、複数の企業が共催して自社の顧客を集めるため、一社単独のウェビナーと比べて参加企業は低予算かつ効率的に新規顧客層との接点を創出できるでしょう。
複数企業や専門家が参加することで、自社の信頼獲得やブランドイメージ向上につながりやすいのも特長。幅広い業界の関係者との接点創出の機会になったり、業界全体の盛り上がりに貢献できたりと、他社とのつながりを強める効果も期待できます。企業間でシナジーが創出できれば、参加者にとっても満足度の高いイベントになるでしょう。
配信ツールを使って参加者のコメント・質問を募れるのもメリットです。通常のカンファレンスでは、参加者が発言するのは質疑応答など一部の時間に限られます。ほかの参加者に気兼ねして、発言を控えてしまう参加者も少なくありません。
しかし、オンラインカンファレンスであれば、チャット機能をつかって匿名で自由に発言が可能。投票機能で参加者の意見をイベントにリアルタイムで反映させるなど、柔軟なコミュニケーションが取れるでしょう。双方向性・参加性の高いイベントになるうえに、参加者の声を次回以降のイベントやマーケティングに活かすことができます。
一方で、「自社の商品・サービスに焦点を当てる」「参加者と深いコミュニケーションを取る」といった機能では単独のウェビナーに軍配があがるかもしれません。参加者の興味関心や質問内容はほかの企業にも分散してしまうため、目的に応じた使い分けが重要になるでしょう。
対面式のイベントと比べると、退出のハードルが低く、参加者の離脱率が上がりやすいのもデメリット。通常のカンファレンス以上に、参加者の注意や興味関心を維持し続けるコンテンツづくりが重要です。
同時接続の参加者が多い場合には、通信環境の整備も大切になります。アクセスが集中しても滞りなく配信できる環境を整えるとともに、推奨環境をアナウンスするなど、参加者が視聴するデバイスや通信の状況にも配慮する必要があるでしょう。
これらの注意点やコンテンツ制作・イベント運営のノウハウを社内に蓄積するまでには相応の時間が必要です。そのため、競合他社よりもはやく導入に着手することで、オンラインカンファレンスの主催企業として存在感を獲得できるかもしれません。
そんなオンラインカンファレンスには「オンライン完結型」と「ハイブリッド型」の2種類があります。
オンライン完結型は、会場を使わず、企業・参加者の全員が配信ツールにアクセスするタイプ。大きな会場の手配やスタッフの人件費・交通費といったコストを大幅に削減できるのが魅力です。
ウェビナー配信ツールなどを使ってリアルタイム配信することで、参加性の高いインタラクティブなイベントを実現できます。あらかじめ収録した動画を編集して、オンデマンド配信することも可能。双方向性は低くなるものの、時間の制約がなくなり、いつでも視聴できるのがメリットです。
これまで、大規模なカンファレンスは豊富な人員・予算のある大企業でないと開催できませんでした。しかしオンライン完結型のカンファレンスなら、中小企業・ベンチャー企業でも、十分に開催することができます。
対してハイブリッド型は、リアルイベントをオンラインでも同時配信します。会場の参加者はもちろん、オンラインの視聴者にもリアルイベントならではの盛り上がりや臨場感が伝わりやすいのが強みといえるでしょう。
会場を訪れるのが難しい参加者も気軽に視聴できるため、リアルとオンラインのいいとこ取りが可能。会場のみのカンファレンスのように参加人数の上限を定める必要がなく、顧客を取りこぼさずに集客できます。登壇者は基本的に会場参加となるものの、モニターなどを使ってオンラインで登壇してもらうこともできるでしょう。
ただし、コストや開催・運営の手間はオンライン完結型よりも大きくなります。また、単なる生中継にしてしまうと、オンライン参加者の満足度が低下することも。会場での講演・演出・熱気をオンライン視聴者にわかりやすく伝えるためには、設営や機材配置・撮影などの工夫も欠かせません。

オンラインカンファレンスに必要な準備
オンラインカンファレンスを主催するうえでまず考えなくてはいけないのが、「企画」と「共催企業」です。開催日から逆算して、遅くとも半年前には企画を終え、共催企業の選定や当日に向けた準備に入れるようにしましょう。
企画で決めるべき内容は、カンファレンスを開催する目的、ターゲット、イベント全体のテーマ、開催日時、予算、規模感など多岐にわたります。
とくに目的とターゲットは、企画や共催企業の方向性を決める重要な要素。「製品・サービスの認知拡大」「新規顧客の獲得」「見込み顧客のナーチャリング」など、カンファレンスのゴールを明確にしたうえで、どのようなターゲット層を集めるべきかを具体化しましょう。
ターゲットは具体的な一人の人物像を立てると、その後の企画が進めやすくなります。居住エリアや年齢・性別、業界・業種・役職、趣味などに加えて、ターゲットが抱えている課題・ニーズも細かく明確化します。
イベント全体のテーマも、集客や目的達成の可否を大きく左右するポイントです。
ただし、自社が発信したいメッセージだけに重心を置いてしまうと、参加者や賛同企業はなかなか集まりません。ターゲット層や業界・社会レベルの課題・ニーズ・トレンドなどもふまえつつ、三方よしのテーマを立てることがカンファレンス成功の秘訣です。
開催日時はターゲット層が参加しやすい曜日・時間帯を設定します。業界・業種などにもよるものの、BtoBのイベントであれば火・水・木曜日の業務時間内は、比較的スケジュールが確保しやすい日程です。
果たしたい目的や予算・規模感に応じて、オンライン完結型にするかハイブリッド型にするかも明確にしましょう。当日のプログラムも大まかに決めておくと、共催企業に内容を共有しやすくなります。
共催企業は、実現したいテーマや集めたいターゲットと親和性の高い企業を選定するのが理想。加えて、自社の商品・サービスと競合しないこと、相手企業にとっても共催のメリットがあることも大事な条件です。
条件に合う企業が見つからないときは、共催企業をマッチングするサービスを利用してみてもいいかもしれません。オンラインカンファレンスの企画をサイト上に掲載したり、集客力やターゲット業界・ターゲット職種などから企業を検索できたりするサービスもあり、効率的に共催企業を見つけることができるでしょう。
依頼時には企画内容に加えて、相手企業を選んだ理由、果たしてもらいたい役割、相手企業が得られるメリットなどを説明するのがポイント。承諾の返事がきたら、より具体的な講演内容を打ち合わせて企画を詰めていきます。
企画・共催企業が決まったら、開催したい規模感や予算感に応じて適切な配信ツールの選定を行います。
配信ツールを選定するときは、予算感やコミュニケーション機能などに加えて、参加可能な人数もしっかりとチェックしましょう。ツールによっては上限人数を追加できるプランやオプションを用意している場合も少なくありません。
複数人が操作・登壇するときは、共同ホスト機能の確認も不可欠。アカウントごとに操作やアクセスの権限を細かく設定できるツールであれば、安心安全にオンラインカンファレンスを運営できます。
同時に、会場・機材・スタッフ・登壇者などの手配や、LP・申込フォームの作成、顧客への告知やそのほかの集客施策、問い合わせへの対応、共催企業との打ち合わせ・事前リハーサルなども並行して進めていきましょう。
LPにはオンラインカンファレンスのタイトル・開催日時・共催企業・参加方法・プログラムなどを漏れなく記載します。申込みフォームもページ内に埋め込むと、画面遷移が少なくなり申込者の負担軽減につながります。
共催企業のハウスリストや、SNS・オウンドメディアなどでの告知がメインですが、予算に余裕があればプレスリリースやWeb広告・ポータルサイトを活用するのもひとつ。とくにプレスリリースは、著名なゲストや企業の代表が登壇するなどイベントに話題性があれば、各メディアが取り上げることで高い訴求力を期待できます。
告知・集客にあたっては、共催企業間で足並みをそろえることも重要です。イベント全体の集客目標や、現状の集客人数を共有して、連携を取りながら施策を進めましょう。バナー画像や定型文を提供して、積極的に活用してもらうことも大切です。
本番の前日までには、少なくとも1度はリハーサルを実施。プログラムの流れや当日のコミュニケーション方法、登壇のタイミング、講演内容、時間配分、役割分担、音声・映像の品質、トラブル発生時の対応方法などを最終確認しましょう。
なお、業務を企業ごとに分担しようとすると、かなりの統率力・連携力が必要です。認識のすり合わせに苦労すると余計に工数や労力がかかる場合も珍しくありません。
そのため、集客以外は主催企業がまとめて進めるのが基本。しかし、開催ノウハウやリソースが不足している場合、最初からイベントを成功させるのは難易度が高いかもしれません。当日運営でも、司会進行・参加者対応・配信ツールの操作・配信トラブルの対処などこなすべき業務は多岐にわたります。
より気軽に着実にオンラインカンファレンスで成果を出すなら、運営代行会社に業務を委託するのもひとつでしょう。
ウェビナー・オンラインカンファレンスの代行ならマジセミ
ウェビナーの運営代行会社「マジセミ」は、オンラインカンファレンスの企画から集客・当日運営まで、当日講演以外のすべての業務をワンストップで代行。年間1,000回のウェビナーを開催してきた知見・ノウハウを活かして、成果につながるイベントを実現します。
過去には20社の共催で400名を集客した実績もあり、オンラインカンファレンスは得意領域です。オンラインカンファレンスを活用して新規リードを獲得したいという企業様・担当者様は、ぜひマジセミにご相談ください。