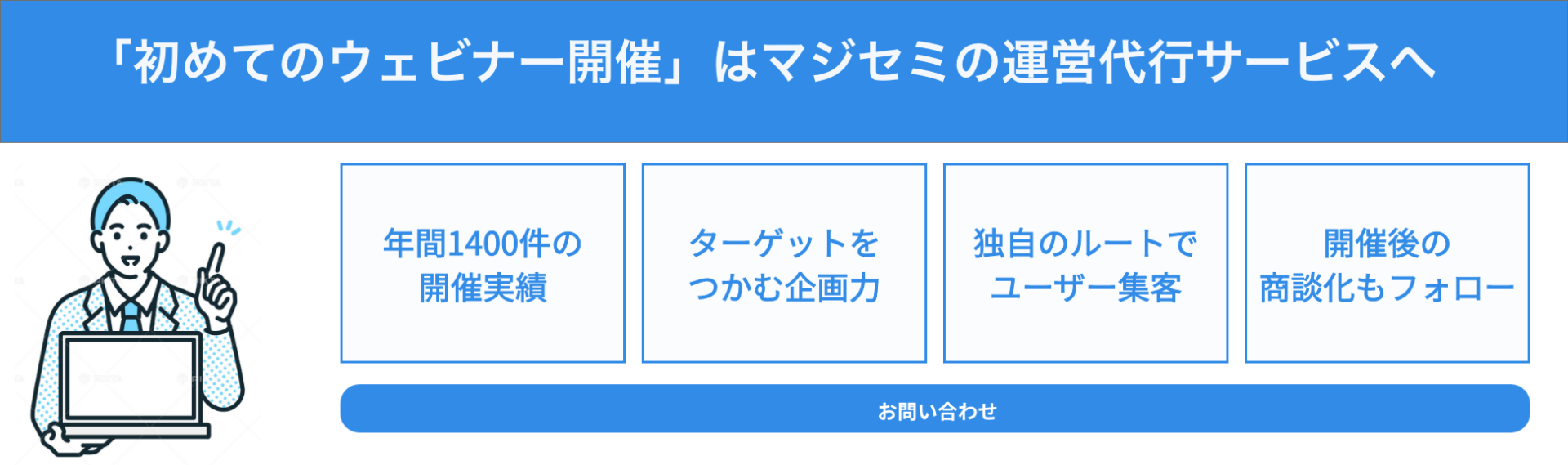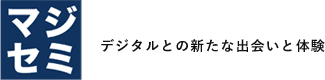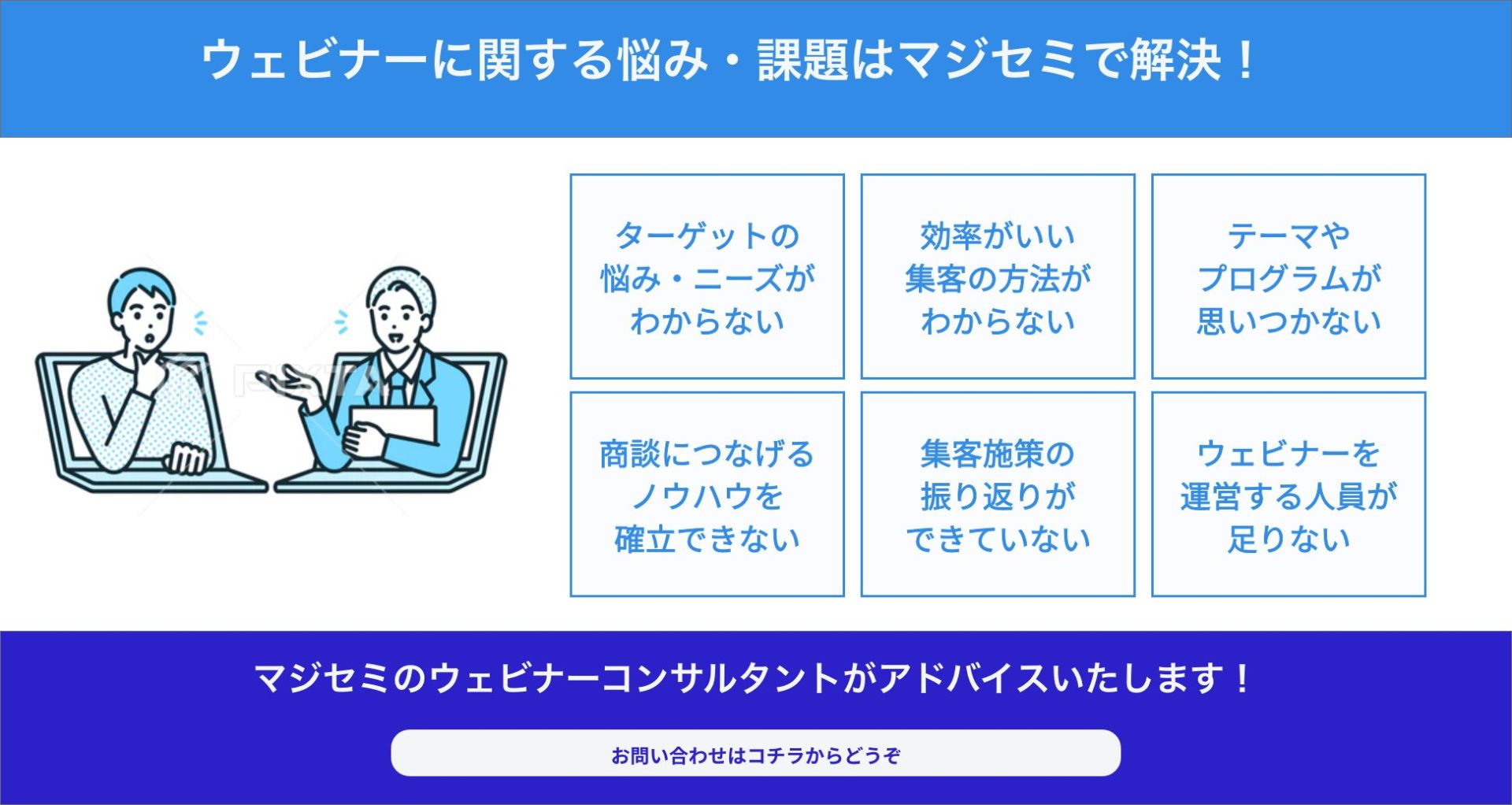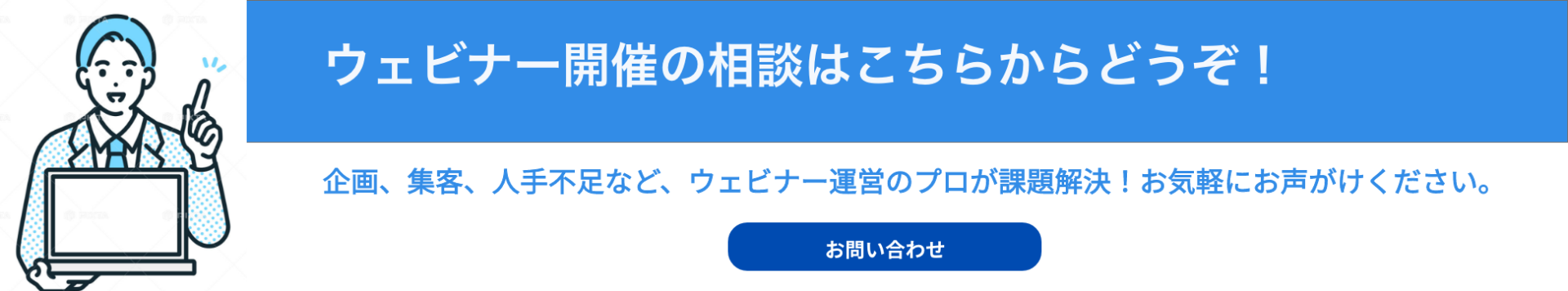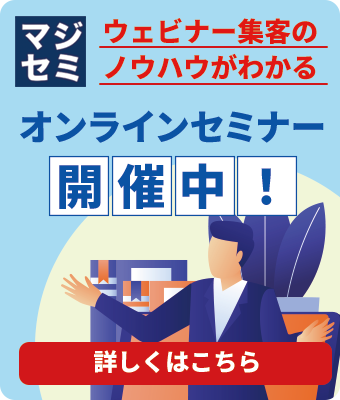近年、セミナーに代わって開催企業が増えているのがWeb版のセミナー・通称「ウェビナー」です。とくにコロナ禍以降は、新時代のマーケティング手法として幅広い業界で注目度が高まりました。
会場に参加者があつまるセミナーに対して、ウェビナーはインターネットを通じて行われるのが特徴。どちらも「特定のテーマについて専門知識を持ったプレゼンターが講義を行う」「自社の製品・サービスに興味関心のある顧客を集客できる」という点は同じですが、開催・集客の方法などには違いがあります。
本記事ではセミナーとウェビナーの具体的な違いを比較。開催・運営の具体的な流れについても解説していくため、ぜひ最後までチェックしてみてください。
セミナーとウェビナーの開催方法の違い
セミナーとウェビナーの最大の違いは両者の開催方法です。
セミナーは特定の日時・会場に主催者と参加者が集まり、対面形式で実施されます。
一方、ウェビナーはZoomウェビナーなどの配信ツールを活用して、オンライン完結で実施するのが一般的。
参加者はPC・スマートフォン・タブレットなどを使って、自宅・オフィスなど好きな場所からウェビナーにアクセスができます。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い外出自粛やイベントの規制が求められたことで、非対面で実施できるウェビナーは急速に普及しました。
配信形式にはリアルタイム配信のほかに、録画動画を公開するオンデマンド配信もあり、後者であればユーザーは好きなタイミングでウェビナーを視聴することが可能です。リアルタイム配信の内容を録画・編集して、当日参加できなかった人に向けて公開するのもひとつ。また、昨今は対面形式のセミナーをリアルタイムで同時配信するハイブリッドセミナーを開催する企業も少なくありません。
主催者と参加者、あるいは参加者同士の交流が取りやすいのは、直接コミュニケーションが取れる対面式のセミナーでしょう。イベント自体も盛り上がりやすく、参加者の集中力を維持しやすいのもメリットです。結果として、開催後の個別面談などで商談を獲得しやすい形式といえるでしょう。
対するウェビナーは、参加者にとって参加するための制約が少なく、会場に足を運ぶ必要もないため、セミナーと比べてより気軽に参加できる開催形式といえます。業務の合間に参加できることから、忙しいビジネスパーソンにも人気です。

主催企業からしても遠隔地の顧客をふくむより多くのターゲットを集客でき、開催コスト・運営コストも最小限で抑えられるのがメリット。会場や配布物の準備、当日の受付・来場者案内、撤去といった人員も不要です。多くのスタッフをそろえられない中小規模の企業でも、比較的簡単に、高頻度でイベントを開催できるでしょう。
また、配信ツールのチャット機能・質疑応答機能を活用すれば、参加者はプレゼンターへの質問・コメントを自由なタイミングで行えます。匿名の設定にもでき、ほかの参加者の目を気にすることなく発言ができるため、インタラクティブなコミュニケーションが生まれやすいのもウェビナーの特徴です。ブレイクアウトセッションを活用して、少人数でのディスカッションやワークを実施することもできます。
効果計測がしやすいのも魅力のひとつです。配信ツールで行動履歴やコメント・質問、アンケートなどのデータをスムーズに収集。参加者の興味関心や行動パターンに基づいて、効果的なマーケティング戦略を立てたり、アフターフォローや次回以降のウェビナーに活かしたりできます。
ウェビナーで参加者との関係構築や商談獲得につなげるためには、パーソナライズされたアフターフォローが必須です。収集した顧客情報に基づいて、適切な距離感で情報を提示。中長期的なナーチャリングを実施することで、最終的な成約につなげます。
これらの特徴から、近年のウェビナーは会場型セミナーの代替としてだけでなく、展示会・研修・企業説明会・株主総会・決算報告会など、幅広いシーンで活用されるケースも少なくありません。
セミナーとウェビナーの集客方法の違い
セミナーもウェビナーも、活用できる集客方法は基本的に同じです。
とくに主流なのは、ハウスリストへのメールや自社サイト、SNS・ポータルサイト・Web広告・プレスリリースなどのオンラインチャネルを活用した告知でしょう。また、DM・チラシ配布・地域の掲示板や情報誌などオフラインの集客方法が利用されるケースもあります。
ただし、集客すべきターゲットやリーチの方法はセミナーとウェビナーで最適解が異なります。
セミナーは集客すべきターゲットのエリアが限定されるため、チラシの配布やポスターの掲示といったオフラインでの集客手法がメイン。オンラインの集客はメルマガ、一部のWeb広告など、居住地・勤務地をしぼってリーチできる集客手法に限定されます。
集められる参加者の人数も、会場のキャパシティに依存します。人数が集まりすぎた場合には申込みを断らなければならず、機会損失が発生してしまうケースもあるでしょう。
そのため、オンラインチャネルで幅広く告知をしても、かけた費用に比例した成果は得られないかもしれません。
一方、ウェビナーはエリア・会場の制約を気にせず、地方・海外の顧客もふくめて幅広くターゲッティングすることが可能。グローバルなマーケットも含めて、ビジネスチャンスを大きく広げる契機になりえます。
ウェビナーで集客しやすいメインターゲットは、日常的にオンラインで情報収集をする層。申込者・参加者の管理のしやすさもふくめて、オンラインチャネルでの集客とはとくに相性がいい形式といえるでしょう。
ターゲットの母数が多くなれば、それだけ多くの参加者を集客できたり、多くの商談を獲得できたりする可能性があります。参加ハードルも低いことから、通常のセミナーよりも集客しやすいのが利点です。

ただし、自社の商品・サービスの潜在顧客にピンポイントで訴求しないと成果につながらないのは、セミナーもウェビナーも同様です。集客したいターゲット像を明確にしたうえで、課題・ニーズにマッチした企画を立てる必要があります。
とくにウェビナーの場合、気軽に参加できるだけに、ターゲット層以外の参加者が多く集まってしまう可能性もゼロではありません。その分だけ、自社の商品・サービスに興味関心を持っている参加者が埋もれやすくなるリスクもあるでしょう。
そのような事態を防ぐために、告知の際にはテーマや対象者をわかりやすく提示するとともに、ターゲット層にリーチしやすい集客手法を選択することが重要です。
また、ウェビナーは心理的ハードルの低さゆえに、セミナーと比べて当日の欠席者が多くなりやすい傾向にあります。参加方法をわかりやすく記載するなど、参加者の疑問・不安をできるだけ解消するとともに、数回のリマインドメールを送るなど、当日キャンセルにつなげないための工夫が大切になります。
セミナーとウェビナーの準備の流れ
セミナーとウェビナーの開催前の準備は大まかに下記の流れで進みます。
・目的・ターゲットの設定
・テーマ・プログラムの企画
・集客・告知・問い合わせ対応
・プレゼン資料の作成
・配信環境の準備
・リハーサル
セミナー・ウェビナーともに、開催が決定したらまず考えるのは「目的・ターゲット」です。ビジネス領域のイベントなら、主要な目的としては「新規リードの獲得」「リードナーチャリング」「商談の獲得」などが挙げられるでしょう。
規模感や企画・予算・集客力にもよるものの、対面式のセミナーは商談獲得に、幅広い参加者を集められるウェビナーはリードの獲得やナーチャリングに、より利用しやすい形式といえます。
ただし商談獲得が目的の場合でも、コミュニケーションが取りやすい少人数制の企画や製品の特徴を映像でくわしく紹介する企画であれば、ウェビナーでも十分な効果が期待できます。
企画・ターゲットが決まったら、つぎに具体化するのはイベントの「企画」。
テーマは自社の商品・サービスと親和性が高いだけでなく、ターゲット層の課題・ニーズにもマッチしたものを選ぶのがポイントです。参加者の興味関心を引くなら「著名なゲストを招く」「業界のトレンドやタイムリーな話題を提示する」といった切り口もあります。
ウェビナーのプログラムを組み立てるときは、セミナー以上に参加者の集中力が途切れやすいことを踏まえて、参加者の興味関心を維持できる構成を意識しましょう。要点をわかりやすくまとめたスライドや、図解・イラスト・写真・映像の提示など、視覚的に注意を引く工夫が効果的です。
参加者に質問をしてチャット・投票機能での回答を募ったり、質疑応答やワークの時間を設けたりと、参加性の高いプログラムを用意するのもひとつ。それ以外の時間にも積極的な質問・コメントを促すようにすると、イベントの盛り上がりを演出できます。
準備すべき「開催環境」は、セミナーなら参加者を収容する会場の手配・設営、ウェビナーなら配信スペースと機材の確保です。
セミナーの会場は予算・キャパシティなどを考慮しつつ、ターゲット層がアクセスのしやすい場所を選定することが重要。ハイブリッドセミナーを開催する場合には、通信環境や機材の搬入が可能かも確認しましょう。
ウェビナーの配信スペースは通信環境が整っていて静かな場所なら、自宅・オフィスでも問題ありません。またレンタルスペースを活用するのもひとつでしょう。配信に必要な機材としては、PCや配信ツールのほか、カメラ・マイク・照明・モニターなどが挙げられます。
カメラはPC内蔵のものだと、講師を下から見上げる画角になってしまい印象がよくありません。マイクも音声が聞こえにくかったり、ノイズが入ったりしてしまうケースがあるため、外付けのものを用意するのがおすすめ。加えて照明を用意しておくと、講師の顔が明るくなり、好印象につながるでしょう。
当日に使う資料や参加者へのアンケートは、セミナーの場合には紙ベースで準備して配布・回収しますが、ウェビナーならオンラインで完結することが可能。当日の設営も不要のため、開催準備にかかる全体的な工数や手配すべきスタッフの数をかなり軽減できます。
オンデマンド配信の場合には、収録したウェビナー動画を編集することでより満足度の高いコンテンツを提供できます。無駄な時間をカットするとともに、見出しやテロップ・画像・動画などを挿入すると、参加者にとって見やすい動画になります。
本番前には、必ずリハーサルを行って当日の業務内容や注意点をチーム内で共有しましょう。想定しうるトラブルを洗い出して、対策を具体化しておく準備も重要です。ウェビナーの場合には、通信環境や映像・音声の状態もしっかりチェックします。
目的と状況に応じたセミナー・ウェビナーの使い分けが鍵 以上、セミナーとウェビナーの違いについて、開催方法・集客方法・準備の流れという観点から解説をしました。
会場に集まって対面式で実施するセミナーに対して、ウェビナーはオンライン上で完結するのが特徴です。主催者・参加者の交流が深まりやすいのはセミナーですが、ウェビナーには「気軽に参加・開催できる」「双方向のコミュニケーションが生まれやすい」というメリットがあります。
そのため、開催の目的や集めたい顧客の数や属性、予算感などに応じて、最適な形式を選ぶ必要があるでしょう。
ウェビナーを初開催するなら、企画から集客・当日運営までをワンストップで代行する「マジセミ」の利用がおすすめです。
年間のウェビナー開催数は1,400回以上。大手IT企業から製造業DX企業、スタートアップまで、毎年300社以上にご利用いただいており、リピーターも少なくありません。
IT業界・製造業のウェビナーで国内トップクラスの集客実績があり、250,000件の独自ハウスリストと、経験に裏打ちされた企画力を駆使して情報感度の高い決裁者を呼び込めます。2024年には年間60,000人を動員しました。
当日運営も、司会進行から配信ツールの操作、参加者対応まで、講演以外のすべての業務を代行することが可能です。また、生成AIが基調講演を代行するオプションサービスも用意しており、申込者の20%から商談を獲得した実績もあります。
料金は集客人数に基づく完全成功報酬型。集客単価14,500円からのVisitorプラン、12,000円からのLiteプラン、商談保証付きのAdvanceプランを用意しており、着実な成果獲得をめざせます。
ウェビナーで高いコストパフォーマンスと、集客・商談の成果を両立させたいという企業様・担当者様は、ぜひマジセミの利用をご検討ください。