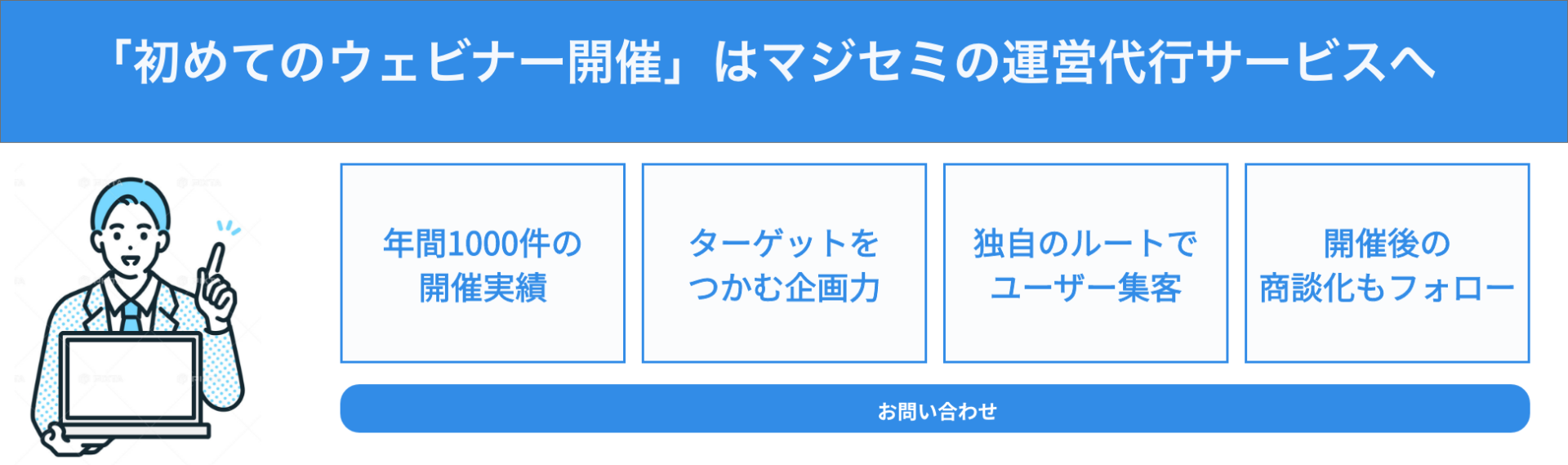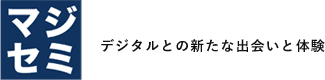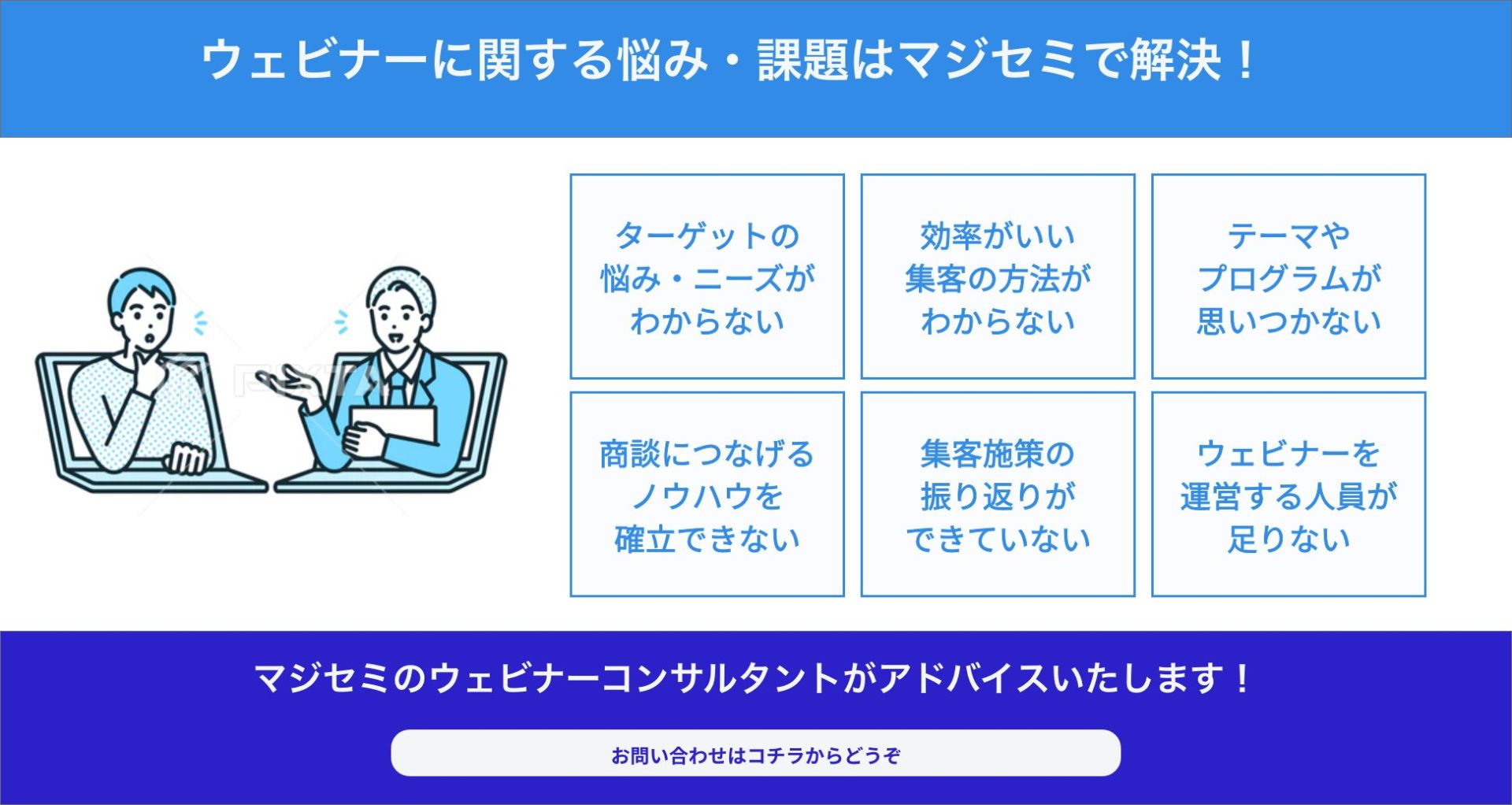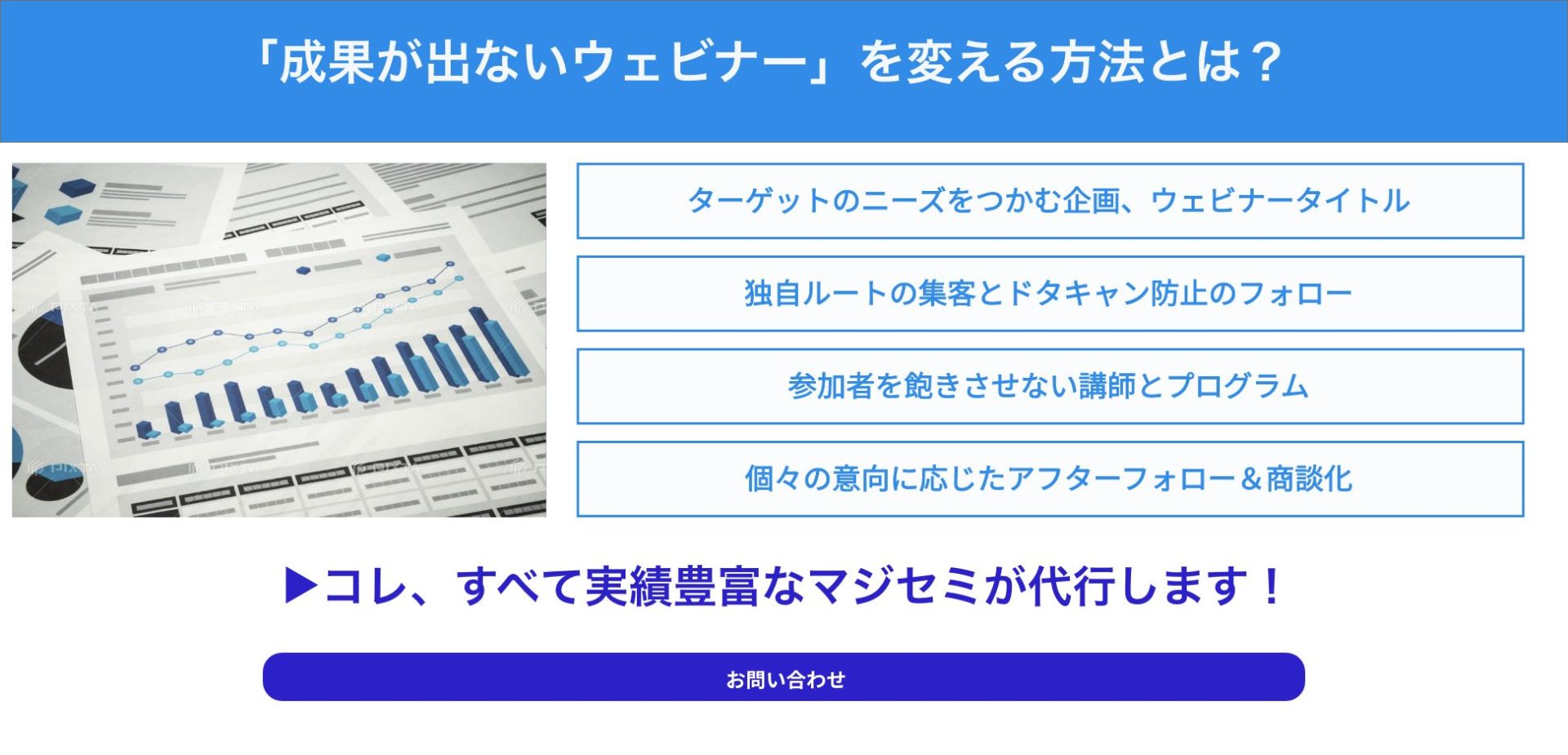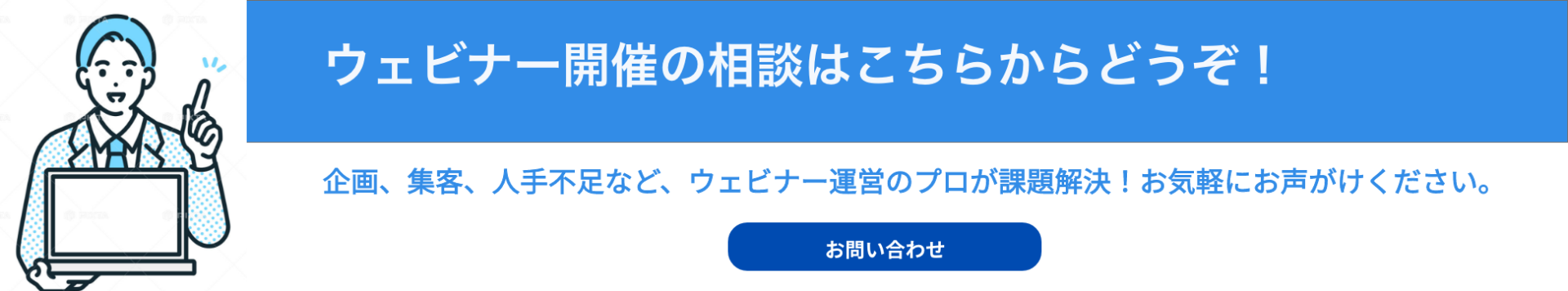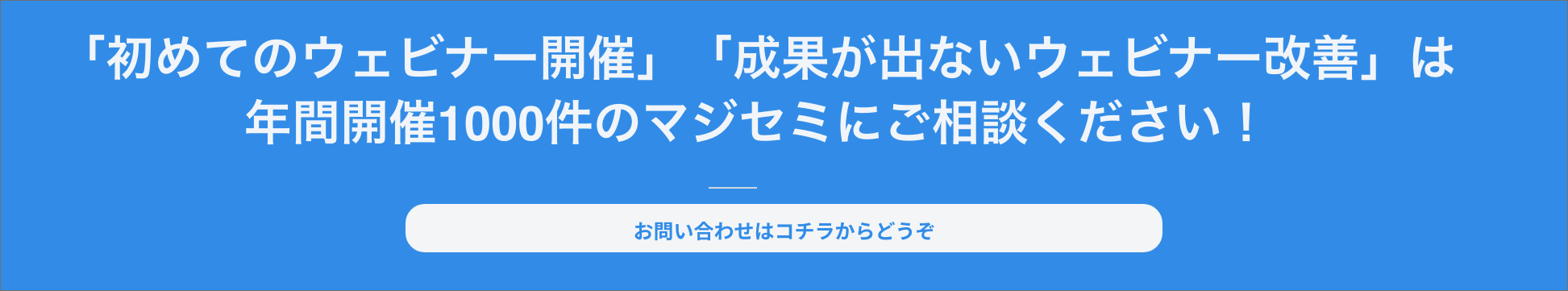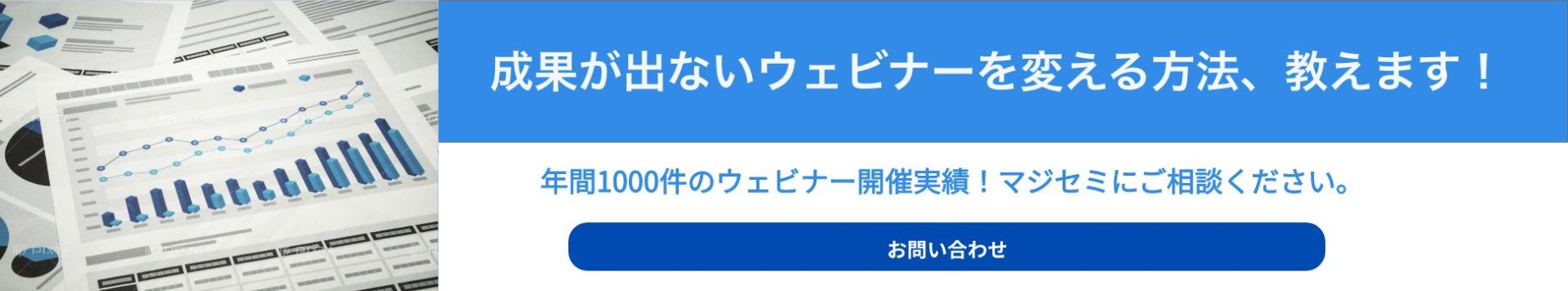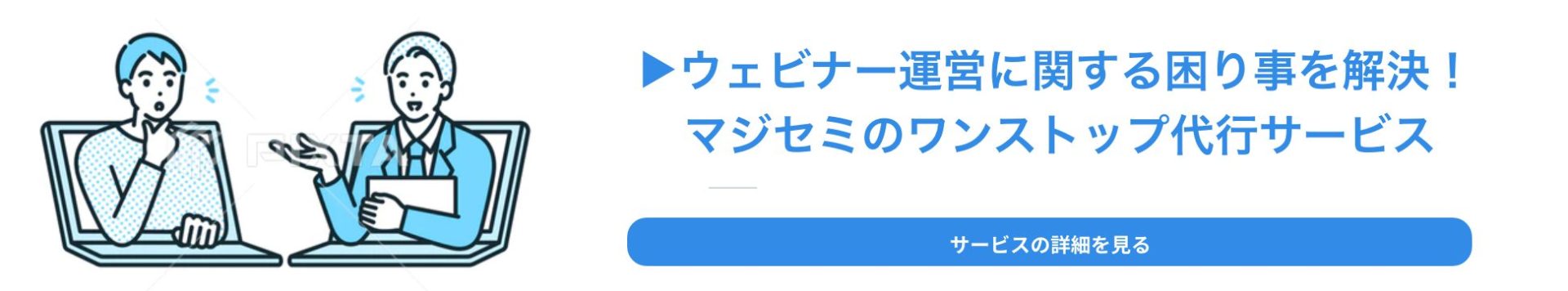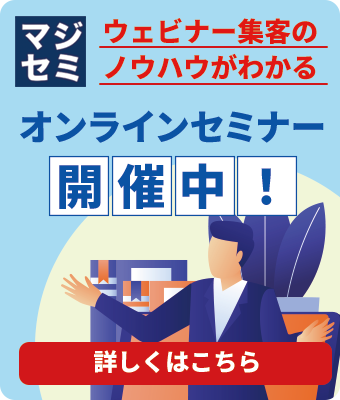新規リード獲得やリードナーチャリング、商談獲得のための施策として人気のセミナー。しかしセミナーの運営ノウハウがないために、何をどのように進めればいいかわからずなかなか開催に踏み切れないという人は多いのではないでしょうか。
セミナー成功の鍵は集客や本番に向けた事前準備にあり、行き当たりばったりの運営ではなかなか上手くいきません。
また、開催したはいいものの想定したほど参加者が集まらず、成果につながらないというのもよくある悩みです。
そこで今回はセミナーの企画立案から開催までの流れを紹介。集客方法についても基礎知識からくわしく解説していきます。
「セミナーを開催したいけど知識・経験がない」「参加者が集まるセミナーにしたい」という企業様・担当者様は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
セミナー全体のスケジュール
具体的な開催プロセスについて考える前に、まずはセミナー全体のスケジュールを把握しておきましょう。セミナーの企画立案から本番までの大まかな流れは下記のとおりです。
・企画・集客の準備・告知・集客スタート・運営準備・本番
十分な参加者を集めるためには告知・集客の期間をたっぷり設けることが重要。この期間を1〜2週間など短く設定してしまうと、ターゲット層にセミナーの情報が広まりきりません。すでに開催日に予定が入ってしまっているリスクも高まります。
ただし、集客期間が長過ぎるのも考えものです。たとえば本番の2ヶ月前に告知を行っても、スケジュールが予測できないために、申込みを躊躇してしまう人は多いでしょう。
意思決定の猶予があるために、申込みを後回しにされてしまうリスクもあります。ファーストインプレッションで興味を持った人も、時間の経過とともに関心が薄れたり、セミナーの存在自体を忘れてしまったりするかもしれません。
そのため、周知のスタート時期は本番の3週間から1ヶ月前を目安にするのがおすすめ。企画や集客の準備なども、そこから逆算して余裕のあるスケジュール設定をしましょう。
セミナー開催では、集客や講演・プレゼン資料の準備だけでなく、シナリオ作成、講師の手配、会場・機材といった環境の準備、問い合わせ対応など、さまざまな業務を同時進行する必要があります。運営チームの人数がよほど多くなければ、担当者の負担はかなりのものになります。
とくにセミナーを初開催する場合、想定どおりに準備が進まず、工数がかさんでしまうケースも少なくありません。セミナー直前にバタつくことのないように、アクシデントをみこして、あらかじめ長めの準備期間を確保しましょう。
目安としては、社内でさける工数にもよるものの本番の3ヶ月前までには企画をかためて、集客・会場・機材などの準備に入るのが理想です。

目的・ターゲット設定
セミナーの企画に入る前にまず着手するのが、セミナーを開催する「目的」と集めたい「ターゲット」の言語化。この2つが明確になっていると企画・集客の方向性がスムーズに固まり、成果につながりやすいセミナーを開催しやすくなります。
「目的」は、下記のようなマーケティングのフェーズを意識するとわかりやすいかもしれません。
・新規リードの獲得・リードの育成・商談の獲得
これらのフェーズのうち、今回開催するセミナーがどこに位置づけられるかを考えましょう。
達成したい目的ごとに、集めるべきターゲット層や人数、最適なセミナーのプログラムは異なります。そのため複数のゴールを立てるのではなく、ひとつのセミナーにつき目的をひとつに絞るのがおすすめ。
たとえば商談の獲得をゴールに設定するなら、メインターゲットはすでに自社の商品・サービスに興味関心がある検討層です。プログラムは、商品・サービスの具体的な特性を紹介する内容が効果的でしょう。
しかし、自社の商品・サービスを知らない層に同じセミナーを訴求しても、高い集客効果は見込めません。まずは現状の課題意識にフォーカスしたアプローチで顧客接点を獲得して、中長期的にリードナーチャリングを実施していく必要があります。
このように、目的の異なる複数のセミナーを段階的に開催しながら最終的に商談の獲得をめざすのが、セミナーマーケティングを成功させるコツです。目的設定で迷ったときは、成果までのスピードが速く、効率的に集客しやすい商談獲得から着手してみましょう。
目的が決まったら数値目標(KPI)も明確にしましょう。たとえば「新規リードの獲得」が目標なら、セミナー終了後に何件のリードを獲得するかがKPIになります。理想ありきではなく、予算感などもふくめた現実的な目標を設定するのがポイントです。
また、そのためにどれくらいの参加者・申込みを集めるべきか、どの程度のリード獲得率・成約率が求められるかまで細かく設定しておくと、達成のための手段・課題を明確にすることが可能。集客戦略でも、メール開封率、リンクのクリック率、セミナーへの申込率といった各フェーズの反応率を概算して、目標達成に必要な最低限のコスト・工数が割り出せます。過剰な費用・労力の投入の抑止にもつながるでしょう。
もちろん、最初から適切な目標が設定できるわけではありません。しかし、セミナー終了後の振り返りで実際の数字がわかれば、次回以降は精度をさらに高めることができます。改善点が浮き彫りになるため、ブラッシュアップにつながりやすくなるのもメリットです。

なお、セミナーの集客人数は多ければ多いほどいいとは限りません。商談獲得を目的にする場合などは、むしろ少人数制の方が双方向のコミュニケーションを取りやすく、成果が出やすい傾向にあります。
顧客対応やアフターフォローに手が回らないと満足度の低下やリードの離脱につながる可能性も。そのため後に紹介する「企画」や「セミナーの具体化」も踏まえつつ、現実的な数値を設定するようにしましょう。
「ターゲット」は主婦層・ビジネスマンといった大まかなカテゴリではなく、人物像を具体的に掘り下げるのがコツです。人物像が明確になるほど「どのような悩み・ニーズを抱えているか」「どのような言葉で訴求すると申込みにつながるか」がわかってくるため、戦略を立てやすくなります。
目的のときと同じく、ターゲットも複数の人物像を想定するのではなく代表的なひとりの顧客をイメージした方が施策がぶれません。年齢・性別・職業・役職・年収・居住地といった基本的な項目に加えて、抱えている課題やふだん使っているメディアなども明確にしましょう。
人物像をイメージがしにくいときは顧客理解が不足している可能性があるため、アンケートや個別面談などのリサーチを行うのも一案です。
企画・テーマ設計
企画・テーマを設計するときのポイントは、自社の目的とターゲットの課題の両方を解決できる方向性を見極めること。とくにターゲットの悩み・ニーズに一致する企画かどうかは集客の成功や顧客満足度を大きく左右するでしょう。
たとえば自社を知らない・接点がない顧客を集めるなら、業界で話題のテーマを取り扱ったり、特定の課題解決につながったりと、ターゲット層が興味関心を抱きやすい企画を打ち出すのがセオリー。
また、業界で著名な講師に登壇してもらう、ほかの企業とセミナーを共催する、といった方法も新規リード獲得に効果的です。共催セミナーであれば、各企業が既存顧客にセミナーを告知するだけなので、新たに新規顧客を開拓する手間がかかりません。
ただし、訴求力を高めようとするあまり誇大広告にならないように注意が必要です。
参加者に「期待していた内容ではなかった」と思われてしまうと、不満・不信につながって、それ以降の関係構築が難しくなります。最悪の場合、悪い口コミが広まってブランドイメージが損なわれる可能性もあるでしょう。課題解決型のセミナーを企画する以上は、実際にターゲット層の課題解決につながるような情報・施策を提供することが大切です。
一方、参加者の満足度は高いのに、その後のナーチャリング・商談化につながらないというケースも珍しくありません。セミナーの内容と、自社の提供する商品・サービスとの関連性が薄いために、具体的なアクションへ誘導できないのが原因です。
集客はあくまでも目的を達成するための手段。最終的なゴールにつながる企画・テーマ・プログラムであることが大前提です。
そのため、ターゲットのニーズを満たすだけでなく、自社の得意分野を打ち出せるような設計を心がけましょう。専門性や権威性、高付加価値な情報をからめることで、高品質なコンテンツが生み出しやすくなり、参加者からの認知と信頼が獲得できます。自社の商品・サービスとも関連づけやすく、成果の出るセミナーを実現可能です。
企画の方針が決まったら、提供価値がひと目でわかるセミナータイトルを作成してみましょう。20〜30字程度を目安に短くまとめると、重要な情報が端的に伝わります。
タイトルは集客でターゲット層の興味を引くのに役立つだけでなく、セミナー全体の軸となるため、プログラムなどの詳細を具体化するときも目的からブレていないかの基準になります。運営チームの連携力向上にもつながるでしょう。

参加者にどのようなメリットがあるのか、どのような課題を解決できるのか、競合のセミナーとはどのような点が異なるかを短く簡潔に言語化するのがポイントです。「売上◯%アップ」のような数字や、業界トレンドのキーワードを加えるのも効果的。また「製造業」「マーケター」といった、セミナーの対象者も具体的に提示すると、ターゲットにスルーされにくくなるでしょう。
セミナーの詳細を具体化
開催形式・日時・開催場所・講師・プログラムなども、告知・集客のときに漏らさず伝えられるようにこのタイミングで具体化していきます。A案とB案のどちらにすべきかなど、判断に迷ったときは、つねにあらかじめ設定した目的・ターゲット・企画内容に立ち返るようにしましょう。
セミナーの「開催形式」は会場に参加者を集めるリアルセミナー、オンラインで完結するウェビナーの大きく2種類。
リアルセミナーは参加者との対面形式のため、信頼関係を構築しやすく臨場感のあるイベントになりやすいのがメリットです。ただし会場の手配・設営や当日運営には相応の人員・時間・コストが必要になるでしょう。
ウェビナーはウェビナー配信ツールを利用することで、手軽に低予算で開催できるのが利点。参加者が自宅・オフィスなどから視聴できるため、リアルセミナーと比べて大人数を集客しやすいという特徴もあります。セミナー開催の予算やリソースを最小に抑えたい場合におすすめの開催形式です。
リード獲得やナーチャリングにはウェビナー、商談獲得にはリアルセミナーなど、目的に応じて使い分けるのもひとつでしょう。
「開催日時」はターゲット層の仕事・生活のスタイルを基準に参加しやすい曜日・時間を設定します。
たとえばBtoBセミナーの場合、ターゲットは業務時間中にセミナー参加するケースが多いため集客しやすい日時は平日の日中から夕方にかけて。
一方、BtoCセミナーは業務中の参加が難しいため休日または平日の退勤後の時間帯が無難です。平日であれば業務量が多くなりやすい月曜日と金曜日を避けて、水〜木曜日に設定すると参加率アップを期待できるでしょう。
ただし主婦層や個人事業主などを集客するなら、平日の日中の方が参加率は高いかもしれません。またGWや夏休み・年末年始などはプライベートの予定が入っている可能性もあるため、集客に苦労する可能性があります。業界・自社の繁忙期や、競合他社のセミナーの日程とかぶらないように調整することも大切です。

リアルセミナーであれば、日程が決まったタイミングですぐに「開催場所」の手配を進めましょう。着手が遅れると、目標とする集客人数に適した会場が確保できないリスクがあります。結果として、セミナーの規模縮小を余儀なくされたり、必要以上に大きな会場をレンタルすることで余計な費用がかかってしまう場合があります。
「開催場所」の選定基準として挙げられるのは、参加者のアクセスのしやすさ、キャパシティ・利用料金などです。たとえばターミナル駅から徒歩10分圏内の会場や、近くにランドマークがあり土地勘がない人にも場所がわかりやすい会場なら、参加者が迷うことなく会場にたどりつけるでしょう。
ウェビナーの場合には自社オフィスからでも配信が可能。騒音・映り込みなどの問題があるときはレンタルスペースを利用する方法もあります。その場合、混雑時には通信が不安定になるケースも少なくないため、有線LANに接続できる環境を選ぶと安心です。
講師を外部から招く場合や、セミナーを他社と共催する場合にも、早め早めの対応が重要です。現在は講師や共催企業を探せるサービスやマッチングサイトも存在するため、効果的に活用することで、スムーズに手配が進みます。
講師を選ぶときにとくに重要な基準は、権威性と依頼料のふたつ。業界・分野の第一人者や、希少性の高い実績・資格の持ち主など、権威性がある講師ほどターゲット層への訴求力は強まるでしょう。反面、依頼料も高くなる傾向にあるため、予算感を考慮しつつ最適な講師を選定する必要があります。
共催する企業は集客したいターゲット層が重なっていること、かつ競合関係にないことが条件です。スピーディーに準備を進めるために、企画内容やコンセプト、役割分担などを明確にした状態での依頼を心がけましょう。
集客の事前準備
セミナーの詳細が決まったら、いよいよ集客に向けた準備をはじめましょう。事前準備でやるべきことは大きく下記のとおりです。
・集客手法の選定 ・訴求メッセージの作成・バナーの作成・セミナー専用ページの作成
セミナーの集客手法は集めたいターゲット層によって決まります。
すでに接点のある見込み顧客を集めるならハウスリストへのメールが効果的。一斉送信により、時間・手間・コストをかけることなくセミナーを周知できるでしょう。最近は、LINEの公式アカウントを活用する企業も増えてきました。スマートフォンから友達追加するだけで登録できる気軽さや、アプリ自体の親しみやすさ、コストパフォーマンスなど、ハウスリストへの情報発信にも効果的なツールといえます。
とくにターゲット像に近い顧客には、個別のメールやLINE、電話などで周知をするのもひとつです。顧客情報や過去の問い合わせ内容に基づき、課題・ニーズにピンポイントで訴求できるため、集客率アップが期待できるでしょう。
対して、新規顧客にアプローチする方法としてはたとえば下記が挙げられます。1つの手段に絞るのではなく、活用できる集客ルートはすべて活用するのが、集客成功の秘訣です。
・自社サイト・SNS・ポータルサイト・Web広告
自社サイトやSNSは低コストで運用できるうえに、はまると集客力が高い手法です。
とくにSNSはインパクトのある訴求メッセージを提示できると拡散により幅広い層にアピールすることが可能。ただしフォロワーがほとんどいない状態で、いきなり高い拡散力を実現するのは難しいでしょう。実際に閲覧者を増やすためには、継続的に価値のある情報を発信しつづけるなど中長期的な施策が欠かせません。
セミナー情報を掲載できるポータルサイトも、無料で活用できるサービスが数多くあります。費用を払うことでサイト内への上位表示や集客支援を行ってくれるサービスもあり、うまく活用すれば情報感度の高いユーザーにリーチできるでしょう。
とくに狙い目なのが、特定の業界・業種に特化したポータルサイト。閲覧者も関連する業界・業種のユーザーである可能性が高く、効率的に集客ができます。
Web広告はそれなりに費用がかかるものの、特定の検索キーワード・顧客層を指定することで狙ったターゲットにピンポイントで訴求できるのがメリットです。出稿するとターゲット層にすぐに広告が表示されるため、即効性が高いのも魅力。
Googleなどの検索プラットフォームのほか、SNS・YouTube・ポータルサイトなどに掲載できる広告形態もあり、高い集客力が期待できます。たとえばビジネスパーソンを集客する場合には、ユーザー層が多いFacebookやXへの広告掲載が効果的でしょう。

とはいえどの集客手法を選択する場合でも、大量の情報に埋もれさせないためには競合他社との差別化が必須。ターゲットの興味関心を引きつけるうえで重要になるのが、魅力的なタイトルと訴求メッセージです。
訴求メッセージには開催形式・日時・場所などの基本的な情報に加えて、タイトル同様に対象者やセミナーに参加することで得られるメリット・解決できる課題、具体的な数字などをわかりやすく記載します。
また講師の肩書やプロフィール、参加者特典もターゲットの参加意欲を喚起するのに効果的でしょう。即決を促すための早期申込特典など、条件付きの特典を用意するのもひとつ。特典の内容はターゲット層以外からの申込みを防ぐために、セミナー資料、アーカイブ動画、割引券、個別相談枠など、セミナーや自社の商品・サービスと関係するものを提示します。
SNSやポータルサイト、Web広告でターゲットの目を引くうえでは、セミナータイトルが大きく記載されたバナーの作成もおすすめです。セミナーの概要や講師の顔写真・肩書き・経歴などもわかりやすく配置すると、クリック率アップにつながります。
これらの施策と同時並行で、各集客ルートから誘導するセミナー専用ページ(LP)の作成も進めましょう。集客の位置づけとしては、各集客ルートでターゲット層の興味を引き、LPで参加を後押しするイメージです。
LPの出来はセミナーの集客力や費用対効果を大きく左右します。たとえばWeb広告では、LPに遷移した時点で広告費が発生するケースがほとんど。ほかのルートでも、LPの申込率が高ければ流入数が少なめでも問題なくなるため、集客は楽になるでしょう。
LPにはセミナー・講師のより詳細な情報やベネフィット、参加費の有無、定員数、具体的なプログラムを記載するとともに、申込みフォームを設置。疑問・不安を解消するQ&A、申込み後の流れ、当日のアクセス方法、過去の参加者のコメントなども掲載することでセミナーに興味を持った人が申込みに至るまでのルートを設計します。
なお申込みフォームの入力項目は、顧客情報を収集しようとするあまり数が多くなってしまう場合が少なくありません。しかし入力の手間が増えるほど離脱率は高まるため、項目数は氏名・会社名・電話番号・メールアドレスなど、最小限にとどめるのが無難です。
集客
開催日の3週間から1ヶ月前になったら、いよいよ集客をスタート。反応率を見ながら訴求メッセージやバナー、LPの内容を微調整して、より効果的な集客ルートを確保しましょう。
SNSは告知文がすぐに流れてしまうため、定期的に投稿する必要があります。
余裕があればその度に告知文を変更して、より効果的な訴求メッセージを検証するのがおすすめ。クリック率の高い文言が見つかればWeb広告などほかの集客ルートにも反映させることで、集客力の底上げが可能です。
告知を開始した直後はとくに申込みが集中しやすいため、事務局の体制を整えて備えましょう。問い合わせにはできるだけ迅速・丁寧に対応して、セミナーに興味を持ったターゲットの離脱を防ぎます。
その後は徐々に反応がゆるやかになり、再び申込みが増加するのが、申込者のスケジュールが確定したセミナー開催1〜2週間前。集客のラストスパートでもあるため、Web広告やブログ・SNS・ポータルサイトでの告知頻度を上げて、集客目標の達成をめざしましょう。現在の申込状況や、残りの定員数を報告するのも効果的です。
あわせて実施したい集客戦略が「リマーケティング」。LPを訪問したものの申込みに至らなかったターゲットに、改めてセミナーを訴求する手法です。たとえばWeb広告のひとつであるリターゲティング広告を活用すれば、LP訪問者に再度広告を表示させることができます。URLをクリックした対象者に、メール・電話でアプローチする方法もあります。
リマーケティングを行うとき、ターゲットにとって既知の情報を繰り返すと、迷惑がられてしまうリスクがあるため注意が必要です。訴求しきれていなかったセミナーのメリットの提示、特別待遇での招待など、切り口を変えてアプローチすることで再検討を促せるでしょう。
また、申込者には申込直後の招待メールに加えてリマインドメールを送信することで、キャンセル防止につながります。
送信のタイミングは開催日の2週間前・1週間前・3日前・前日、当日の朝などが目安。改めて日時・メリット・参加特典をアピールすることで、リマインドだけでなくモチベーション維持の効果も期待できるでしょう。
当日運営の準備
集客と並行して当日運営の準備も進めます。満足度が高いセミナーを実現するためにはこの事前準備がとても大切です。
多くの参加者を集めることに成功しても、当日運営の進行やプレゼンがうまくいかなければ、リード獲得や商談化などの目的は達成できません。それどころか、企業としての信頼感を失うなど、マイナスプロモーションになってしまう可能性もあります。
そのため、当日の資料やスライド・アンケートなどを作成するだけでなく、円滑な運営を実現するための準備にもしっかりと時間を使うことが重要です。
具体的には、スタッフ間で業務分担や連携方法・トラブル発生時の対処法を共有。運営マニュアルや台本に落とし込んだうえで、複数回のリハーサルを実施して本番に備えましょう。リハーサルでは、マイクやスピーカー、プロジェクター、カメラ、ウェビナー配信ツールなど、機材のチェックも入念に行います。
加えて、アフターフォローのための準備もあらかじめ整えておきます。
セミナーがその後のリード獲得・商談化につながるか否かは、アフターフォローの質とスピードにかかっていると言っても過言ではありません。アフターフォローの反応率はセミナー終了から時間が経過するほど下がっていくため、熱量が高い当日から翌日のうちに電話・メールなどで次のマーケティング施策を展開できるように、業務フローを具体化。また顧客の課題・ニーズごとに適切なアプローチができるように、セグメントの方略を決めておくことも重要です。

たとえば、セミナーの満足度が高く、すでに自社の商品・サービスへのニーズが顕在化している層には、商談化を目的としたセミナーに招待するなど、積極的なアプローチが効果的。逆に、購買意欲がまだそこまで高くないのであれば、リードナーチャリングを実施して、着実に関係性を構築していくのがセオリーです。
参加者だけでなく、申込みはあったものの当日参加に至らなかった欠席者のフォローも忘れてはいけません。欠席者は自社の潜在的な顧客である可能性が高いため、メールでアプローチして、次回以降のセミナー参加などを促します。
申込者・参加者のセグメントには、事前・事後のアンケートの回答結果が参考になります。アンケートの中身を作成するときは、次回以降のセミナーの改善を目的としたものにとどまらず、アフターフォローやその後のマーケティングも見据えて設計しましょう。
ウェビナーであれば、セミナー中の視聴履歴・行動履歴や、コメント・質問・投票の内容なども貴重な情報源です。配信ツールにはこれらの情報を管理・分析をサポートする機能が搭載されているものも多いため、うまく活用することでアフターフォローの内容を最適化できます。
人員不足で手が回らないときは、MAツール・CRMを活用してアフターフォローを効率化するのもひとつでしょう。参加者情報の管理・分析やセグメント、メール送信、次回以降のセミナーへの招待など、業務の多くを自動化できるため、担当者の負担を大幅に減らすことが可能です。ウェビナーの場合には配信ツールと連携することで、アンケートやセミナー中の行動ログ・質問・コメントなども加味して、より効果的にマーケティングを展開できます。
当日の講演以外をすべて代行する「マジセミ」
以上、セミナーの企画立案から集客・開催までの流れを網羅的に紹介しました。
開催のための業務が多岐にわたるセミナー。実際に成果を出すためには、社内のリソースと開催ノウハウの蓄積が欠かせません。
「できるだけ最短でセミナーを成功させたい」とお考えの方におすすめなのがセミナー運営代行サービス「マジセミ」です。
年間1000回のセミナー開催ノウハウを活かして、主催企業様の代わりに企画・集客・事前準備・当日運営・アフターフォローを実施。当日の講演以外のすべての業務をおまかせいただけます。
とくにIT業界・製造業の集客実績は国内トップクラスです。200,000件のハウスリストを活用して毎年50,000人以上を動員しており、「本気の参加者を集客できる!」と量・質の両方で好評をいただいています。
料金は集客人数による完全成功報酬型なので、コストパフォーマンスの高さも業界屈指。
「初めてのセミナー開催でノウハウがない」「セミナー開催の負担をできるだけ軽減したい」という担当者様・企業様は、ぜひマジセミの利用をご検討ください。