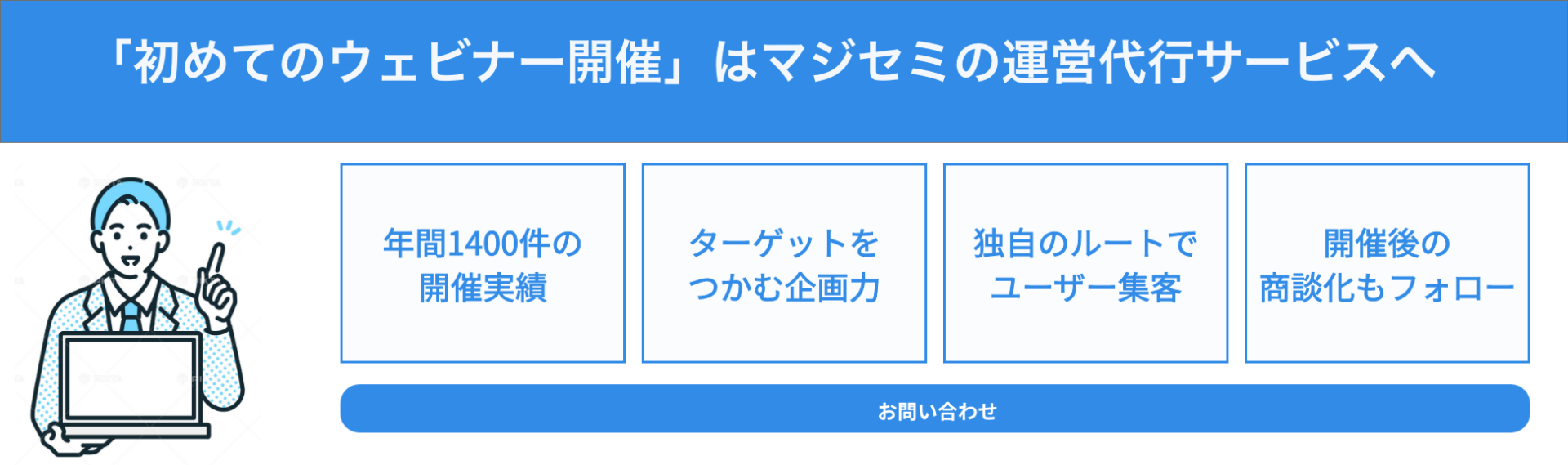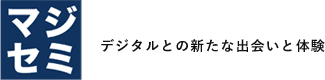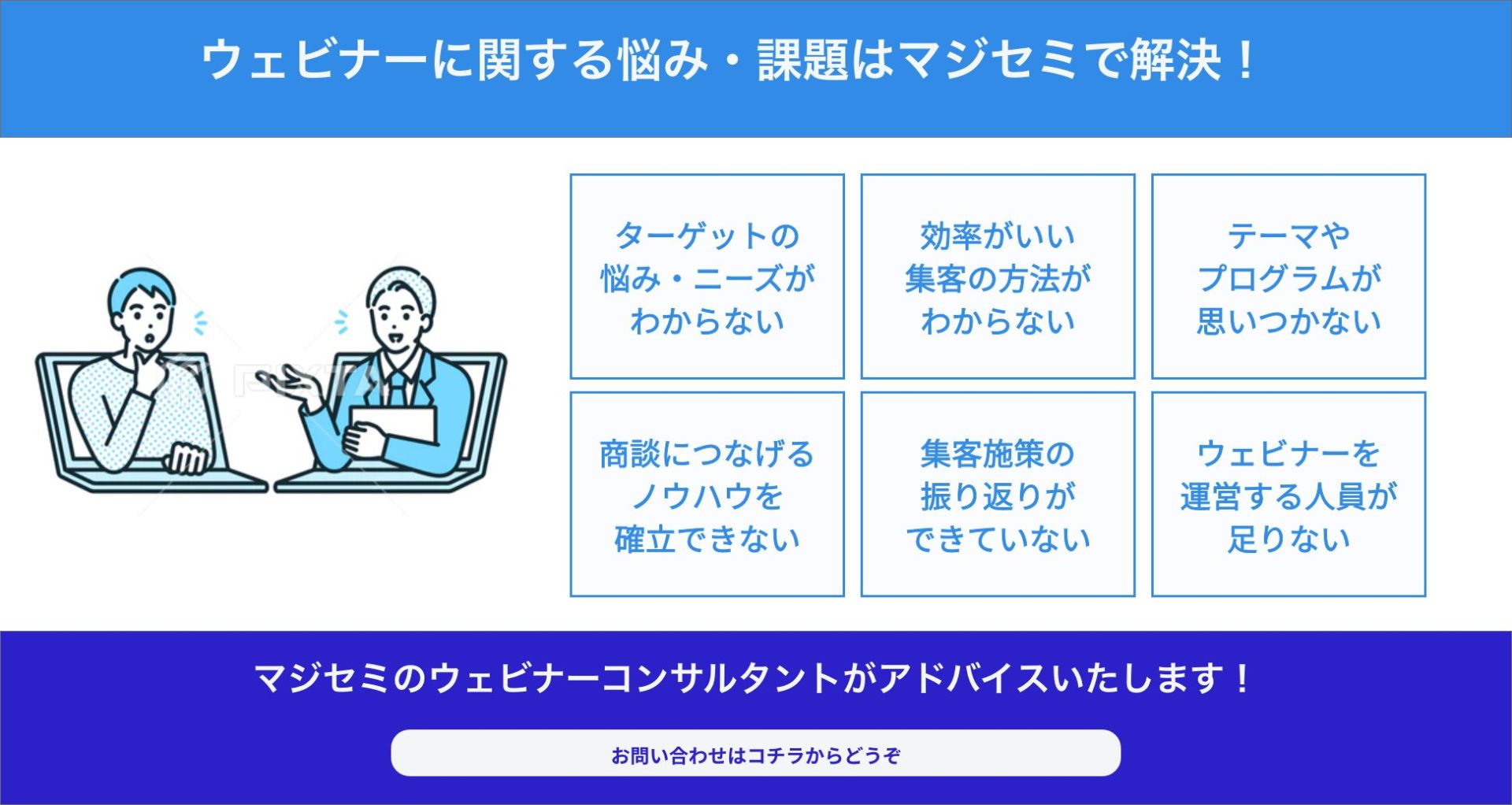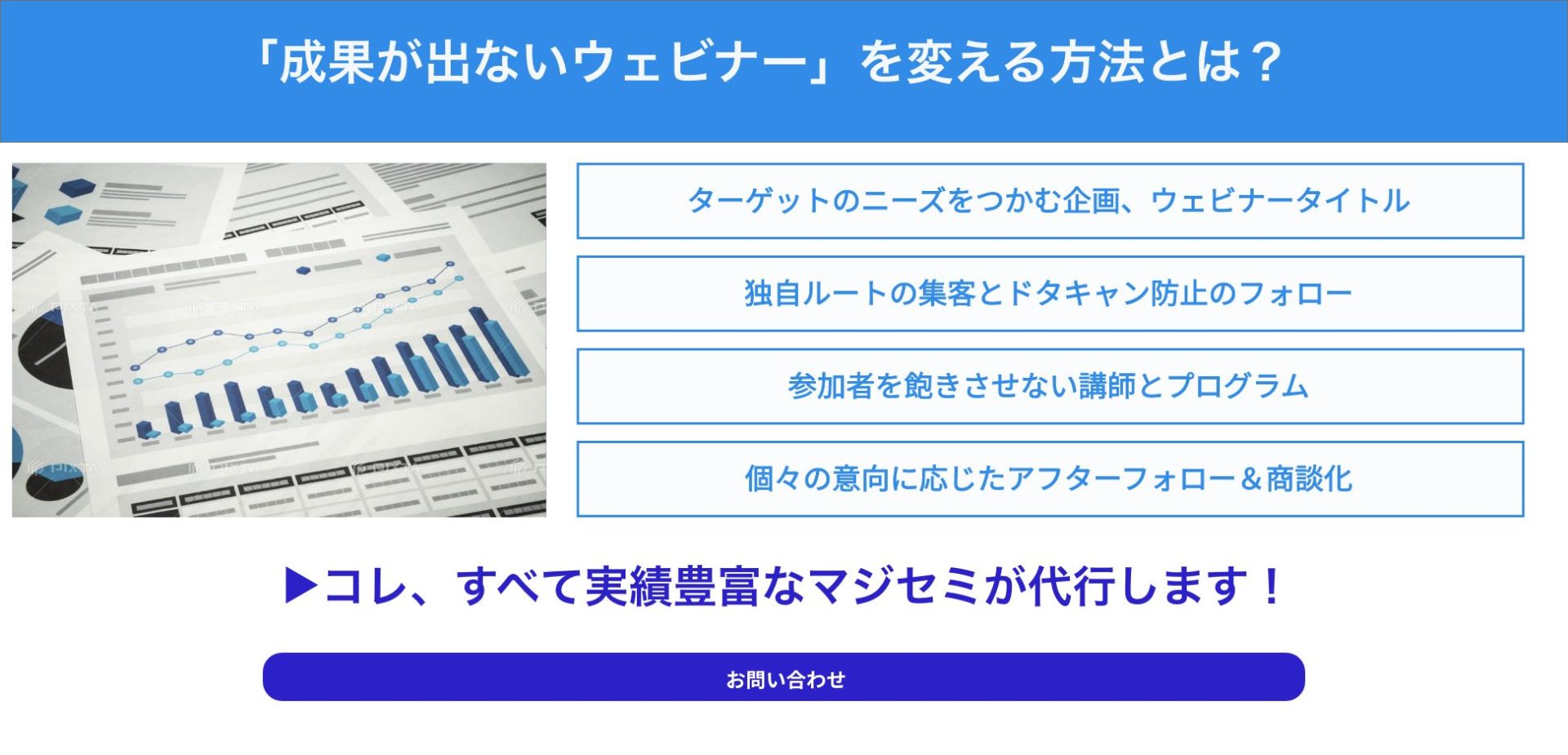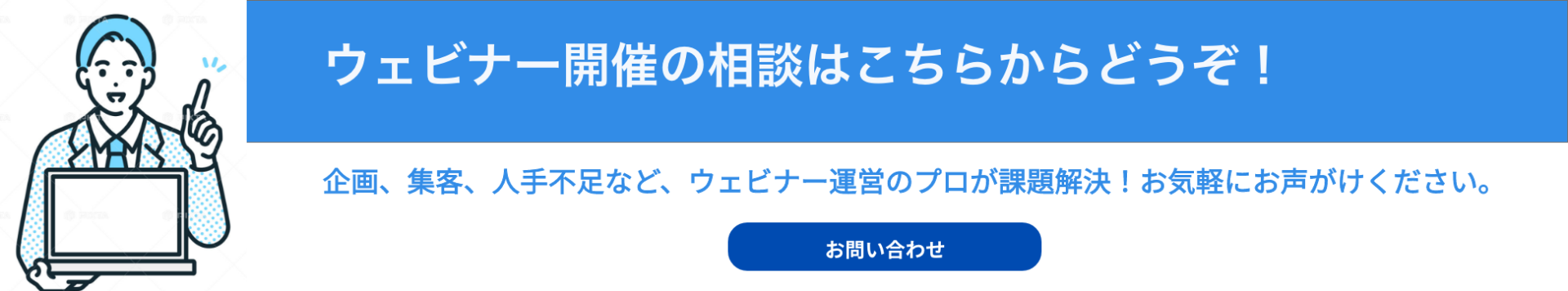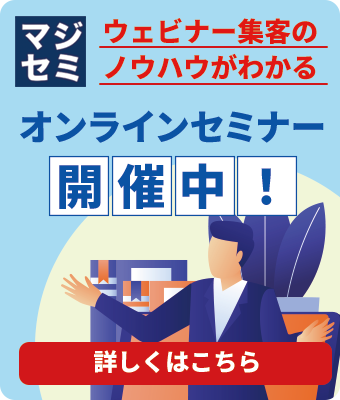多くの人が気軽に参加できる、費用対効果が高いなどメリットが多いウェビナーは「コンテンツを二次利用しやすい」のも魅力です。
二次利用とは、リアルタイムで配信したウェビナー動画やその内容を再度利用すること。追加の工数・コストをほとんどかけることなく、効果的な集客やリードの獲得・ナーチャリング・商談化をねらえます。
今回はウェビナーを二次利用する具体的な方法と、あらかじめ心がけておきたいポイントを解説。ウェビナー開催の効果を最大限に高めたいという担当者様・企業様は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
ウェビナーを二次利用する方法
ウェビナーを二次利用する方法として、まず挙げられるのがコンテンツやスライドの「別媒体での再利用」です。
メールマガジンやブログ・SNSなどで情報収集する顧客層は、動画で情報収集をする層とは異なるケースが少なくありません。そのため、ゼロからコンテンツを制作する手間をかけずに、認知拡大やSEO対策、登録者・フォロワーの増加などに寄与する高品質な情報が発信できます。
とくにブログ・SNSは有益情報を定期的に発信することで、リード獲得や過去の参加者のナーチャリングにも活用できるなど、ウェビナーとのシナジーを発揮しやすいメディアです。ビジネスパーソンからのフォロー獲得をねらうなら、FacebookとXは有力なツールになります。
まだ本格的な運営をしていない場合には、コンテンツの二次利用をとっかかりに、ぜひ取り組みをスタートしてみてください。
読者からのニーズが高いのは、ノウハウやハウツー情報を紹介するコンテンツ。ウェビナーで活用したビジュアル資料なども盛り込みつつ、具体的な方法論をわかりやすく解説することで、顧客層を惹きつけることが可能です。
また応用編として、ウェビナー開催の模様をレポート形式で紹介するというアイデアもあります。
先述した自社メディアのコンテンツとして、ブランディング・集客・ナーチャリングに活用できるだけでなく、「当日の参加者がウェビナーの内容を復習できる」「社内のメンバーに取り組みを共有できる」のもメリット。
レポートの内容は、ウェビナーの企画内容や概要、集まった参加者の数と層、発信したメッセージ、最終的に獲得した成果・反応など、当日の状況や雰囲気を描写するのが効果的です。加えて講師がプレゼンしている模様などを画像で紹介すると、雰囲気が伝わりやすいレポートになるでしょう。
ただし盛り上がりを過剰にアピールするのは逆効果。ウェビナーの宣伝だと思われないように、客観的な表現を心がけるようにします。
参加者からの質問は、ほかの読者層にとっても知りたい内容である場合が少なくありません。そのような質問への回答をまとめれば、それだけで独自情報を詰め込んだ記事が作成できます。
ウェビナーのアンケートや投票などで得たデータなどを公開するのもひとつ。データを分析したうえで、短いコメントなども付け加えると、読み応えのある記事になります。
ウェビナーの内容だけでなく、開催の経緯や主催企業の思い、参加者の声などを多面的に盛り込むことも可能です。参加者からのコメントや満足度などのデータは、次回以降のウェビナーに向けて、閲覧者の参加意欲を高める効果も期待できるでしょう。

「オンデマンド配信」も二次利用の効果的な方法のひとつです。
オンデマンド配信とは、録画したウェビナー動画を公開することで視聴者が任意のタイミングで視聴できる配信形式。リアルタイム配信のような双方向のコミュニケーションは取りにくいものの、開催日時の制約がなく、より多くのターゲット層にリーチできます。
当日参加できなかった人の受け皿として、次回以降のウェビナーへの参加を促す機能も期待できるでしょう。余計な部分をカットしたり、テロップを挿入したり、講師の声を聞き取りやすくしたりと動画を編集することで、より高品質なコンテンツに仕上げられるのも魅力です。
会場で開催するセミナーと比べて、オンライン完結のウェビナーは内容を簡単に録画できます。
ウェビナーツールには録画機能が標準搭載されているケースも少なくありません。たとえばZoomウェビナーは、レコーディングボタンひとつで録画をスタートできます。録画した動画の保存先は、デスクトップなどへのローカル環境に加えて、Zoomのクラウド内を選択することが可能です。
動画の掲載場所としては、ホームページやブログ、SNS、プレスリリース、YouTubeをはじめとする各種動画サイト、セミナー集客サイトなどが挙げられるでしょう。過去動画が豊富なら専用のアーカイブページを作成するのも一案です。
動画の希少性を保ちたいときや視聴者層を絞りたいときは、あらかじめ日時を指定して限定公開するという手もあります。特別感のある限定公開は視聴者がモチベートされやすくなるため、視聴率も高くなる傾向にあります。ちなみに一般的な視聴期間の目安は2週間程度。パスワードの設定も、視聴範囲をコントロールするのに有効です。
「次に開催するウェビナーへの参加」「アンケートへの回答」「メルマガへの登録」など、促進したい行動の「特典」としてウェビナー動画をプレゼントするのもおすすめ。
ホームページに専用フォームを用意して、顧客が氏名・メールアドレス・企業名などを入力することで動画をダウンロードできるという形にすれば、新規リードの獲得にも役立ちます。プレゼン資料・レポート資料などとセットにすれば、さらに訴求力が高まるでしょう。
オンデマンド配信の視聴者や動画をダウンロードしたユーザーには、リアルタイムのウェビナー同様アフターフォローを実施します。メールマガジンやSNSの紹介、ウェビナーへの招待などを行ってリード獲得につなげましょう。
短く編集したウェビナー動画を、ウェブ広告・SNS広告として掲載する方法もあります。とくに効果的なのは、ビジネスパーソンのユーザーが多いFacebookや、動画広告との相性がいいYouTubeへの広告掲載です。
広告なら幅広いターゲット層に自社やウェビナーを周知することが可能。新たに広告用の動画を制作する必要もないため、コスト削減につながるのも、ウェビナーを二次利用する利点といえるでしょう。

ウェビナーを二次利用するために心がけること
ウェビナーをさまざまな方法で二次利用するうえでは、普遍性のあるテーマ設定が効果的です。幅広い層が興味をもつ内容であれば媒体や公開範囲を限定せず、汎用性の高いコンテンツとして展開できます。
やや上級者向けのノウハウですが、プログラムも二次利用を見据えて最適化するのが理想。たとえばスライドや資料は、補足説明がいらないレベルのものを用意することで、コンテンツとしての提供価値が高まります。視認性やビジュアル要素、高級感のあるデザインも、資料としてのクオリティを考えるうえでは大切なファクターです。
ウェビナー中の参加者への質問・投票・アンケートにも、自社の情報収集目的だけでなく、二次利用時の情報価値を考慮した項目を用意しましょう。その際のターゲット層は、ウェビナーの参加者層と必ずしも一致していなくても構いません。
ウェビナーの構想段階で「どのようなハウツー記事・レポート記事・SNSへの投稿を展開できるか」「リアルタイム配信とオンデマンド配信の両方に適したコンテンツはどのようなものか」「二次利用も含めてどのようなターゲット層にアプローチしたいか」という視点を持ちながらアイデアを考えると、二次利用しやすい企画を立ち上げやすくなります。
ただしオンデマンド配信はリアルタイム配信と異なり、コメントや質疑応答などで参加できないため、どうしても視聴者の注意力が散漫になりがち。そのため最後まで集中してもらうために、テロップの挿入や冗長な箇所のカットなど適宜編集を行いましょう。
編集動画は、視聴者の心理状態をつねに意識しながら、退屈させない構成を心がけます。プレゼンだけでメリハリをつけるのが難しいときは、べつの動画や補足情報を挿入したり、BGMで盛り上がりを演出するのもひとつです。口頭の説明だけではわかりにくい部分には、別途イラストや図表などを用意するのがおすすめです。
オンデマンド配信の一般公開・配布は、リアルタイム配信が終わってからできるだけ早いタイミングで行うのが効果的。時間が経過するほど情報の鮮度やターゲット層の熱量は下がっていくため、スピーディーな編集が重要になります。
自社に十分なノウハウがない場合やリソースが不足している場合には、外部の専門家に編集を委託しましょう。高品質な動画が仕上がれば、自社ブランディングの効果も期待できます。
ウェビナーの動画・資料をそのまま公開する場合、権利関係をクリアにしておくことも大切です。
たとえば講師に無断で講演内容を公開してしまうと、著作権や肖像権などの侵害にあたる可能性があります。二次利用の展開方法に関しては、講師ともあらかじめ打ち合わせをして、トラブルがないように認識を合わせておきましょう。
またスライドなどに用いる画像・素材の著作権にも、十分に注意が必要です。フリー素材を利用する、制作者から許可を取る、商用利用ができる有料の画像・素材を購入するなどの方法で対処します。
参加者の顔や本名・個人情報が含まれる動画は、逐一編集や許可が必要になるなど公開ハードルが上がってしまうため、事前の対策が重要です。必要に応じて、ウェビナーの冒頭で参加者への協力要請やアナウンスを行いましょう。自社の機密情報や、競合他社に知られたくない情報に関しても、取り扱いには十分な注意が必要です。
公開範囲を限定する場合でも油断は禁物。リークなどにより情報が流出してしまう可能性はゼロではありません。
視聴者への注意喚起や、資料・動画をダウンロードしたユーザーの把握をはじめとするセキュリティ体制の徹底もさることながら、コンテンツ作成の時点で「本当に情報を公開して問題ないか」をしっかりと吟味することが大切です。
アーカイブ動画が増えすぎると、公開期間を過ぎているのに放置してしまったり、公開すべき動画が公開されていなかったりと、混乱をきたしてしまう可能性もあります。動画は管理用のリストと掲載・削除のフローをつくり、間違いのない運用を心がけましょう。期間が過ぎたら自動的に非公開になるように設定するなど、自動化できるところは自動化しておくと、管理の負担を抑えることが可能です。
加えて、公開動画はジャンルや課題・ニーズ別にカテゴライズしておくと、参加者が興味のある動画を選びやすくなり、視聴回数アップにつながります。
オンデマンド配信や動画ダウンロードは、小まめに効果測定をして、分析・改善による成果向上をはかりましょう。効果測定には、クリック率・視聴率・離脱率・コンバージョン率などの数字や、コメント・質問などの定性的なデータが参考になります。
これらの情報から改善案を考え、次回以降のウェビナーや二次利用の戦略に反映します。その後、ターゲット層の反応がどのように変化したかをチェックすることで、リード獲得・ナーチャリング・商談化をさらに加速させることが可能です。
ウェビナー・ワンストップ支援なら「マジセミ」
以上、ウェビナーを二次利用する具体的な方法や、心がけたいポイントについて解説をしました。
ウェビナー開催の効果をさらに高めたいという担当者様におすすめなのが、ウェビナー運営代行サービスの「マジセミ」です。
年間ウェビナー1000回開催で培ったノウハウと、企画・集客・準備・当日運営のトータルサポートで、リード獲得・商談獲得にコミット。成果報酬型のサービスのため、高いコストパフォーマンスを発揮します。
IT業界・製造業の集客力にはとくに定評があり、200,000件の独自ハウスリストで情報感度の高いターゲット層を集めることが可能です。動員人数は毎年50,000人を超えており、日本マーケティングリサーチ機構の調査で「集客に強いセミナーNo.1」に選ばれた実績があります。
また情報システムやセキュリティ担当のユーザーが多い自社運営のウェビナー情報サイトに、アーカイブを掲載できるのも強み。ウェビナー参加者の集客もふくめて、多くの新規顧客にリーチできます。
「ウェビナーで効率的に成果を上げたい」「二次利用もふくめてウェビナーの効果を最大化したい」とお考えの方は、ぜひマジセミの利用をご検討ください。