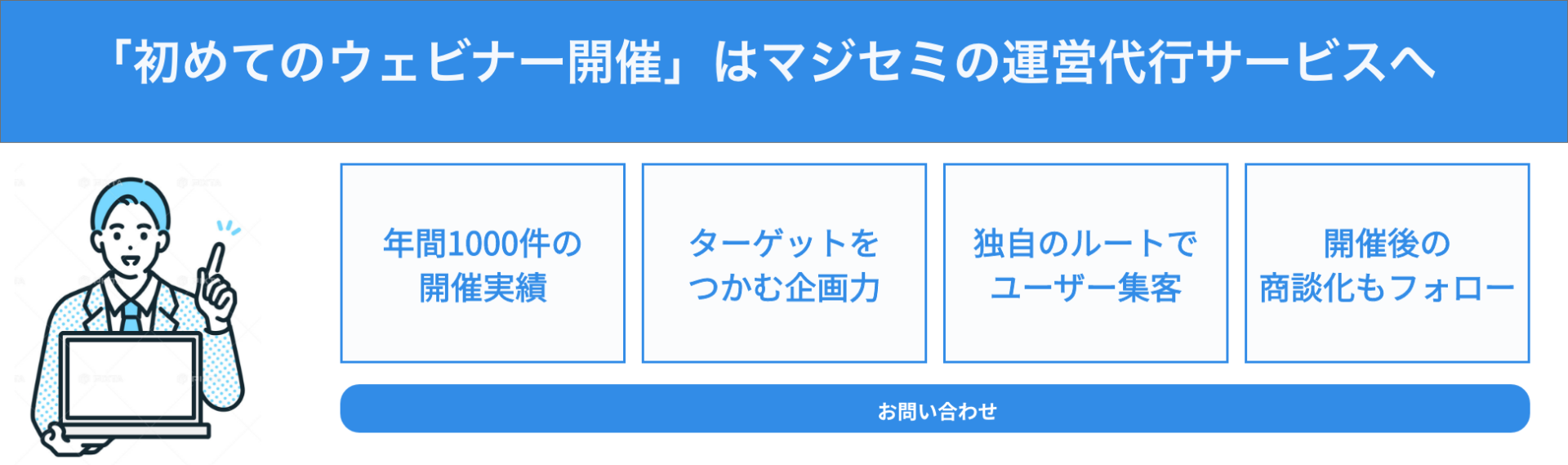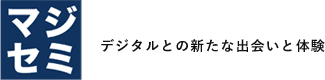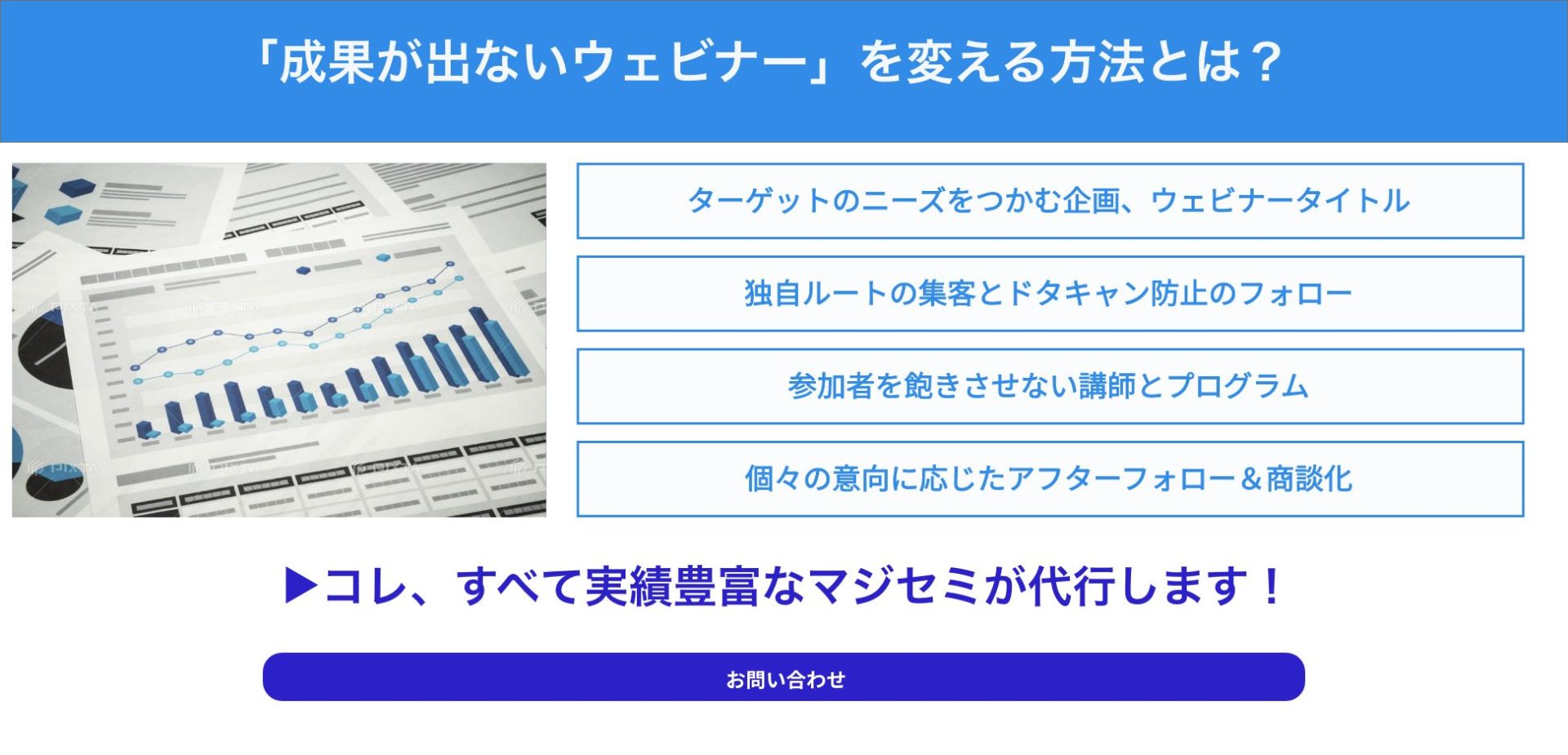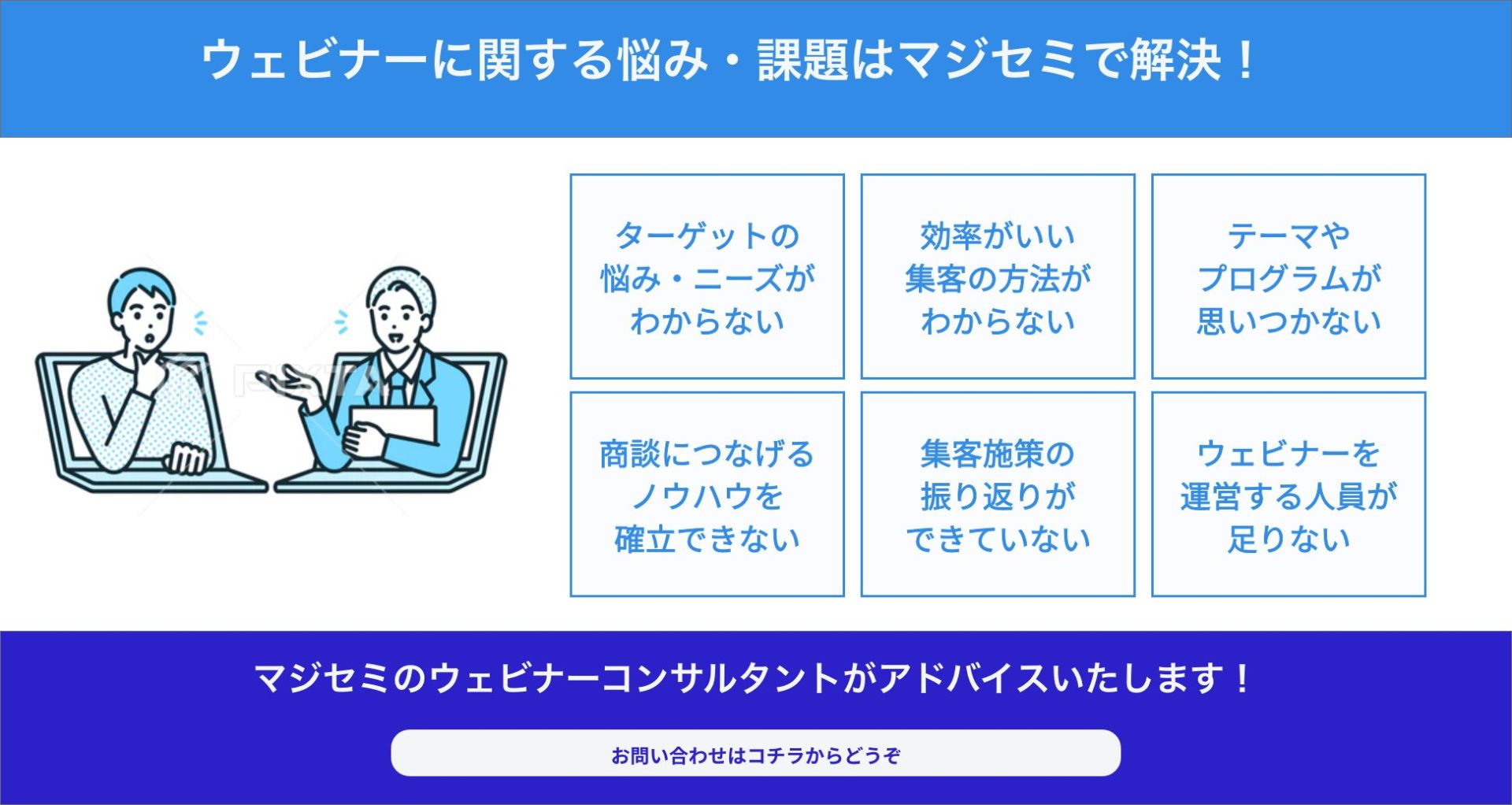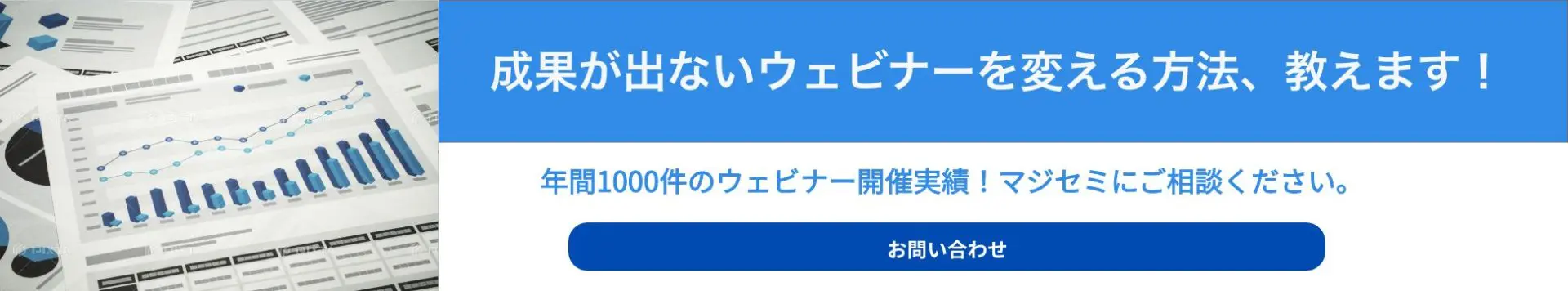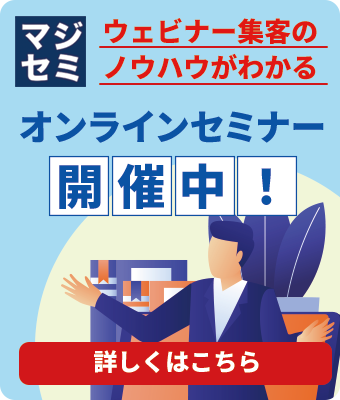会場で実施するセミナーと比べて、オンラインで完結するウェビナーは開催ハードル・集客ハードルが低く、マーケティング手法の主流になりつつあります。
一方で、参加者に直接アプローチできるわけではないため、開催直後の商談獲得は難しい傾向に。ウェビナーの成約率を高めるためには、講義内容の質を高めるだけでなく、開催後のリードナーチャリングが欠かせません。
ウェビナー開催後のアンケート・レポートの作り方次第で、マーケティング効果が大きく異なります。
そこで今回はアンケート・レポートの効果的な作り方を紹介。ウェビナーをより成功させたい担当者様、成約率を課題とする企業様は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
ウェビナーアンケートの目的
アンケートの項目は目的に応じて設定することが基本です。まずはアンケートを実施する主要な目的を押さえておきましょう。
リードの獲得とナーチャリング
ウェビナーアンケートの最大の目的は、参加者の詳細な情報を収集してナーチャリングにつなげることです。参加者の属性や参加動機、課題、商材への関心度を把握することで、個別商談へ移行するか、次回のウェビナーへ招待するか、一人ひとりにパーソナライズされたフォローアップが可能になります。
商材への興味関心度合いがわかれば、参加者の熱量に応じて積極的にアプローチすべきか、中長期的にナーチャリングすべきか判断できるでしょう。結果として、すべての参加者に同じ内容のメールを一斉送信するより反応率、成約率が高まります。
ウェビナーの改善
ウェビナーのアンケートは、コンテンツの品質と集客力を高めるための貴重なデータ源でもあります。参加者の満足度や理解度、改善要望を収集することで、次回開催に向けた具体的な改善点の把握が可能です。
不満な点、残念だった点の回答はコンテンツをブラッシュアップする材料となり、ポジティブな評価は「参加者の声」として次回集客の訴求に活用できます。ウェビナーの認知経路や参加のきっかけに関する回答からは、どの集客チャネルが効果的だったかを特定できるでしょう。
ウェビナーの企画・運営を継続的に改善するには、フィードバックの蓄積が不可欠です。
ウェビナーアンケートを作る手順
リードナーチャリングと良質なフィードバック獲得に結び付くウェビナーアンケートは、以下の手順で作成します。
- 1.まずアンケートの目的を定める
- 2.目的に応じてターゲットを定める
- 3.目的に応じて、必要なデータを取れる設問項目を決める
- 4.アンケートを取るタイミングを決める(項目と同時でも良い)
まずアンケートを収集する目的と、目的のために得たいデータを明確にしましょう。目的や必要なデータから逆算して、アンケートを実施する適切なタイミングと設問を組み立てます。収集すべきデータを洗い出して何を、どのタイミングで聞くか、設問項目に落とし込みましょう。
ウェビナーアンケートの実施タイミング
アンケートを実施すべきタイミングはウェビナーの開催前と開催中、開催後の3回です。各タイミングの特徴を理解し、戦略的に活用しましょう。
ウェビナー開催前
ウェビナー開催前に実施するアンケートは、参加者の氏名・職種・役職・電話番号・メールアドレスといった基本情報の収集が主な目的です。基本情報は講演内容の調整や開催後のフォローアップに活用でき、レポートを作成する際にも重要なデータとなります。
ウェビナーの内容に申込者の声を反映させるなら、「ウェビナーに興味を持った理由」や「期待していること」「聞きたいこと」などの設問を設けるとよいでしょう。多くの参加者ニーズに一致するコンテンツを提供することで、満足度アップをねらえます。
ウェビナー開催中
ウェビナー開催中は、投票機能やチャット機能を活用したアンケート収集が可能です。講演内容への理解度チェックや質疑応答、意見収集をリアルタイムで実施することで、対面と同様の双方向性を実現できます。Zoomウェビナーなどの投票機能を使えば、集計結果が即時に表示され、場の盛り上がりにも一役買うでしょう。
参加者の関心が高いうちに回答を得られることも、開催中にアンケートを実施するメリットです。クロージング前に回答時間を設けると回答率が高まります。
ウェビナー終了後
ウェビナー終了後は、アンケートで参加者のフォローアップと次回以降のウェビナーの改善に役立つ情報を収集できるタイミングです。
終了直後はウェビナー体験を踏まえた率直な評価を得られるため、内容や運営の改善点を明確化するのに役立ちます。リードナーチャリングの面では「商品・サービスへの興味関心の度合い」を収集し、参加者の熱量に応じたフォローアップ方針の判断材料にします。導入検討時期や予算感、決裁プロセスなどの情報も収集できれば、営業効率をより高められるでしょう。
即座に回答を得られない場合は、終了直後のサンクスメールやリマインドの設定など、確実に回答してもらう工夫をしましょう。

ウェビナーアンケートの必須項目
質の高いデータ収集とリード獲得を実現するために、ウェビナーアンケートに必ず設置したい項目は以下の5つです。
基本情報
参加者の基本情報は、プロフィールを把握してセグメント分析や個別フォローを実施するための重要な項目です。業界や役職によって抱える課題やニーズ、訴求ポイントは異なるため、申し込みの段階で以下の情報を取得しましょう。
- ・氏名・会社名
- ・部署・役職
- ・業界・業種
- ・企業規模(従業員数・売上規模)
- ・連絡先(メールアドレス・電話番号)
会社情報があれば決裁権限や予算規模も推測が可能です。相手が入力する手間も考慮し、フォームはプルダウンなどの選択式設問をメインにしましょう。
参加動機や認知経路
参加動機と認知経路はターゲットの課題を探るヒントとなるだけでなく、施策の効果測定にも役立ちます。具体的な項目の例は以下の通りです。
- ・参加のきっかけ(課題解決・情報収集・競合調査など)
- ・認知経路(メール・SNS・Web広告・紹介など)
- ・現在抱えている課題やニーズ
- ・解決したい期限や優先度
参加動機は参加者の本気度と購買可能性の判断に、認知経路は効果的な集客チャネルの特定に必要です。
ウェビナー内容の評価
ウェビナーの内容に対する評価は、今後の品質と参加者満足度の向上につなげるための重要な項目です。多角的な評価項目を設けることで、改善すべきポイントがより明確になります。ポジティブな回答についても集客やコンテンツに活用できるので、以下の項目を設けて積極的に評価を収集しましょう。
- ・理解度(5段階評価)
- ・満足度(5段階評価)
- ・最も参考になった内容
- ・物足りなかった点・改善してほしい点
- ・講演時間の適切さ
参加者の理解度と満足度の数値化は、コンテンツの難易度や構成の見直しに必要です。特に「物足りなかった点」や「改善してほしい点」は、コンテンツのブラッシュアップに欠かせません。忘れずに質問項目を設けて次回のウェビナーにつなげてください。
ウェビナーに対する要望
ウェビナーに対する要望の項目も、次回以降の品質と参加者ロイヤルティを向上させるヒントになります。参加者の生の声には運営側が気づけない改善点や、新たなニーズが詰まっている場合が多いからです。
以下のような項目を設け、自由記述方式で書いてもらいましょう。
- ・今後取り上げてほしいテーマ
- ・開催形式の希望
- ・配信時間帯の要望
- ・資料提供方法の改善点
他社事例の紹介希望や、もっと詳しい解説が欲しかった分野なども把握できれば、企画の精度が大幅にアップします。次回告知時に改善点をアピールすることで参加者の期待値も高まります。
今後の参加意欲
今後の参加意欲を集計することで、次回集客の目安となるほか、効率的なリードナーチャリングが可能です。参加者の熱量を数値化することで、優先的にフォローアップすべき対象が明確になります。以下のような項目を設置しましょう。
- ・当社のウェビナーにまた参加したいと思いますか?
- ・希望するテーマを選択してください
5段階評価で次回参加への関心度を測定し、関心の高い参加者には新企画の優先案内や限定コンテンツの提供を行います。関心が低い場合は理由を聞くことで改善点を把握できるでしょう。
また、興味を持った分野や希望開催頻度なども併せて聞けば、参加者のニーズに合わせたウェビナーの立案につなげられ、顧客との長期的な関係構築に役立ちます。
商材への関心度
商材への関心度は、営業活動の優先順位付けに役立ち成約率向上の鍵を握る項目です。ウェビナー参加者の購買意欲を段階的に把握することで、商談化プロセスの効率化が可能です。
- 今回紹介した商材・サービスについて当てはまるものを選んでください
- ・詳細な資料が欲しい
- ・サンプル(事例)を見たい
- ・詳しく話を聞きたい
- ・導入を予定している
- ・すでに導入している
- ・興味なし
詳細な回答項目を用意することで、自由記述式に近い高精度な情報を得られ、参加者の関心度をより詳細に把握できます。

ウェビナーアンケートの回答率を高める方法
オンラインウェビナーでは対面セミナーと比べてアンケートの回答率が低い傾向があります。アンケートの回答率を高めるためには、参加者の回答の負担を軽減すると同時に回答への動機付けが必要です。
重要な質問だけに絞る
本当に必要な情報だけを厳選して設問化し、重要度の低い項目は削除しましょう。アンケートの質問数は5~7問程度に絞り込むことがポイントです。多くの情報を得たいといっても、10問を超えるアンケートでは参加者の集中力と意欲が削がれ、離脱の原因となってしまいます。
どうしても多くの情報が必要な場合は、以下の方法が良いでしょう。
- ・複数の情報を一つの質問で取得できないか検討し、類似する質問は統合する
- ・基本項目と詳細項目に分けて、段階的にアンケートを実施する
回答の負担感を軽減することで、得られる情報の質と量を担保できます。
選択式+自由記述のバランスに留意する
選択式と自由記述式のバランスによってもアンケートの回答率は左右されます。選択式は回答の負荷が少なく回答率を高めやすい反面、詳細な情報は得にくいことが難点です。一方の自由記述式は詳細で質の高い情報を得られる反面、回答の煩雑さから離脱を招くリスクがあります。
アンケート構成は選択式が7割、自由記述が3割程度が理想的です。基本情報や評価項目は選択式で効率的に収集し、要望や改善点など生の声が欲しい部分のみ自由記述にすると良いでしょう。選択式の回答に応じて自由記述が表示される条件分岐機能を活用する方法もあります。
回答を迷うような曖昧な質問も離脱される原因となります。「〇〇について、具体的にお聞かせください」と、回答しやすい質問文を心がけてください。
回答に対するインセンティブを提供する
アンケートに回答する動機付けとして、インセンティブを提供することも一つの方法です。参加者に以下のような特典を示すことで、ウェビナー開催後のアンケートの回答率向上が期待できます。
- ・ウェビナー録画動画
- ・講演資料のダウンロード
- ・関連ホワイトペーパーの無料配布
- ・商品の無料トライアル権
抽選によるプレゼントでも一定の効果はありますが、全員に提供できる特典のほうが訴求力は高くなります。インセンティブを事前に告知して期待感を高め、アンケート画面で再度表示するのも手です。ただし特典目当てのいい加減な回答を避けるために、回答に一定の品質基準を設けることも大切です。
リマインドやアナウンスを実施する
アンケートの回答を促すリマインドとアナウンスを実施しましょう。
例えば①ウェビナー終了直後、②翌日、③3日後の3回に分けてリマインドメールを送信し、回答を促すといった具合です。メールの件名は、緊急度に応じて「【重要】アンケートご協力のお願い」から「【最終】貴重なご意見をお聞かせください」へと表記を変えると良いでしょう。
もしくは、クロージング時にアンケートの重要性と所要時間を明示し、「皆様のご意見で次回ウェビナーがさらに良くなります」と参加者の協力意識に働きかける方法もあります。回答期限を明記したうえで、早期の回答には感謝を示しましょう。
ウェビナーレポートの活用方法
アンケートで収集した顧客データは、レポート化することで企業の成長を支える重要な資産となり得ます。ここではウェビナーレポートの活用方法を紹介します。
参加者フォローアップやリードスコアリング
ウェビナーレポートは営業活動の効率化と成約率向上に役立ちます。収集した情報を基にリードスコアリングを実施し、優先順位を明確化することで営業リソースを最適に配分できるからです。
例えば、商材への関心度、参加動機、役職、企業規模などの項目に点数を付与し、総合スコアで顧客をランク分けするといった使い方ができます。
- ・Aランク⇒直接商談の打診
- ・Bランク⇒事例紹介や導入支援コンテンツの提供
- ・Cランク⇒定期的な情報提供による関係構築
また、業界別や課題別にセグメント化したフォローアップシナリオを設計すれば、アプローチを個別最適化でき、長期的な顧客の獲得につなげることも可能です。
ウェビナーの改善
レポート分析による効果測定と改善点抽出は、ウェビナーの振り返りと継続的な品質向上に不可欠です。ウェビナーを定量・定性データの両面から分析することで、次回企画の精度を高められます。
- 1.参加率、満足度、理解度、退室タイミングなどの定量データから全体的な傾向を把握
- 2.自由記述の定性データから具体的な改善要望を抽出
満足度の低いセクションや退室者の多い時間帯を特定できたら、コンテンツ構成や説明を見直して改善を図る、といった具合です。
さらに、認知経路別の参加率や満足度を分析したレポートは、効果的な集客チャネルの特定に役立ちます。分析結果を次回企画に反映させることで、PDCAサイクルを回しながらウェビナーの品質を継続的に高められます。
マーケティング資産化
ウェビナーレポートは自社の専門性をアピールし、潜在顧客との接点を創る貴重なマーケティング資産でもあります。
レポートを適切に加工し公開することで、ブランド価値の向上と集客力の強化を同時に実現が可能です。例えば、参加者の声や満足度データを活用した成功事例として自社ブログに掲載したり、業界動向レポートとしてホワイトペーパー化したりすることで、SEO効果と専門性アピールの両方を狙えるでしょう。
特に、過去の参加者数や視聴維持率などの実績数値は、コンテンツの信頼性を高める要素となります。
ただし、活用するのは事前に公開許可を得た内容のみとし、個人情報の取り扱いには留意しましょう。適切にコンテンツ化されたレポートは将来的な集客材料となり、事業の持続的な成長に貢献します。
アンケート&レポートの作成もマジセミにおまかせ
「そうは言ってもアンケートとレポートを作成している時間がない」「集めたデータをどう分析したらよいかわからない」とお悩みの方におすすめなのが「マジセミ」です。
マジセミはウェビナーの企画・準備・集客・申込者対応・当日運営・参加者フォロー・振り返りを、ワンストップで支援するウェビナー運用代行サービス。
プランの提案から、開催後のアンケート・レポート作成・振り返りまでをひとつのストーリーに落とし込むPDCAサイクルにより、次回以降のウェビナー改善や商談化を見据えたウェビナーが開催できます。
また年間1,200回のウェビナー開催実績で培った企画力、150,000件の独自ハウスリストを活用した集客力も強み。とくにIT業界・製造業のウェビナーでは国内トップクラスの集客実績があり、「本気の参加者を集客できる」と好評です。
アンケート&レポートと集客の質を高めて成果につながるウェビナーを実現したい方、ウェビナーに必要な業務負担を軽減したい方は、ぜひマジセミの利用をご検討ください。