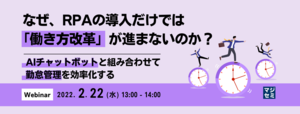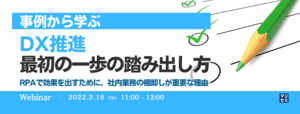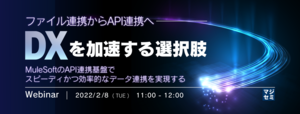業務自動化
Business automation
業務自動化の課題を解決するウェビナー
RPA、AI-OCR、iPaaSなどを活用した業務自動化に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。業界別の活用事例や業務効率化の方法、データ処理の改善についても学べる内容が揃っています。また、業務自動化の市場規模や最新の動向についても紹介しています。
業務自動化・効率化
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
物流会社向け!「紙業務」のデジタル化 ~受発注伝票・運転日報をAI-OCRで業務自動化~
3.6 東日本電信電話株式会社
本セミナーはWebセミナーです。
ツールはTeamsを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
まだまだ紙が多い物流業界、こんなお悩みはありませんか?
DXブームが到来し、物流業界でも急速にデジタル化が進んでいます。 しかし、まだまだ紙を用いた業務が多く残っているのが現状です。 以下のようなお悩みを多いのではないでしょうか。
・指示書や請求書などFAXでのやり取りが未だに多い ・売上が伸びた分事務員の人数が増えてしまいっている ・デジタル化と言っても何をすればいいのか分からない ・紙からPCへの転記業務に膨大な時間がかかっている ・デジタル化は高そうで手が出にくい
毎日2時間を紙の処理に費やしているのが現状です...
ある調査結果によると、 物流センター・配送センターで業務をしている人は 1人あたり平均で毎日約40枚の帳票を処理しており、約2時間も紙の伝票作業に時間を費やしていることが分かりました。 実際に、受発注はFAXでやり取りし、ドライバーの運転日報は手書きで行っている事業者も多いのではないでしょうか?
これらの現状を解決する一つの選択肢がAI-OCRです。
FAX・紙のデータ入力業務を激減させる方法をお伝えします!
AI-OCRをはじめとしたデジタルツールの導入において、下記のような懸念や不安があるかと思います。
・今いる従業員では、ツールを使いこなすことができるか不安だ ・自社の業務にマッチしたツールが分からない ・導入による費用対効果はどうなのか ・手書き文字、FAXの文字などの読み取り精度はどうなのか
そのような場合もご安心ください。 本セミナーでは、「生産性向上」「業務効率化」のツールとして注目を集めている AI-OCRの導入・活用方法を、物流会社で効果的に使える実例も交えながらお伝えします。 また、読取精度の高いAI-OCRの機能・特徴、事例紹介、製品デモも実施します。
こんな方におすすめ
・DXや業務自動化を命じられているが何から手をつけていいか悩んでいる ・自社の書類がどれくらい読み取れるのか知りたい ・紙からPCへの転記業務を何とか減らしたいと考えている
プログラム
13:45-14:00 受付
14:00-14:05 オープニング(マジセミ)
14:05-14:30 物流業(運送・倉庫)の受発注や日報が「紙ベース」「手書き」から抜け出せない(船井総研ロジ)
・物流業(運送・倉庫)の紙業務における課題 ・なぜデジタル化が進まないのか?
14:30-14:55 AI-OCRのご紹介(NTT東日本)
・AI-OCRの特徴・事例紹介 ・製品デモ
14:55-15:00 質疑応答
主催
東日本電信電話株式会社(プライバシー・ポリシー)
共催
船井総研ロジ株式会社(プライバシー・ポリシー)
なぜ、RPAの導入だけでは「働き方改革」が進まないのか? 〜AIチャットボットと組み合わせ...
3.7 株式会社電通国際情報サービス
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
「働き方改革」の必要性
労働者がワークライフバランスに合わせた働き方ができる社会を実現すべく、数年前から「働き方改革」の推進が始まっています。 「働き方改革」の処方箋として、RPAを活用されている企業も多いのではないでしょうか。 長時間労働の是正や柔軟な働き方の実現を目的としており、昨今のコロナ禍に伴うリモートワークの普及もその一環と言えるでしょう。 そんな状況において、各企業には従業員の健康や安全を守りながら事業を継続していくことが求められています。
リモートワークに伴い、勤怠登録・管理作業が煩雑に
しかし、リモートワークの普及には労働生産性の観点から見てマイナスな影響もありました。 事例として挙げられるのは、社員同士が物理的に離れた環境で仕事をするため、勤怠管理の手間が増えたことです。 従業員は上司への報告に加え勤怠管理システムへの登録作業が必要になり、管理者である上司は部下の勤務状況の確認や承認の手続きが必要になっています。 手間が増えたことで労働時間も膨らんでしまうため、かえってストレスフルな労働環境になっており、真に望ましい形で「働き方改革」が実現できていない実情があるのです。
RPAだけでは「部分最適」が限界
上記で挙げたような非効率な業務を是正する手段としてRPAがありますが、RPAを導入するだけでは業務全体をうまく効率化することは難しいです。
その理由は、RPAによる効率化は「部分最適」が限界であり、その部分
と部分
の隙間に、効率化が及ばない単純作業(いわゆるポテンヒット
)がやむを得ず発生してしまうからです。
AIチャットボットとRPAの組み合わせにより「働き方改革」を実現する
そこで本セミナーでは、RPAとAIチャットボットを組み合わせることで「部分最適」の限界を克服し、業務全体の効率化を実現する方法を紹介します。 おざなりになりがちな残業時間の把握や年休取得などを促す機能も有しており、「働き方改革」実現の一助となる電通国際情報サービス社のソリューション「チャットボットコンシェルジュ」についても紹介しますので、ぜひご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 なぜ、RPAの導入だけでは「働き方改革」が進まないのか?
13:45~13:55 質疑応答
主催
株式会社電通国際情報サービス(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
事例から学ぶDX推進最初の一歩の踏み出し方 ~RPAで効果を出すために、社内業務の棚卸しが...
3.5 ライトウェル
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
何から始めたら良いか分からず、取り掛かりが難しいDX
その必要性が広く謳われ、専任の部署や担当が立ち上がる等、多くの企業がDX推進にリソースを投じています。 ただ、DX推進を任されたものの、具体的にどう進めればいいか、何に留意すればいいのか、どうすれば失敗せずに進められるのか等が分からず、最初の一歩が踏み出せないという担当者も多いのではないでしょうか。
ただRPAを導入するだけでは効果が出ない可能性も
DXの第一歩として、RPAを導入して業務プロセスのデジタル化を行うという方法が考えられます。 しかし、RPAを導入する際には押さえておくべきポイントがあり、それが抜けてしまうと何の効果も出ず、せっかく導入した製品も使われずに放置されるという事態を招く可能性があります。
取り掛かりとして最重要なのは社内業務の棚卸し
RPA導入で失敗しないためには、まず社内業務の棚卸しをすることが重要です。 棚卸しをすることで、どの業務に問題があるのか、どこに手を打つべきか、改善点は何なのか等を明確にしてから注力する部分を見極めないと、RPAで明確な効果を出すことは出来ないのです。
棚卸しの方法と、RPAによる業務改善のプロセスをイグアスの事例をベースに紹介
とはいえ、棚卸しをどう行えばいいかわからないという方も多いと思います。 そこで本セミナーでは、RPAによって業務のデジタル化を実現したイグアス社の事例をもとに、社内業務の棚卸し方法とRPAによる業務改善のプロセスを紹介します。 DX推進の取り掛かりとして「何から始めたらいいか分からない」とお悩みのDX推進担当者や情シス担当の方は、ぜひご参加ください。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 RPAで効果を出すために、社内業務の棚卸しが重要な理由
11:45~12:00 質疑応答
主催
ライトウェル(プライバシー・ポリシー)
共催
株式会社イグアス(プライバシー・ポリシー)
知識ゼロでも導入できるRPA 非システム部門や現場担当者向け RPAの始め方
3.8 株式会社デリバリーコンサルティング
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
73%がRPAを知らない...いまさら誰も教えてくれないRPA
RPAとは一体何なのか?何ができるのか?いまさら誰かに聞けないとお困りではありませんか。
株式会社SheepDogの調査によると、会社員のRPA
の認知率は27%、使用経験があると回答したのは約13%という結果が出ています。
つまり全体の73%は「RPAをよく知らない」 ということです。
RPA導入でぶつかる壁
「DX推進」が叫ばれる中、「とにかくまず業務自動化をはじめよう」と、情報収集に駆け回る担当者も多いのではないでしょうか。 業務自動化の手段としてRPAを導入する際にぶつかる壁は共通しています。
社内に専門部隊やサポート体制がない
RPAで業務効率化できそうな対象業務件が少ない
費用対効果が見合うかわからない
導入後の副次的効果が見えづらい
RPAが大事だと理解しているが、社内を説得させられる材料がない
こうした理由から、RPAの検討を途中で諦めてしまう担当者も多くいます。
知識ゼロの方でもわかるように、60分で基礎を解説!
本セミナーでは「RPAの基本がよくわかっていない」初心者向けに、RPAの特徴、自動化業務の種類などを導入事例を交えながら解説します。 また、デリバリーコンサルティングが提供する簡単RPA「ipasロボ」の製品デモも実施するので、「RPAは実際にこういう風に動くのか」とイメージを持って頂けるかと思います。 はじめてRPA導入を検討される方も、一度導入してうまくいかなかった方も、奮ってご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:40 知識ゼロでも導入できるRPA 〜非システム部門や現場担当者向け RPAの始め方〜
■RPA基礎知識 RPA自動化業務とは RPAの対象業務とは 社内への説得方法
■RPA導入事例 1)経理部門の仕訳、請求、経費関連業務 2)購買担当者のFAXからの受注入力 3)配送事務の依頼書入力 4)サポート部門の問い合わせ業務 5)本部での各店舗からの勤怠、売上情報の収集
■ツール紹介 簡単に現場使えるツール「ipaSロボ」の紹介
■費用対効果 POCを実施する時の作業(業務)時間を測定
13:40~13:55 質疑応答
主催
株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)
電子帳簿保存法の改正、電子取引データ保存2年の猶予で、いま取り組むべきこと おすすめソフト...
3.6 東日本電信電話株式会社
本セミナーはWebセミナーです。
ツールはTeamsを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
電子帳簿保存法の改正、電子保存義務の2年猶予で、いま取り組むべきこと
2022年1月施行の電子帳簿保存法の改正により、紙ベースでの請求書は電子データで保存が必須だったため、環境整備を急いだ企業が多かったのではないでしょうか。 2021年12月の中旬、電子取引データ保存について2年の移行猶予がニュースになりました。
環境整備が間に合わなかった企業にとっては一安心ですが、 システム導入だけではなく運用手順の変更や社内規定の変更等を考えますとあまり猶予がありません。 「改正されたけど何から始めればばよいのか?」「すべての事業者が対象なのか?」「違法にならないようにするにはどうしたらよいのか?」 など、事業者が取るべきアクションを理解しきれていない方が多いのが現実です。 現在開催されている多くのセミナーでも、法改正の内容説明に終始しています。
2年間の移行猶予がある中でのジレンマ
法改正の認知、ソフトウェア導入もまだ進んでおらず、紙ベースでの仕事をメインにする事業者も多いことから、令和4年度税制改正大綱にて、改正施行に向けて2年間の猶予が設けられました。
そこで、事業者としては大きく3つの選択肢が与えられています。 ①移行を先延ばしにする →その場合に直近で必要な対応とは? ②インフラ、業務フローの見直しをしっかり行い、ペーパーレス化に移行する →2年の猶予を活用するための考え方、検討の手順 ③コストはできるだけ抑えて、取り急ぎペーパーレス化に移行する →システムの入替えも想定し、まずは電子帳簿保存法に準拠したものを導入する
ペーパレス化による作業効率化・コスト削減を成功させるためには、新しいシステムの導入だけでは十分ではありません。 実際に、どの帳票やワークフローを電子化すべきなのか、どんな仕組みを構築すべきなのか、かけるべきコストはどのくらいがよいのか、お悩みの方も多いのではないでしょうか?
電子帳簿保存法改正で取るべき対策を解説します。
本セミナーでは、「結局何をしたらいかわからない」電子帳簿保存法の改正内容と事業者が行うべき対策をわかりやすく解説します。併せて、電子データ保存ソリューション、ペーパーレス化に向けたAI-OCR活用事例もご紹介します。
プログラム
9:45~10:00 受付
10:00〜10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:15 電子帳簿保存法の改正ポイントと、事業者がとるべき選択肢(芙蓉総合リース)
10:15~10:25 電子帳簿保存法対応に関するよくある質問(NTT東日本)
10:25~10:40 電子データ保存ソリューション「ClimberCloud(クライマークラウド)」紹介(NTTデータビジネスブレインズ)
10:40〜10:50 電子帳簿保存法改正に伴うAI-OCR活用方法(NOCアウトソーシング&コンサルティング)
10:50〜11:00 質疑応答
主催
東日本電信電話株式会社(プライバシー・ポリシー)
共催
NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社(プライバシー・ポリシー)
芙蓉総合リース株式会社(プライバシー・ポリシー)
NTTデータビジネスブレインズ
「ファイル連携からAPI連携へ」DXを加速する選択肢 ~MuleSoftのAPI連携基盤で...
3.6 株式会社オージス総研
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
切実にデータ連携が求められる時代
コロナ禍により、テレワークの浸透や顧客接点の多様化が一気に進み、劇的にデジタルシフトが進行しています。 急激に変化する世の中で、企業は既存のアセットと新しいテクノロジーを組み合わせてイノベーションを起こし、顧客中心のDXを進める必要があります。 そのためには、お客さまへ価値を提供するためのデータ連携が今まで以上に重要です。 しかしながら、円滑なデータ連携が実現できている企業はそれほど多くはありません。
ファイル連携がDXの推進を減速している
データ連携の方法としては、旧来からのファイル連携が未だ主流です。 ただ、ファイル連携ではリアルタイムにデータが同期できない、個別連携のため効率が悪く運用コストがかさむ等の問題があり、プロジェクトの進行や開発スピードを遅らせ、DX推進の妨げとなっています。 もはや従来のポイントツーポイントのファイル連携だけでは変化のスピードに対応しきれず、別のアプローチが求められています。
API連携により、スピーディで効率的なデータ連携を実現する
本セミナーでは、API連携基盤で円滑なシステム間連携を実現し、DXをスピーディに進めていくためのシステム構築の方法を解説します。 オージス総研がパートナーである、MuleSoftのソリューション「Anypoint Platform」についても紹介しますので、ぜひご参加ください。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 「ファイル連携からAPI連携へ」DXを加速する選択肢
11:45~12:00 質疑応答
主催
株式会社オージス総研(プライバシー・ポリシー)
業務自動化の鍵となる「PDF」を徹底活用する方法 ~PDFからテキストを取り出す、テキスト...
3.5 アンテナハウス株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
業務自動化のために、PDFの活用が必要
2019年にMM総研が行ったリサーチによれば51.5%のビジネスマンが「最も非効率な業務」として「データの入力・登録」と回答しています。
データ入力業務における自動化は、ビジネスが加速する現代においてますます需要が高まっています。
一方で、自動化したくても元データがPDFであるため、自動化が進まないといった課題もあります。
特に、同じ形式のデータが各PDFに大量にある場合など、PDFからデータを自動集計できれば、業務効率の大幅な改善が見込めます。
PDFからテキストを取り出す、フォーム情報を活用するには?
取り出したいデータがPDFファイル内にしかない場合があります。その場合、OCRでテキストを取得するという選択肢もありますが、読み取り精度は100%ではなく、結局手作業が発生する場合も少なくありません。
一方で専用のツールを使えば、PDFから直接テキストデータを取得することも可能です。
今回のセミナーでは、PDFからテキストデータやフォーム情報を、具体的にどのようにデータを取得するのか、取得したデータをどう扱えばいいのか、など、実際のデモを中心にご紹介します。
PDFにテキストを挿入するなど、その他多数の事例を徹底解説
今回のセミナーでは、上記に加え実際にお客様からご質問いただいた下記の内容について、デモをお見せいたします。
デモ予定一覧
・PDFからフォーム情報を取得する方法 ・PDFの注釈情報をコピーする方法 ・1万ファイル以上にも及ぶPDFファイルに「Confidential」と入力する方法 ・1つのPDFを「しおり」ごとに分割する方法 ・フォントを埋め込む方法
など、PDFファイルを自由自在に使いこなし、自動化へのヒントを持ち帰ってください。
プログラム
14:45~15:00 受付
15:00~15:05 オープニング(マジセミ)
15:05~15:35 業務自動化の鍵となる「PDF」を徹底活用する方法
15:35~15:45 質疑応答
主催
アンテナハウス株式会社(プライバシー・ポリシー)
OCRの種類比較。クラウド、オンプレ、アウトソースどれを選ぶべきか? 卸売業における紙業務...
3.4 東日本電信電話株式会社
本セミナーはWebセミナーです。
ツールはTeamsを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
卸売業の「紙業務」の課題
DXが進む中、卸売業の生産性を下げている要因の1つに「紙業務」の多さにあります。 注文書、発注書、納品書、注文明細、支払明細、検収書(証明書)など処理すべき伝票は多種多様。 その結果「デジタル化」を進めたいものの、どうしても「手作業」に依存してしまいます。 もし手作業の時間を削減でき、空いた工数で他の業務に着手できたら、生産性アップにつながるはずです。
過去にOCR導入がうまくいかなかった理由
OCR導入の3つのポイントとして、 ・読取精度の高さ ・どれだけ手作業が減らせるか ・イニシャルコスト、ランニングコスト といった点が挙げられます。 過去のOCR導入ネックとして「読取精度が低い」「読取だけ自動化しても手作業はあまり減らない」「初期費用が想像よりも高い」等があったのではないでしょうか。 これらを解消するOCRはあるのでしょうか?
3つの種類にわかれる「OCR」。どれが最適なのか?選び方は?
OCRには、 ・クラウド ・オンプレミス ・アウトソース(ベンダーにおまかせ) の3つの種類があります。
今回のセミナーではそれぞれの特徴と機能、費用相場、メリット・デメリットを比較解説いたします。 主に卸売業向けにクラウド・オンプレミス・アウトソースの3種類のOCRを比較し、自社に合った形態の選び方や活用事例もご紹介。 紙伝票業務のマンパワー削減を検討されている企業様のヒントになれば幸いです。
こんな事業者さまにおすすめ
多品種の伝票処理に、社員の工数をできるだけかけたくない 紙業務のDXを進めたいが、自社に最適なOCRの選び方がわからない 過去にOCRを導入・検討したが、効果があるかわからなかった
プログラム
13:45-14:00 受付
14:00-14:05 オープニング(マジセミ)
14:05-14:35 OCRの種類比較。クラウド、オンプレ、アウトソースどれを選ぶべきか?(レゾナゲート)
・卸売業における紙業務の課題 ・OCRの種類比較 ・OCRでの課題解決事例
14:35-14:50 紙業務DXとOCRの果たす役割(NTT東日本)
・OCRを活用したDXの進め方 ・OCR製品デモ
14:50-15:00 質疑応答
主催
東日本電信電話株式会社(プライバシー・ポリシー)
共催
株式会社レゾナゲート(プライバシー・ポリシー)
RPAからはじめる「デジタルファースト」 現場が使いやすいRPAツール紹介
3.5 株式会社デリバリーコンサルティング
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
73%がRPAを知らない...いまさら誰も教えてくれないRPA
RPAとは一体何なのか?何ができるのか?いまさら誰かに聞けないとお困りではありませんか。
株式会社SheepDogの調査によると、会社員のRPA
の認知率は27%、使用経験があると回答したのは約13%という結果が出ています。
つまり全体の73%は「RPAをよく知らない」 ということです。
RPA導入でぶつかる壁
「DX推進」が叫ばれる中、「とにかくまず業務自動化をはじめよう」と、情報収集に駆け回る担当者も多いのではないでしょうか。 業務自動化の手段としてRPAを導入する際にぶつかる壁は共通しています。
費用対効果が見合うかわからない
導入後の副次的効果が見えづらい
RPAで業務効率化できそうな対象業務件が少ない
社内に専門部隊やサポート体制がない
RPAが大事だと理解しているが、社内を説得させられる材料がない
特に「費用対効果」を論理的にも感覚的にも経営層に理解させるのは難しいく、お困りのご担当者様も多いと思います。
また、導入後にRPA専任担当やサポート体制がいなかったり、自動化できる業務が明確になっていないと意味がありません。 RPAの設計や操作が複雑で途中で諦めてしまう担当者も多くいます。
RPAとは何か、RPAの費用対効果の算出方法を、初心者
向けに解説します!
本セミナーでは「RPAはどんな業務を効率化してくれるのか」「どうすれば社内をスムーズに説得させ、導入を失敗せずに進めることができるのか」をテーマに、初心者向けにRPAをイチから解説します。基礎知識は不要です。 RPA導入コンサルティング実績が豊富なデリバリーコンサルティングが提供する簡単RPA「ipasロボ」の特徴、さまざまな業務課題ごとの導入事例、製品デモを行います。 はじめてRPAという言葉を聞く方も、一度導入してうまくいかなかった方も、奮ってご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:40 業務自動化ツール「RPA」入門〜費用対効果の算出方法も解説〜
■RPA基礎知識 RPA自動化業務とは RPAの対象業務とは 社内への説得方法
■RPA導入事例 1)経理部門の仕訳、請求、経費関連業務 2)購買担当者のFAXからの受注入力 3)配送事務の依頼書入力 4)サポート部門の問い合わせ業務 5)本部での各店舗からの勤怠、売上情報の収集
■ツール紹介 簡単に現場使えるツール「ipaSロボ」の紹介
■費用対効果 POCを実施する時の作業(業務)時間を測定
13:40~14:00 質疑応答
主催
株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)



.jpg?1766370984)