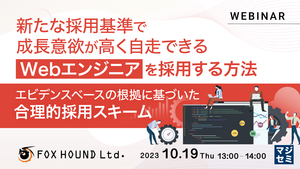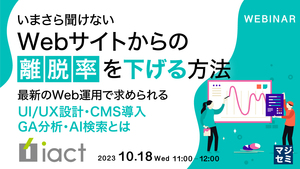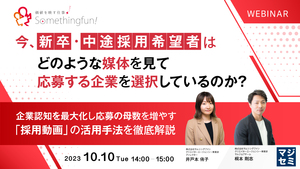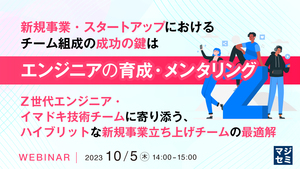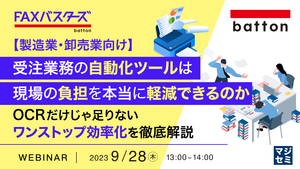ビジネス
Business
ビジネスの課題を解決するウェビナー
デジタルトランスフォーメーション(DX)、カスタマーサクセス、UX/CX、新規事業立ち上げ、ビジネス戦略、ITベンダーの事業戦略など、経営や事業運営に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。
ビジネス
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
ビジネス
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
新たな採用基準で成長意欲が高く自走できるWebエンジニアを採用する方法 ~エビデンスベースの...
3.8 FOX HOUND株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
IT人材採用の課題
人材不足の解消方法として新卒、中途問わず未経験者のポテンシャル採用を率先している企業は増えてきています。 ですが、未経験者は採用リスクや教育コストが大きく、また適切な指導方法も見いだせず育成した人材の流出につながることも多くあります。
自走できるWebエンジニアを採用できる合理的根拠に基づいたスキーム
このようなIT人材採用の課題を解決するために必要なのは、採用前に成長意欲が高く・育成投資価値がある人材かを見極めることです。 また、学歴よりも信頼の高いEBPMによるエビデンスベースでそのような人材であることを見極める方法を知ることがこれからの採用においての重要なポイントです。 本ウェビナーでは、その見極めを実現できる「SLスタジオコネクテッド」をご紹介します。 採用対象となるのは、持続型学習プラットフォームである「SLスタジオ」で必要なスキルと学習し続けるサイクルを身に着けた人材となるため、 採用後に発生する課題を未然に回避し、育成投資価値がある人材を採用できる、合理的根拠に基づいた採用スキームです。 Webエンジニアの採用、特に人材の見極め方法に課題感をお持ちの方や優秀なIT人材の判別に悩まれている方におすすめの内容です。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 新たな採用基準で成長意欲が高く自走できるWebエンジニアを採用する方法 ~エビデンスベースの根拠に基づいた合理的採用スキーム~
13:45~14:00 質疑応答
主催
FOX HOUND株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
いまさら聞けない、Webサイトからの離脱率を下げる方法 ~最新のWeb運用で求められる、UI...
3.8 株式会社アイアクト
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
時代の移り変わりにあなたの会社のWebサイトは適応できていますか?
ここ数年で、社会全体に影響するような大きな変化が多数起こり、令和の時代の価値観はめまぐるしく移り変わっています。 そのような状況の中で、働き方やビジネスの進め方にも大きな変化があったという方も多いのではないでしょうか? その変化は、ユーザーにも発生していると考えられ、会社のWebサイトの在り方も時代に適応させる必要性があります。 本ウェビナーでは、そうした時代の変化にあわせたWebサイトの在り方をご紹介いたします。
Webサイトの運用負荷・コストなどを軽減できるAI検索
また、AIの技術の進歩も著しく、一般の方でも気軽に扱える生成AI(ChatGPTなど)が登場するなど、AIが身近になってきています。 そうした中で、WebサイトにもAI検索を取り入れる企業が増えてきています。 ウェビナー後半では、これまでのサイト内検索で発生していた課題や、AI検索がそうした課題をどう解決できるのかをデモを交えて説明いたします。
エンゲージメント向上・離脱率低下を実現するポイントとは
Webサイト来訪者のエンゲージメントを向上させたい、最近サイト離脱率が上昇傾向にあるといったお悩みがある方に、 対応すべきポイントや具体的な対策をウェビナーの中でお伝えいたします。 これから、Web担当者になる方や課題がありリニューアルを行う必要がある方、最新のWeb運用を知り自社のサイトを適応させていきたいとお考えの方におすすめの内容です。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:25 【第一部】今の時代のWebのトレンドについて ポイントを押さえて分かりやすくご紹介
担当しているWebが本当に時代に沿っているのか、自信がありますか? 時代が変化していく中で、 常にトレンドを追い続けるにはハードルが高い…令和の時代において、 Webサイトを作る際、 気を付けるべき点や 押さえるべきターゲットや構成のポイント、 CMSやGA4分析、 アクセシビリティ、セキュリティなど技術的に避けられない点などを わかりやすくご紹介いたします。
11:25~11:45 【第二部】離脱率が減る、エンゲージメントが上がる デモで確認できるAIサイト内検索の実力
みなさまはお宝満載の自社のサイト内検索のログを見たことがありますか? 「あれ、この検索で正しいページが表示されてないぞ」という課題だけではなく、 「えっ、うちにこんなニーズがあるんだ」という発見があるのがサイト内検索のログです。 これまでの検索機能ではなかなか思い通りの検索ができず、サイト内検索はサブの機能でしたが、 AI検索の登場により、 劇的に環境が変わってきています。 例えば、サイトの離脱率が減った。 あるいは、GA4のエンゲージメントがあがったというような成果も。 本セッションでは、これまでの検索機能の課題とAI検索の実力をデモでご説明しながら、 Webサイトの運用負荷・コストなども軽減することができる理由をご説明いたします。
11:45~12:00 質疑応答
主催
株式会社アイアクト(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
なぜCRMを導入しても、“形骸化”してしまうのか? 〜Microsoft Dynamics ...
3.8 株式会社 シーイーシー
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
多くの企業が取り組むCRMへの移行
近年、多くの企業で顧客管理や営業活動の効率化を目指してCRMの導入が進められています。 CRMは、顧客情報の一元管理や営業活動の可視化を通じて、営業担当者の業務をサポートする強力なツールである一方、運用に課題を抱える企業も少なくありません。
「CRMを導入しても定着しなかった」事例は数知れず
CRMの導入は、実際には「形骸化」してしまう現状があります。 高い投資をして導入したにも関わらず、従業員がうまく使いこなせず、運用が定着しないという問題が生じています。
機能が多く使いこなせない、営業情報の入力が手間、どう使っていいか分からない
CRMの導入において、従業員が直面する課題は多岐にわたります。 特に、機能が多すぎてどれを使っていいのか分からない、営業情報の入力が煩雑で時間がかかる、使い方が複雑で学習コストが高いなどの問題が挙げられます。 これらの課題が積み重なることで、CRMの運用が定着しづらくなってしまいます。
Microsoft Dynamics 365向けのテンプレート、ツール連携により「定着するCRM」を実現
本セミナーでは、「Microsoft Dynamics 365 CRM」「Microsoft Sales Copilot」の機能を活用した効果的なCRM運用の方法を紹介します。 多くの機能を有するMicrosoft Dynamics 365を営業向けにシンプルにカスタマイズした「Salesテンプレート」を利用することで、営業担当者が必要とする機能だけをシンプルに使えるようになります。 さらに、Microsoft Sales Copilotとの連携により入力の省力化を実現し、営業情報を効率的に収集することも可能になります。 CRMを導入したものの、運用が定着していないとお悩みの営業担当者やマネージャーの方はぜひご参加ください。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 なぜCRMを導入しても、“形骸化”してしまうのか?〜Microsoft Dynamics 365×AIを活用して「定着するCRM」を実現〜
11:45~12:00 質疑応答
主催
株式会社 シーイーシー(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
中堅中小製造業向け 高コスト・高性能・多機能な経営管理システム(ERP)を使いこなせています...
3.4 ITbookテクノロジー株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
高性能・多機能な経営管理システム(ERP) 導入・運用コストが中堅中小企業には大きな負担に
企業の「会計業務」「人事業務」「生産業務」「物流業務」「販売業務」などの情報を統合する、経営管理システム(ERP)。 多くの企業で導入が進む一方、中堅中小企業にとっては、導入・運用コストが高く、大きな負担となっている現状があります。
少量多品種生産など日本のものづくりの特徴と、中堅中小製造業におけるシステム導入の壁とは
中堅中小製造業においては、海外にはない特徴があります。海外ベンダーが提供するシステムでは想定されていない少量多品種生産や、細やかな製造ラインの切替など、日本の製造業の特徴を解説します。 また、IT人材の採用が困難な状況は今後も続くと考えられており、そのような中、自社に適したERPの選定は困難を極めます。 SIer、ITベンダーによって、必要以上に高性能・多機能なERPを勧められるというケースも見受けられます。
中堅中小製造業の経営に寄り添う、身の丈にあった経営管理システムを導入事例とともに解説
中堅中小製造業に求められるのは、状況に対応し、フットワーク軽く、変化に対応すること。そのためには、自社の経営に合わせた伴走型で企業に寄り添ってカスタマイズが可能なERPが必要になります。 伴走型のERPの導入とはどのようなものなのか、豊富な導入事例を交えながら、身の丈にあった経営管理システムをご紹介します。
プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 中堅中小製造業向け 高コスト・高性能・多機能な経営管理システム(ERP)を使いこなせていますか~少量多品種生産など、日本のものづくりに適した、小回りの利く、身の丈にあったERPとは?~
10:45~11:00 質疑応答
主催
ITbookテクノロジー株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
持続的なイノベーションのカギとなる「アイデアを管理する」という考え方 ~アイデア獲得から投票...
3.9 株式会社システムコンシェルジュ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
予測できないビジネス環境では、組織気おける持続的なイノベーション活動が競争力と成長のカギとなる
近年の人工知能や5Gなどの技術革新、グローバル市場の拡大、消費者のニーズの多様化により、企業のビジネス環境は急速に変化しています。
企業がこの変化を乗り越え、成功を続けるには、変化に対応した新しい価値をつくり続ける「持続的なイノベーション」を生み出す組織づくりが必要になります。
アイデアが出てこない、出しても採用されない組織が多い
しかしながら、多くの組織で「アイデアが出てこない」「出しても採用されない」という問題が生じています。
従業員が意見やアイディアを出しにくい文化や環境には、以下のように様々な要因があります。
・経営層や上司からの前向きではないフィードバック ・過度にリスクを見積もられる ・組織内の情報共有が十分に整ってない ・アイディアの評価基準が不明確である
企業の文化や価値観が、変化や革新を受け入れにくい傾向にある場合は、持続可能なイノベーションを生み出すことが難しくなります。
イノベーションを生み出す文化を醸成する「イノベーション管理プラットフォーム」とは
本セミナーでは、メンバーからのアイディアを収集、評価、実装するためのイノベーション管理プラットフォームである「IdeaScale」を通じて、企業や組織がどのようにして革新的な変革を促進し、競争力を向上させることができるのかを詳しく解説します。
「IdeaScale」は、投票・コメント機能を使用して、社員のアイデアを「見える化」して、ブラッシュアップすることができます。また組織横断でコミュニティを作り、チームでアイディア推進することも出来ます。問題点のレビューや、ROI計測を行ってアイデアを「数値化」することも可能です。
従業員から新しいアイデアが出てこないことに課題を持っている方、自組織にイノベーションを生み出す文化を醸成したいと考えている方、出たアイデアを評価して育てる仕組みづくりを検討したい方、などに特におすすめです。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 持続的なイノベーションのカギとなる「アイデアを管理する」という考え方
13:45~14:00 質疑応答
主催
株式会社システムコンシェルジュ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社セレンディピティ・イン・ リサーチ・アンド・イノベーションズ (プライバシー・ポリシー) 株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
今、新卒・中途採用希望者は、どのような媒体を見て応募する企業を選択しているのか? ~企業認知...
3.5 株式会社サムシングファン
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
様変わりする採用希望者の行動
これまでは、新卒や中途採用希望者は企業サイトや採用サイトなどテキストや画像といった情報で判断を行い、応募する企業を選択していました。 そうした中で、生まれた大きな変化として、「動画」で企業の情報を取得するという行動が急速に増加しています。
入社後のミスマッチを引き起こす要因
また、入社後にミスマッチが発生し、社員や従業員が定着しない要因の一つに、「その企業の社風や特徴・雰囲気が入社前に分かりづらかった」という点が挙げられます。 これまでは、テキストや画像のみで判断する必要があるため、このようなケースが発生しやすい状況でした。 そのような中で、より正確かつ分かりやすく社風や特徴を伝えることができる手法として採用動画の活用に注目が集まり、運用する企業が増えたことで、就職活動時に採用動画を確認することが当たり前となりつつあります。
採用動画の活用で企業認知の最大化と応募数の増加を実現する
ここまで、採用活動の中で動画を取り入れる点を言及しましたが、やみくもに動画を作成すれば良いわけではありません。 本ウェビナーでは、抱えている課題や実現したい運用にあわせて伴走型の動画活用支援を行うサービスをご紹介いたします。 課題や目的に合わせ動画制作・配信運用を行うことで、企業認知の最大化や応募の母数の増加を実現します。 動画制作において20年以上の実績があるため、ノウハウや技術の水準が高い点やご要望に応じて採用代行やエージェントとしての支援が行える体制を整えている点でご好評をいただいています。 採用に課題を抱えている人事・採用部門のご担当者様や新たな採用手法を模索されている方に特におすすめの内容です。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 今、新卒・中途採用希望者は、どのような媒体を見て応募する企業を選択しているのか? ~企業認知を最大化し応募の母数を増やす「採用動画」の活用手法を徹底解説~
14:45~15:00 質疑応答
主催
株式会社サムシングファン(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
新規事業・スタートアップにおける、チーム組成の成功の鍵は、エンジニアの育成・メンタリング Z...
3.8 PLAYLAND株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
新規事業立ち上げ時や、スタートアップ企業において、技術チームを立ち上げたいがノウハウがない
新規事業やスタートアップにとって、”スピード”と”柔軟性”は、開発において重要なポイントとなります。そのために、自社でエンジニアを抱え、開発を内製化するのが主流となっています。 しかし、いざ自社で技術チームを立ち上げるとなると、ノウハウがなく行き詰ってしまうケースも見受けられます。
エンジニアの確保はできたが、若手技術者の育成や、メンタリングができる人材が見つからない
技術チームの立ち上げに際して、なんとか若手エンジニアの確保はできても、開発経験が豊富なエンジニアの採用は厳しいのが実状です。 一方、技術チーム成功の鍵と言われているのが、若手エンジニアのメンタリングです。スタートアップなどでは、経営者が必ずしも エンジニアとは限らず、適切なメンタリングができないケースも。
イマドキ技術チームのマネジメント方法とは? マネジメント人材を確保する方法をあわせて解説
Z世代エンジニア・イマドキ技術チームの特徴とは?伴走型で、若手エンジニアに寄り添いながら、技術チームを立ち上げていく方法とは?豊富な実例を交えながらわかりやすく解説します。 IT人材が枯渇している今、技術視点で事業の立ち上げができる人材をどのように確保するのかもあわせて解説いたします。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 新規事業・スタートアップにおける、チーム組成の成功の鍵は、エンジニアの育成・メンタリング~Z世代エンジニア・イマドキ技術チームに寄り添う、ハイブリットな新規事業立ち上げチームの最適解~
14:45~15:00 質疑応答
主催
PLAYLAND株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
Engineerforce Inc. (エンジニアフォース)(プライバシー・ポリシー) 株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
知らなかったでは済まされない、Salesforce管理者なら知っておきたいセキュリティリスク...
4.0 ウィズセキュア株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。
ビジネスの根幹を担う「Salesforce」で起こっている“情報漏えい”と“サイバー攻撃の被害”とは
クラウドベースのCRMソリューションとして広く認知されている「Salesforce」。小規模ビジネスから大手企業まで様々なビジネスニーズに対応できる拡張性や柔軟性、カスタマイズ性などを備えていることから、国内外の多くの企業・組織で利用されています。 ただ、2020年以降、「Salesforce管理者の設定不備」が原因となり、金融機関やEC事業者、自治体、システム会社などで、Salesforce上のデータが外部から参照可能な状態になったことによる情報漏えい事故が相次いで発生しました。また、サイバー攻撃者にも狙われており、Salesforceを対象としたマルウェアやランサムウェアの攻撃が確認されています。
見落としがちな「コンテンツのセキュリティ責任はユーザー側にある」という事実
通常、クラウドサービスにおけるユーザーとクラウド事業者の担当領域・責任範囲は「責任共有モデル」として責任分界点が定義されています。クラウドサービス利用時の重要なポイントになるにもかかわらず、ユーザーが見落としがちな観点です。 Salesforceの設定不備が原因で情報漏えいのリスクが生じた際、その設定変更の権限と責任はユーザー企業に帰属します。 また、Salesforceのサービスではデータプライバシー保護の観点から、クラウド上に共有したデータをファイルデータとして取り扱うため、基本的にウイルススキャンや検疫などを実施しません。そのため、Salesforceにアップロードするコンテンツの安全性は、ユーザー側で対策やチェックを実施する必要があります。たとえば、顧客やパートナー企業と共有するコミュニケ―ションツール「Experience Cloud」におけるコンテンツ共有では、ユーザー側でもセキュリティ対策に万全を期すことが求められます。
Salesforce上で気を付けるべきリスクと安全に利用するためのベストプラクティスを解説
本セミナーでは「Salesforce利用時に注意すべきセキュリティリスク」「ユーザーが安全に利用するため実施すべきセキュリティ対策」について、専門家が分かりやすく解説します。
特に、以下のような方におすすめです。 ・Salesforceを利用する組織の情報セキュリティ責任者、担当者 ・Salesforceのシステム開発/インテグレーション事業者 ・Salesforceを利用する組織のSalesforce管理者やエンジニア ・Salesforceのセキュリティリスクと対策を把握したい方
また、Salesforceにおけるセキュリティ対策のベストプラクティスとして、Salesforce社と共同開発したセキュリティソリューションを具体的な改善事例を交えてご紹介します。Salesforce製品をご利用の企業の方は、ぜひご参加ください。
講演プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 知らなかったでは済まされない、Salesforce管理者なら知っておきたいセキュリティリスクと対策~ 改善事例を交えて情報漏えい/サイバー攻撃対策などのベストプラクティスを解説 ~
「Salesforceからの情報漏えいリスクと対策」 ・Salesforce セキュリティ診断事例のご紹介 「Salesforceへのマルウェア/ランサムウェア攻撃のリスクと対策」 ・Salesforce マルウェア/ランサムウェア 攻撃の防御について ・「WithSecure Cloud Protection for Salesforce」国内導入事例
10:45~11:00 質疑応答、クロージング
主催
ウィズセキュア株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
【製造業・卸売業向け】受注業務の自動化ツールは、現場の負担を本当に軽減できるのか 〜OCRだ...
3.6 株式会社batton
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
部分的な自動化では、受注業務の効率化は実現しない
製造業や卸売業の受注処理は、事務作業とベテラン社員のチェックによって成り立っています。自動化には、異なるフォーマットの読み取りやマスタ照合など、各業務に適した技術の組み合わせが必要です。AI-OCRによる文字読み取りだけでは、現場の業務負担は軽減されません。
ベテラン社員の知見が必要な業務をA Iが実行
これまで、ベテラン社員による受注作業のチェックは自動化が難しい領域でした。しかし、近年ではこうした業務もAIによって自動化できるようになりました。社員は生産性の高い業務に集中できるようになり、労働時間の削減にもつながっています。
ITツールのネックとなる、導入時の業務負担の解決
さらにITツールを検討する際にネックとなるのが各種の設定などの導入時の業務負担です。またツールに合わせてこれまでの業務フローを変える必要があり、導入をあきらめたケースも多く見られました。しかし、AI搭載の最新DXツールであれば、初期導入コストを大幅削減、かつ業務フローそのままでDXが実現できています。
ワンストップ効率化可能な受注業務DXツールをデモ付きで紹介
本セミナーでは、複数の先端技術を組み合わせた受注業務DXツール「FAXバスターズ」によるワンストップ効率化について、デモを交えて紹介します。 受注作業のデジタル化・自動化を検討している方、これまで検討したが自社に合うものが見つからなかったという方、ぜひご参加ください。
こんな方にオススメ
・製造業や卸売業の方
・受注業務がある企業の方
・最新のDXやITツールに興味がある方
・生産性向上や業務効率化に興味がある方
・AI-OCRを導入検討もしくは導入済の方
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 受注業務の自動化ツールは、現場の負担を本当に軽減できるのか
〜OCRだけじゃ足りない、ワンストップ効率化を徹底解説〜
13:45~14:00 質疑応答
主催
株式会社batton(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)