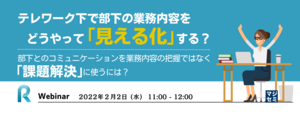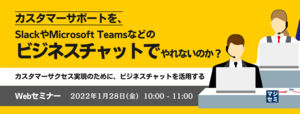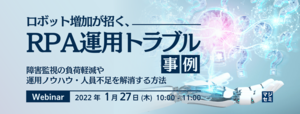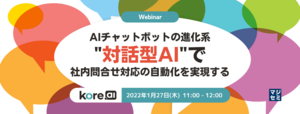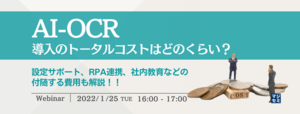業務自動化
Business automation
業務自動化の課題を解決するウェビナー
RPA、AI-OCR、iPaaSなどを活用した業務自動化に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。業界別の活用事例や業務効率化の方法、データ処理の改善についても学べる内容が揃っています。また、業務自動化の市場規模や最新の動向についても紹介しています。
業務自動化・効率化
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
業務自動化・効率化
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
知識ゼロでも導入できるRPA 非システム部門や現場担当者向け RPAの始め方
3.8 株式会社デリバリーコンサルティング
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
73%がRPAを知らない...いまさら誰も教えてくれないRPA
RPAとは一体何なのか?何ができるのか?いまさら誰かに聞けないとお困りではありませんか。
株式会社SheepDogの調査によると、会社員のRPA
の認知率は27%、使用経験があると回答したのは約13%という結果が出ています。
つまり全体の73%は「RPAをよく知らない」 ということです。
RPA導入でぶつかる壁
「DX推進」が叫ばれる中、「とにかくまず業務自動化をはじめよう」と、情報収集に駆け回る担当者も多いのではないでしょうか。 業務自動化の手段としてRPAを導入する際にぶつかる壁は共通しています。
社内に専門部隊やサポート体制がない
RPAで業務効率化できそうな対象業務件が少ない
費用対効果が見合うかわからない
導入後の副次的効果が見えづらい
RPAが大事だと理解しているが、社内を説得させられる材料がない
こうした理由から、RPAの検討を途中で諦めてしまう担当者も多くいます。
知識ゼロの方でもわかるように、60分で基礎を解説!
本セミナーでは「RPAの基本がよくわかっていない」初心者向けに、RPAの特徴、自動化業務の種類などを導入事例を交えながら解説します。 また、デリバリーコンサルティングが提供する簡単RPA「ipasロボ」の製品デモも実施するので、「RPAは実際にこういう風に動くのか」とイメージを持って頂けるかと思います。 はじめてRPA導入を検討される方も、一度導入してうまくいかなかった方も、奮ってご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:40 知識ゼロでも導入できるRPA 〜非システム部門や現場担当者向け RPAの始め方〜
■RPA基礎知識 RPA自動化業務とは RPAの対象業務とは 社内への説得方法
■RPA導入事例 1)経理部門の仕訳、請求、経費関連業務 2)購買担当者のFAXからの受注入力 3)配送事務の依頼書入力 4)サポート部門の問い合わせ業務 5)本部での各店舗からの勤怠、売上情報の収集
■ツール紹介 簡単に現場使えるツール「ipaSロボ」の紹介
■費用対効果 POCを実施する時の作業(業務)時間を測定
13:40~13:55 質疑応答
主催
株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)
業務自動化の鍵となる「PDF」を徹底活用する方法 ~PDFからテキストを取り出す、テキスト...
3.5 アンテナハウス株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
業務自動化のために、PDFの活用が必要
2019年にMM総研が行ったリサーチによれば51.5%のビジネスマンが「最も非効率な業務」として「データの入力・登録」と回答しています。
データ入力業務における自動化は、ビジネスが加速する現代においてますます需要が高まっています。
一方で、自動化したくても元データがPDFであるため、自動化が進まないといった課題もあります。
特に、同じ形式のデータが各PDFに大量にある場合など、PDFからデータを自動集計できれば、業務効率の大幅な改善が見込めます。
PDFからテキストを取り出す、フォーム情報を活用するには?
取り出したいデータがPDFファイル内にしかない場合があります。その場合、OCRでテキストを取得するという選択肢もありますが、読み取り精度は100%ではなく、結局手作業が発生する場合も少なくありません。
一方で専用のツールを使えば、PDFから直接テキストデータを取得することも可能です。
今回のセミナーでは、PDFからテキストデータやフォーム情報を、具体的にどのようにデータを取得するのか、取得したデータをどう扱えばいいのか、など、実際のデモを中心にご紹介します。
PDFにテキストを挿入するなど、その他多数の事例を徹底解説
今回のセミナーでは、上記に加え実際にお客様からご質問いただいた下記の内容について、デモをお見せいたします。
デモ予定一覧
・PDFからフォーム情報を取得する方法 ・PDFの注釈情報をコピーする方法 ・1万ファイル以上にも及ぶPDFファイルに「Confidential」と入力する方法 ・1つのPDFを「しおり」ごとに分割する方法 ・フォントを埋め込む方法
など、PDFファイルを自由自在に使いこなし、自動化へのヒントを持ち帰ってください。
プログラム
14:45~15:00 受付
15:00~15:05 オープニング(マジセミ)
15:05~15:35 業務自動化の鍵となる「PDF」を徹底活用する方法
15:35~15:45 質疑応答
主催
アンテナハウス株式会社(プライバシー・ポリシー)
テレワーク下で部下の業務内容をどうやって「見える化」する? 〜 部下とのコミュニケーション...
3.5 株式会社リモシア
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
進捗やコミュニケーションに課題を抱える上司の割合は
コロナ禍によりテレワーク環境へと移行が進むなか、上司部下間でのコミュニケーションが減少し、それまでは生じていなかったさまざまな問題が発生しています。
パーソル研究所が2020年の3月に上司層700人に行ったアンケートによると「業務の進捗状況が分かりにくく不安」(46.3%)、「非対面のやりとりは相手の気持ちが察しにくい」(44.9%)、「部下が仕事をサボっているのではないかと思うことがある」(40.0%)と、実に75.3%の方が部下の業務内容の把握やコミュニケーションに課題や不安を抱えています。
さらに、部下層の31.4%も「上司から公平・公正に評価してもらえるか不安」と訴えています。
参考:https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/research/activity/data/telework-anxiety.html
部下と円滑なコミュニケーションをはかるために
一方で、部下とのコミュニケーションに使える手段は複数あります。例えば日報や、TO DOリストの共有などです。
しかし日報は情報の粒度としては粗く、部下が行った行動に対して具体的にどう考えたのか?そしてどうアプローチしたのかは見えにくいです。
また、TO DOリストの共有は情報が断片的で、これも部下が何を考えて具体的に何を行ったのかは見えにくいです。
他にもオンライン会議室で常時コミュニケーションをはかったり、チャットツールを導入したり、円滑な部下とのコミュニケーションにさまざまな手段が講じられています。
事実確認ではなく課題解決のためのディスカッションをするには?
部下とのミーティングで多いのは、何をしたか?という「事実確認」に時間がかかることです。
上司は部下の抱えている案件に対し、進捗確認だけでなく、リスクも管理する必要があるため、事実確認に時間がかかるのは当然です。
一方で「リモシア」は、部下が「どんな業務をしたか?」が一目瞭然です。そのためミーティングでは事実確認ではなく、すぐに課題解決に対するディスカッションができます。
今回のセミナーでは、すでに多くの企業様に導入いただいているコミュニケーションツール「リモシア」が実際にどのように使われているか、どのようにコミュニケーションが円滑になるか、実例を基にお伝えします。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 テレワーク下で部下の業務内容をどうやって「見える化」する?
11:45~11:55 質疑応答
主催
株式会社リモシア(プライバシー・ポリシー)
RPAからはじめる「デジタルファースト」 現場が使いやすいRPAツール紹介
3.5 株式会社デリバリーコンサルティング
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
73%がRPAを知らない...いまさら誰も教えてくれないRPA
RPAとは一体何なのか?何ができるのか?いまさら誰かに聞けないとお困りではありませんか。
株式会社SheepDogの調査によると、会社員のRPA
の認知率は27%、使用経験があると回答したのは約13%という結果が出ています。
つまり全体の73%は「RPAをよく知らない」 ということです。
RPA導入でぶつかる壁
「DX推進」が叫ばれる中、「とにかくまず業務自動化をはじめよう」と、情報収集に駆け回る担当者も多いのではないでしょうか。 業務自動化の手段としてRPAを導入する際にぶつかる壁は共通しています。
費用対効果が見合うかわからない
導入後の副次的効果が見えづらい
RPAで業務効率化できそうな対象業務件が少ない
社内に専門部隊やサポート体制がない
RPAが大事だと理解しているが、社内を説得させられる材料がない
特に「費用対効果」を論理的にも感覚的にも経営層に理解させるのは難しいく、お困りのご担当者様も多いと思います。
また、導入後にRPA専任担当やサポート体制がいなかったり、自動化できる業務が明確になっていないと意味がありません。 RPAの設計や操作が複雑で途中で諦めてしまう担当者も多くいます。
RPAとは何か、RPAの費用対効果の算出方法を、初心者
向けに解説します!
本セミナーでは「RPAはどんな業務を効率化してくれるのか」「どうすれば社内をスムーズに説得させ、導入を失敗せずに進めることができるのか」をテーマに、初心者向けにRPAをイチから解説します。基礎知識は不要です。 RPA導入コンサルティング実績が豊富なデリバリーコンサルティングが提供する簡単RPA「ipasロボ」の特徴、さまざまな業務課題ごとの導入事例、製品デモを行います。 はじめてRPAという言葉を聞く方も、一度導入してうまくいかなかった方も、奮ってご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:40 業務自動化ツール「RPA」入門〜費用対効果の算出方法も解説〜
■RPA基礎知識 RPA自動化業務とは RPAの対象業務とは 社内への説得方法
■RPA導入事例 1)経理部門の仕訳、請求、経費関連業務 2)購買担当者のFAXからの受注入力 3)配送事務の依頼書入力 4)サポート部門の問い合わせ業務 5)本部での各店舗からの勤怠、売上情報の収集
■ツール紹介 簡単に現場使えるツール「ipaSロボ」の紹介
■費用対効果 POCを実施する時の作業(業務)時間を測定
13:40~14:00 質疑応答
主催
株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)
カスタマーサポートを、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットでや...
3.6 株式会社ヴィセント
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
重要度が増す「カスタマーサクセス」
サブスクリプション型のビジネスを始めとして、現在全てのビジネスでお客様との継続的な関係構築が必須となっています。
その時に重要になるのが「カスタマーサクセス」という考え方です。 多くの企業が「カスタマーサクセス」の実現を目指し、取り組んでいると思います。
メールによる、お客様とのコミュニケーションの問題点
その際の顧客接点、お客様とのコミュニケーション手段として、「メール」を使っているケースが多いと思いますが、メールでのコミュニケーションは以下のような問題があります。
・お客様も、カスタマーサポート担当者も、日々大量のメールの中で重要なメールを見落としてしまう ・カスタマーサポート担当者が、どのメールがどのお客様のものか、誰が担当なのか、混乱してしまう ・そもそもお客様が、最近メールを見ないようになっている
チャットボットの問題点
カスタマーサポートの手段として、チャットボットを使用するケースも増えてきています。 確かにお客様からカスタマーサポート担当者に連絡する際には便利なのですが、カスタマーサポート担当者からお客様への連絡には使えません。
SlackやMicrosoft Teamsで、多数の顧客とチャットはできないのか?
最近では、多くの企業でSlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットを導入しています。 これらのビジネスチャットを、カスタマーサポートで利用できないのでしょうか?
その際問題になるのが、当然のことながらお客様企業毎に使っているツールが異なる、ということです。
マジセミ株式会社での活用事例を紹介
マジセミ株式会社も同様の課題がありました。 本セミナーでは、マジセミ株式会社がどのような課題を抱えていたのか、それをどのように解決しようとしているのか、その事例を交えて、お客様側のツールがSlack、Microsoft Teams、Chatworkなどバラバラでも、カスタマーサポート担当者は1つのビジネスチャットで対応できるツール「CHAT-HUB」について紹介します。
プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:25 カスタマーサポートを、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットでやれないのか?
マジセミ株式会社 寺田雄一 (プレゼン内容) ・マジセミの業務内容 ・マジセミにおける、カスタマーサポートの課題 ・カスタマーサポートを、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットでやれないのか? ・CHAT-HUBの活用
10:25~10:45 CHAT-HUBの紹介
株式会社ヴィセント 森大地
10:45~11:00 質疑応答
主催
株式会社ヴィセント(プライバシー・ポリシー)
ロボット増加が招く、RPA運用トラブル事例 障害監視の負荷軽減や運用ノウハウ・人員不足を解...
3.8 NECソリューションイノベータ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
人材不足や業務効率化を目指して導入が進むRPA
慢性的に続く人材不足や業務効率化を目指し、デジタル技術を活用した改善への取り組みが進められています。 その中でも、ソフトウェアロボットを利用し、さまざまな業務の自動処理を実行する「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」が導入されてきました。
ロボットの数が増えることで起きる運用時の課題
RPAの導入効果を実感した企業の多くが、社内で複数のロボットを実行するようになりました。 しかし、ロボットの数が増えて対象業務が広がるとともに、RPAの運用時に思わぬトラブルに見舞われることも多くなっています。
正常に安定的に稼働できるような環境を整備したい
ロボットの中には、1つの処理を実行する際に複数システムの連携や操作が必要になるため、処理エラーが発生する場面も出ています。ただ、常時ログを監視しない限り、そうしたエラーの通知を見落としたり、対応漏れが起きることもあります。 また、ロボットの安定化のために実行端末を毎日再起動するなど、どうしても手作業のメンテナンスが必要になることも増えています。 そのため、ロボットが正常かつ安定的に稼働できる環境の整備が求められています。
RPA運用における業務負荷の軽減、ノウハウや人員不足を解消する方法
本セミナーでは、ロボット増加で発生するさまざまな運用トラブルの事例を解決するヒントを解説します。 また、これまでに1,200以上ものロボット運用の実績を踏まえ、障害監視などの作業負荷を軽減できる機能を備えた具体的なソリューションを紹介します。 さらに、RPA運用のノウハウや人員不足を解消したいと考える方に向け、人材育成・研修トレーニングもご案内。現状のRPA運用の改善を検討されている方は、ぜひご参加ください。
講演プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 ロボット増加が招く、RPA運用トラブル事例~障害監視の負荷軽減や運用ノウハウ・人員不足を解消する方法~
10:45~11:00 質疑応答
主催
NECソリューションイノベータ株式会社(プライバシー・ポリシー)
AIチャットボットの進化系"対話型AI"で社内問合せ対応の自動化を実現する
3.6 Kore.ai
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
リモートワークにより社内問合せ対応の問題が発生
リモートワークの普及が進んだことにより、自宅やシェアオフィスで勤務をする形式が一般的になりました。 しかし物理的に離れた場所で仕事をすることに伴い、社内問合わせの対応において問題が生じています。
社員側、受付側の双方から様々な不満が噴出
問合せをする社員側としては、聞きたいことを気軽に質問できない、誰に聞けば良いかわからない、マニュアルが見つからない等の要因により、致し方なく社内ヘルプデスクへ問合わせをせざるを得ないケースが増えました。 そして受付側としては、増加した問合せを受けきれない、マニュアルや社内掲示板等に書かれてあるにも関わらず問合せがくる、といった意見が出ています。 このように、問合せをする側、受け付ける側の双方から様々な不満が噴出しているのが実情です。
従来のチャットボットは設計が困難でインテント(意図)認識率にも課題
社内の問合せ対応を効率化する代表的な手段として、AIチャットボットが挙げられます。 しかし多くのAIチャットボットは、設計や運用が煩雑で外部委託が必要になってしまう、インテント(意図)認識の精度が低いために対応を自動化できず、導入しても効果を得られないといった課題を抱えています。
社内コミュニケーション自動化の事例を紹介
そこで本セミナーでは、設計が容易でインテント認識率も高い社内コミュニケーション自動化ツールの作り方や導入事例について紹介します。 また、ノーコード設計が可能で、問合せを受けるだけではなくその後の処理の実行も自動化できるKore.ai Japan社のソリューション「Kore.ai Platform 9.0」についても紹介しますので、ぜひご参加ください。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 AIチャットボットの進化系対話型AI
で社内問合せ対応の自動化を実現する
11:45~12:00 質疑応答
主催
Kore.ai(プライバシー・ポリシー)
AI-OCR導入のトータルコストはどのくらい? 設定サポート、RPA連携、社内教育などの付...
3.6 東日本電信電話株式会社
Teamsオンラインセミナー
本セミナーは、オンラインセミナーです。 ツールはTeamsを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
こんなお悩みはありませんか?
長期化するコロナウイルスの影響、DX化への意識の高まりにより、テレワークの実施など働き方が大きく変化しました。 一方で、製造業や物流、バックオフィスなど紙帳票を多く扱う業界・部門では、 紙帳票への対応業務によって出社せざるを得ず、テレワーク及び業務効率化の課題となっているとの声が多く見受けられます。
この課題を解決する方法の1つがAI-OCR!!
ですが… 「インターネットの情報では、実際いくらかかるか分かりづらい」 「低コストで導入しても効果が出ないのではないか」 「使い方のレクチャーや技術サポートにかかるコストが見えない」
と、費用面の不安から導入検討を躊躇している方もおられるのではないでしょうか。
本セミナーでは、AI-OCR導入の代表的なケースに即した費用感をご説明いたします。
4つの利用ケースで比較~費用感とその効果~
AI-OCRは業務自動化の一つの手段でしかありません。 設定サポートやほかの製品と組み合わせることにより、AI-OCRの効果を最大化、そして業務全体の効率化につながります。 今回は主に4つのケースでの導入ステップと費用感を解説します。
1)AI-OCR導入のみで解決 2)AI-OCR導入と設定サポートで解決 3)AI-OCR導入と設定サポート、RPA連携で解決 4)AI-OCRとスキャナ導入、VBA連携で解決
ミライト情報システムの豊富な製品導入と技術サポート実績をもとに、効果的な投資をいただくためのヒントをご説明いたします。
こんな方におすすめ
・AI-OCR導入費用、ランニング費用の詳細が知りたい方 ・導入にかかわるサポート・教育など含めたイニシャルコストを知りたい方 ・伝票入力業務の効率化を検討している方、または今後考えたい方 ・AI-OCRの検討をしたことがあるが、導入に踏み切れなかった方
プログラム
15:45~16:00 受付
16:00〜16:05 オープニング(マジセミ)
16:05~16:15 DXを取り巻く環境と、帳票読み取り・データ入力業務の現状(NTT東日本)
16:15~16:50 AI-OCR導入のトータルコストはどのくらい?(ミライト情報システム)
・OCR導入の費用相場解説 ・こんなケースだといくらかかる?パターン別の費用感と効果 ・MIS-OCR+WinActor&技術支援サービス紹介 ・製品デモ
16:50〜17:00 質疑応答
【セミナー参加限定特典!】
・MIS-OCRお申込みで5万円分の技術者サービス(訪問サポート1日5万円相当)※先着10社まで
主催
東日本電信電話株式会社(プライバシー・ポリシー)
共催
株式会社ミライト情報システム(プライバシー・ポリシー)
今さら聞けない「RPA」基礎知識解説 初心者でもわかる、イメージが湧く、すぐに始められる
3.9 株式会社デリバリーコンサルティング
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
73%がRPAを知らない...いまさら誰も教えてくれないRPA
RPAとは一体何なのか?何ができるのか?いまさら誰かに聞けないとお困りではありませんか。
株式会社SheepDogの調査によると、会社員のRPA
の認知率は27%、使用経験があると回答したのは約13%という結果が出ています。
つまり全体の73%は「RPAをよく知らない」 ということです。
はじめて導入する際にネックになる「対象業務」
RPAを導入すると、どんな業務を効率化できるのでしょうか。 対象業務のイメージが湧きづらく、「何ができて、何ができないのかわからない」 というのが本音ではないでしょうか。 RPA対象業務が定まっていないと、目的も費用対効果も見えず、プロジェクトが頓挫してしまいます。
導入した後に、本当に使いこなせるのか?
導入した後にも立ちはだかる壁があります。 RPA専任担当やサポート体制がいなかったり、自動化できる業務が明確になっていないと意味がありません。 RPAの設計や操作が複雑で途中で諦めてしまう担当者も多くいます。
RPAはどんな業務を効率化するのか、初心者
向けに解説します!
本セミナーでは「RPAはどんな業務を効率化してくれるのか?」をテーマに、初心者向けにRPAをイチから解説します。基礎知識は不要です。 RPA導入コンサルティング実績が豊富なデリバリーコンサルティングが提供する簡単RPA「ipasロボ」の特徴、さまざまな業務課題ごとの導入事例、製品デモを行います。 はじめてRPAという言葉を聞く方も、一度導入してうまくいかなかった方も、奮ってご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:40 【超初心者向け】RPAはどんな業務を効率化してくれるのか?
■RPA基礎知識 RPA自動化業務とは RPAの対象業務とは 社内への説得方法
■RPA導入事例 1)経理部門の仕訳、請求、経費関連業務 2)購買担当者のFAXからの受注入力 3)配送事務の依頼書入力 4)サポート部門の問い合わせ業務 5)本部での各店舗からの勤怠、売上情報の収集
■ツール紹介 簡単に現場使えるツール「ipaSロボ」の紹介
■費用対効果 POCを実施する時の作業(業務)時間を測定
13:40~14:00 質疑応答
主催
株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)