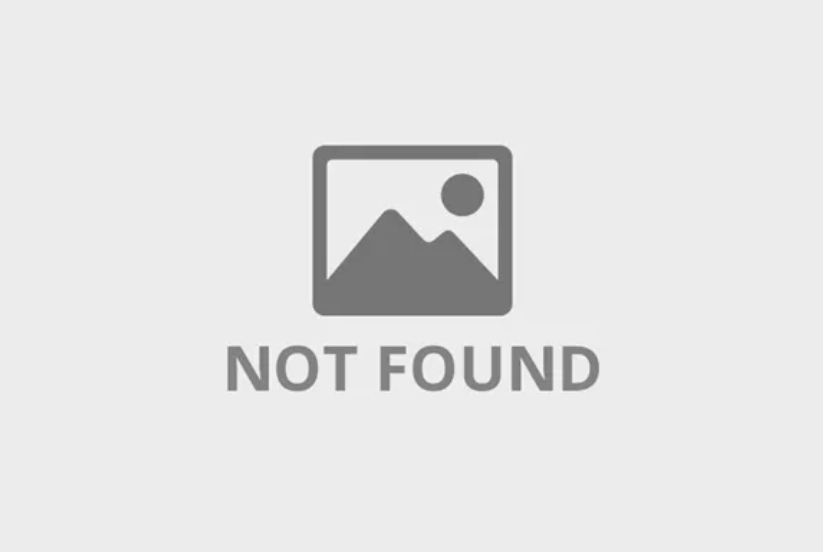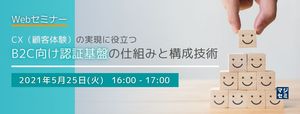ビジネス
Business
ビジネスの課題を解決するウェビナー
デジタルトランスフォーメーション(DX)、カスタマーサクセス、UX/CX、新規事業立ち上げ、ビジネス戦略、ITベンダーの事業戦略など、経営や事業運営に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。
ビジネス
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
ビジネス
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
日本交通は、なぜビジネスチャットの全社導入でオープンソースのMattermostを選択したの...
3.7
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
必須のツールとなったビジネスチャット
テレワークが、「ニューノーマル」となった現在、ビジネスチャットは社員や取引先とのコミュニケーション手段として、必須のものとなっています。
日本交通も全社でのビジネスチャットの導入を検討
タクシー事業の最大手である日本交通でも、ビジネスチャットの有効性に気づき、個人レベルや部門レベルでいくつかのビジネスチャットやメッセージアプリを使うようになりました。 しかし、ツールが統一されていないことで社内のコミュニケーションが煩雑になったり、情報が分散してしまうといった問題や、セキュリティ面での課題から、全社でビジネスチャットを統一することを検討しました。
コスト面から、Mattermostを全社導入
しかし、全社導入となると利用者が1,000ユーザーを超えることからコスト面の課題が浮上。 検討の結果、オープンソースのビジネスチャットである「Mattermost」を全社導入しました。
Mattermostのメリット/デメリットを、日本交通株式会社 システム担当部長 岡村様が回答
本セミナーでは、実際にMattermostの導入をご担当された、日本交通株式会社 システム担当部長 岡村様にご登壇頂き、以下のようなMattermostに対する疑問や、メリット/デメリットを率直にお答えいただきます。
・なぜ、Mattermostを導入したのか?
・オープンソースに対する不安は無かったのか?
・運用は大変ではないのか?
・他のビジネスチャットと比較して、操作性、使い勝手はどうだったのか?
・一部の部門やグループ会社では継続して他のビジネスチャットを使われているところもあるが、どう連携しているのか?
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:40 日本交通は、なぜビジネスチャットの全社導入でオープンソースのMattermostを選択したのか?
日本交通株式会社 システム担当部長 岡村様
13:40~13:55 Mattermostのご紹介
株式会社ヴィセント
13:55~14:00 質疑応答・クロージング(マジセミ)
主催
株式会社ヴィセント
データサイエンティストとは? ワークスアイディ株式会社 シニアデータサイエンティスト 福原...
4.2 マジセミ株式会社
ここでしか聞けない、【IT最新動向ぶっちゃけトーク】
本セミナーは、IT業界の「旬」なトレンドをテーマに、毎回ゲストをお迎えし、対談形式で「ぶっちゃけトーク」をお届けするものです。また、毎回参加者からの大量のご質問を頂き、ライブで回答していく、参加型のセミナーです。
今回は、「データサイエンティスト」について、徹底議論!
今回は、DXで重要性が高まっている「データサイエンティスト」について、ワークスアイディ株式会社 シニアデータサイエンティスト 福原好隆氏とマジセミ代表寺田雄一が徹底討論します!
データサイエンティストとは?何を期待されているのか?
データサイエンティストとは、ビッグデータなどから必要な情報を収集、抽出するプロフェッショナルです。ビジネスに活用するための施策立案やアドバイスも行います。米国では、データサイエンティストが将来性のある職業1位になるなど、注目の職業です。
内製化か?アウトソースか?
DXに取り組む企業が増える中、データサイエンティストの重要性は高まっています。 このような状況の中、企業はデータサイエンティストを競争力の源泉として、採用、育成し、内製化するべきでしょうか?
もしくは、データサイエンティストの数は少なく、採用も難しいため、現実解としてはアウトソースするべきなのでしょうか?
また、内製化、アウトソース、それぞれのメリット、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
データサイエンティストの育成とキャリアパス
企業がデータサイエンティストを内製化しようとしたとき、その育成は大きな課題です。 初めてデータサイエンティストを置く企業にとって、どのような方法が適切なのでしょうか。
また、データサイエンティストになるためのキャリアパスや、データサイエンティストになった後の将来的なキャリアパスはどのようなものなのでしょうか?
ツールの利用とデータサイエンティスト
ITの世界では、技術の普及やコモディティ化に伴い、特定領域のエンジニアへの需要が減っていくということが繰り返されてきています。
例えば、AWSなどのクラウドサービスの普及により、インフラエンジニアやネットワークエンジニアへの需要は減りました。
最近「データサイエンティスト不要」を謳うツールやサービスも登場してきています。 今後データサイエンティストは必要なくなっていくのでしょうか?
企業やITに携わる部署の方々は、今何をするべきなのか?
このような背景の中、企業やITに携わる部署の方々は、「データサイエンティスト」についてどのように取り組むべきなのでしょうか?
今回は、企業のDX化やデータサイエンスプロジェクトの推進、データサイエンティスト養成講座講師などをされている、ワークスアイディ株式会社 シニアデータサイエンティスト 福原好隆氏をゲストとしてお招きし、ぶっちゃけトークを展開します。
また、参加者も交えて議論していきます。シナリオがない対談ですので、どこに行くかわかりません。また、時間の関係で全てのテーマについて十分な議論ができないと思います。ご了承下さい。
福原好隆 氏
ワークスアイディ株式会社 DX事業統括本部IT事業本部 データサイエンス グループ シニアデータサイエンティスト チーフマネージャー
大学卒業・海外留学後、通販会社にてデータ分析チーム責任者等を経てデータサイエンティストへ。DX化・データサイエンスプロジェクトのプロジェクト推進、データサイエンティスト養成講座講師などを担当。九州・東京エリアにおけるデータサイエンス事業の立ち上げ・拡大を推進中。
寺田雄一
ウェビナー(Webセミナー)の集客・運営サービス「マジセミ」を起業、代表取締役社長。IT関連のウェビナーを年間600回運営。 他にも、クラウドID管理サービス「Keyspider」を起業し代表を、空飛ぶクルマの運航プラットフォームを提供するエアモビリティ株式会社のCTOなどを務める。 野村総合研究所(NRI)出身。NRIでは社内ベンチャーとして、オープンソース・サポートサービス「OpenStandia」を起業。
主催
マジセミ株式会社
HCIの弱点と克服ポイントがよくわかるセミナー
本セミナーは、JBCC株式会社 が主催するWebセミナー「HCIの弱点と克服ポイントがよくわかるセミナー」のご紹介です。
HCIの弱点と克服ポイントがよくわかるセミナー
一見、万能と思われるHCIですが、いったい何が良いの?クラウドと何が違うの?デメリットはないの?高そうだけれど安いものはないの?色々な製品があるけれどどれが良いの?と、疑問に思われるかたは多いです。
そこで、実際に早期から検証や導入に関わってきた、次世代プラットフォームのエバンジェリストが、各製品の良いところから苦手なところまで、本音で語ります。各製品の比較検討をして、自社に最適な製品を選定したいお客様は必見です!
ぜひご参加ください。
プログラム
15:00~15:45 【Session 1】HCIに死角はないのか!?ここだけの話、HCIウィークポイントをおしえます
次世代の仮想化基盤と言われているHCI。インターネット上ではHCIの良いことばかりが取り上げられて目立っています。3Tier(サーバー-スイッチ-ストレージ)はもはや古臭いのか? HCIを早期から検証~導入を数多く経験してきたJBCCが、HCIが不得意とするケースなど赤裸々に語ります。 HCI検討中のお客様の仮想化環境では、本セッションで語られる懸念がクリアできるのか、ぜひ見極めてみてください!
講師:JBCC株式会社
15:45~16:00 【Session 2】コストも運用も!継続的なインフラ最適化がもたらすメリットとは
お客様の環境は最適なものになっていますか?リソースが余っていたり、足りなくてパフォーマンスが悪かったりと課題があるお客様も多いです。JBCCではリソース状況の可視化と定期健診で、導入前から導入後まで、お客様の運用とコスト最適化をサポートします。
講師:JBCC株式会社
*参加費:無料 *講師及び講演内容は都合により変更になる場合がありますので予めご了承下さい。 *ご同業の企業様のお申込みは締め切り前であってもお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。
主催
主催:JBCC株式会社
プライバシーポリシー:https://www.jbcc.co.jp/privacy.html
AzureAD/Microsoft365へのユーザー登録、権限設定を自動化する方法 ~ID...
4.0 かもめエンジニアリング株式会社
本セミナーはWebセミナーです ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
本セミナーは、2021年3月18日に実施したWebセミナーの動画配信で行います。 既に聴講された方はご注意ください。(3月18日、4月22日と同内容です)
テレワークの推進で増加する、クラウドサービスの契約
新型コロナウイルスへの対応は今後も続きます。 また、「ニューノーマル」と言われているように、社会やビジネス環境は以前の状態には戻らないとも言われています。 緊急事態宣言時に暫定的に構築したテレワーク環境を、企業は本格的かつ恒久的な環境に見直す必要があります。 そのような背景のもと、企業は様々なクラウドサービスを新規に契約しています。 ・Microsoft365、Google Workspace などのオフィススイート ・Salesforce などのCRM ・BOX などのオンラインストレージ ・Slack、LINEWORKS、ChatWork などのビジネスチャット ・Zoom、Teams などのビデオ会議 ・サイボウズ、Kintone などのグループウェアやWebデータベース ・コンカー、楽々精算、マネーフォワード などの経費精算 ・ジョブカン、KING OF TIME などの勤怠管理
増えるアカウントや権限の管理業務をどう考えればよいのか?
そのような状況の中、各システムのアカウントや権限の管理について、その重要性が高まっていますが、管理する手間も大幅に増えています。 これらはどのように考え、整理すればよいのでしょうか? どのように自動化を考えればよいのでしょうか?
AzureAD/Microsoft365へのユーザー登録、権限設定を自動化する方法
今回は、ID管理クラウドサービス「Keyspider」を使って、AzureAD/Microsoft365へのユーザー登録、権限設定を自動化する方法について紹介します。
プログラム
9:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング
10:05~10:40 AzureAD/Microsoft365へのユーザー登録、権限設定を自動化する方法
10:40~10:45 クロージング
主催
Keyspider株式会社
かもめエンジニアリング株式会社
ニューノーマルで「コミュニケーション」はどう変わるのか? ~バーチャル空間でのWebセミナ...
3.5 マジセミ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールは、oViceを使います。 参加方法(URL)は主催企業より直接メールにてご連絡いたします。
● 注意事項
※パソコンからのご参加をお願いいたします。 ※Chrome・Safari・Edgeの最新バージョンでご利用ください。 ※Internet Explorer ではご利用いただけません。 ※入場時に貴社名及び氏名をご登録いただき、ご入場をお願いいたします。
Webセミナーは、「聞くだけ」になってしまうのか?
これまでのWebセミナーはどうしても「聞くだけ」になってしまいがちです。
本セミナーではバーチャル空間でWebセミナーを開催できる「oVice」を活用し、
・セミナーの開始前、終了後の、参加者同士の「立ち話」
・講師の名刺交換やちょっとした会話
など、新しいWebセミナーのあり方について実験し、参加者の皆様で体感いただけます。
また本セミナーでは、以下のような「コミュニケーション」の課題に対して、ITを使って解決する方法について解説します。
Web会議の日程調整を、もっと簡単にできないのか?
テレワークが普及し、Web会議が「あたりまえ」になりました。 その結果、移動が不要となり、より多くの会議ができるようになりました。
しかし、日程調整は以前と変わらず手間がかかります。 参加メンバーの空き時間を確認し、候補日を複数設定、参加メンバーには「仮」でスケジュールを予約しておいてもらいつつ、お客様に確認、お客様と調整できなかった場合は、また最初からやりなおしです。
もっとスマートに、日程調整ができないのでしょうか?
テレワーク下、営業や社内連絡でオンライン通話した内容を、もっと簡単に社内で共有できないのか?
電話した内容を社内に共有したいケースは多くあります。 例えば電話での商談の内容を営業チームで共有したり、社内メンバーや取引先との会話の内容をプロジェクトメンバーに共有したりするケースです。 最近では簡単に音声データを残せるようにはなりましたが、それを確認する方は「音声データを、最初から最後まで全て聞く」必要があり、とても時間がかかります。
もっとスマートに、音声データを共有する方法はないのでしょうか。
カスタマーサポート、ヘルプデスクを自動化できないのか?
コロナ禍で、情報システムの重要性は高まっています。 EC(ネット通販)は、生活に不可欠なインフラになりましたし、小売業界にとっても最も重要なチャネルになりました。
企業でもテレワークが普及する中、より一層業務のIT化を進めています。
その結果、カスタマーサポートやヘルプデスクへの問い合わせは増えています。 ヘルプデスクの場合、テレワークでメールなどによるサポートが多くなるため、より手間がかかるようになりました。
一方最近では、AIチャットボットも進化してきています。 チャットボットで、カスタマーサポート、ヘルプデスクを効率化、自動化できないのでしょうか?
プログラム
15:45~16:00 受付
16:00~16:05 オープニング
16:05~16:20 Web会議の日程調整を、もっと簡単にできないのか?
株式会社RECEPTIONIST
16:20~16:35 営業や社内連絡でオンライン通話した内容を、もっと簡単に社内で共有できないのか?
pickupon株式会社
16:35~16:50 カスタマーサポート、ヘルプデスクを自動化できないのか?
株式会社サンソウシステムズ
16:50~17:00 質疑応答、クロージング
主催
マジセミ株式会社
協賛
株式会社RECEPTIONIST pickupon株式会社 株式会社サンソウシステムズ
【情シス責任者/管理職向け】なぜセキュリティ研修は形骸化してしまうのか? 〜社員のセキュリ...
3.6 JBサービス株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
標的型メール攻撃は、技術だけでは防ぎきれない
経済産業省が2020年に実施した中小企業向け調査では、対象の1064社中「インシデントの可能性あり」と判断し、対処を行った件数は128件でした。2020年は三菱電機やNECがサイバー攻撃を受け、リスクは高まり続けています。 テレワークや在宅勤務が長期化する中で、ファイアウォールやウイルス対策ソフトだけでは脅威を全て防御するのは困難と言えます。 技術的なツールに加えて、従業員のセキュリティ意識の向上が必要不可欠です。
なぜセキュリティ教育は形骸化してしまうのか?
多くの企業では既にセキュリティ教育を導入しているかと思います。
現在の社内セキュリティ研修には、このような課題はありませんか? ・標的型メール訓練を年1回実施しても、知識として定着しづらい ・実施した結果、企業・組織としての被害リスクが低減しているかわからない ・実際に攻撃を受けた際にどのように行動すべきかを学ぶのが難しい ・教育資料が例年変わらず、メールの開封・リンクのクリックという単調な訓練では従業員も飽きている
セキュリティ意識を定着させるためにできることとは?
本セミナーでは、セキュリティ責任者・管理職の方向けに、近年のサイバーリスクをとりまく環境とセキュリティ教育の課題を解説しながら、JBサービスが提供するSecuLiteracy(セキュリテラシー)のご紹介をいたします。当サービスは、様々なサイバー攻撃のテクニック・ツール・ノウハウ等に精通した認定ホワイトハッカーがご支援する標的型メール訓練・教育サービスです。セキュリティ教育を強化したい企業の経営層、情シス部門の方々は奮ってご参加ください。
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ )
14:05~14:40 セキュリティ研修形骸化の課題と対策〜技術だけでは防げないサイバーリスクに、社員教育でどう対処すべきか〜
・標的型メール、サイバー攻撃を取り巻く環境 ・セキュリティ製品の限界と課題 ・社内セキュリティ教育の課題 ・SecuLiteracy(セキュリテラシー)のサービス紹介
14:40~15:00 質疑応答
主催
JBサービス株式会社
■プライバシーポリシー https://www.jbsvc.co.jp/privacy1.html ※お申込みいただいた方は、プライバシーポリシーに同意頂いたとみなします。
CX(顧客体験)の実現に役立つ B2C向け認証基盤の仕組みと構成技術 〜認証基盤の重要性と...
3.8 株式会社オージス総研
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
好評につき、2/17開催セミナーと同内容をお届けします。
2/17開催のセミナーに参加できなかった方向けです。内容は重複しますので予めご了承ください。
コロナとDXの影響で、ECに進出する企業が増加
コロナ禍を機に新たにEC展開を始めた事業者や、今後EC化を検討している企業は多いのではないでしょうか? 実際に、コロナ禍で巣ごもり需要や在宅勤務が進み、ECを利用するユーザが増加傾向を続けています。三井住友カードの調査結果によると、約3人に1人が2019年比で「利用頻度が増えた」と回答。それに伴いEC事業を開始する企業も増え、ネットショップ開設支援サービス「BASE」の新規ショップ開設数は、前年同四半期比で約2倍に増加しました。 参照: https://www.smbc-card.com/company/news/news0001562.pdf https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08546/506262e6/d747/4750/9a65/de8c7839925a/140120201113424527.pdf
なぜ認証基盤が重要なのか?
ECをはじめとするB2Cサービスは、認証基盤を強化することでユーザの利便性・セキュリティが格段に上がることは言うまでもありません。WEBサイトの会員登録、決済において多要素認証、ソーシャルログイン、シングルサインオンを通じて、安心でノンストレスな顧客体験(CX)をユーザに届けることができます。
もし、認証基盤を利用しないと、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
・各WebサービスやAPIとシステム間連携を個別に行うコストや労力が発生 ・アカウント管理DBの構築や、アカウント統合を失敗したときのリスクが大きい ・認証領域固有の標準技術や知見を持つエンジニアが必要 ・サービスを継続するための最新認証技術仕様への追従、サービス利用の増加に伴った基盤拡張が求められる などが挙げられます。 認証基盤を頼らず、専門知識なしに継続的にサービス提供をし続けることは非現実的です。 このように認証領域のエンジニアへの負担を軽減し、Webサービスのコアとなる開発に注力する役割を担うのが認証基盤です。
ThemiStruct(統合認証パッケージ)を活用して、認証管理を効率化する
本セミナーでは、ECサイトなどのB2Cサービスにおける認証基盤の重要性と有効性をご説明しながら、技術者向けに認証管理の効率化ソリューションとしてThemiStruct(テミストラクト)の仕組みと具体的な構成技術を解説します。実装デモを中心とした、技術者向けの内容になっております。
▼こんな方におすすめ ・情シス部門の担当者、責任者 ・ECサイトの企画・運営担当者 ・ 認証の強化やID統合をご検討の方 ・セキュリティや品質管理のご担当者
プログラム
15:45~16:00 受付
16:00~16:05 オープニング(マジセミ)
16:05~16:45 CX(顧客体験)の実現に役立つ B2C向け認証基盤の仕組みと構成技術
〜認証基盤の重要性と、本人認証・ID統合の実装とデモ〜
講演内容 ・管理(CIAM)における課題と認証基盤の役割 ・魅力あるWebサービス構築に向けた認証管理製品活用の有効性 ・弊社ソリューションThemiStructによる実装デモ (多要素認証など認証強化の組み込みの動作デモ)
16:45~17:00 質疑応答
主催
株式会社オージス総研
AI-OCRとRPAを使った自動受注システムのつくり方 ~プログラムレスだから現場でもでき...
3.7 株式会社デリバリーコンサルティング
迫られる業務自動化への対応
近年、多くの企業では、働き方改革の推進を背景に労働時間の短縮や残業時間の規制により、人手に大きく依存した業務の見直しを迫られる機会が増えてきています。 さらにコロナ禍に端を発したリモートワークなど新しい働き方へのシフトがこうしたトレンドを強く後押しする事態になっています。 人手に頼らなければできない、オフィスに居なければ実施できない業務運営のままでは今後業務が立ちいかなくなるリスクもあります。業務自動化へと大きく舵を切る判断をされる経営者が多いのも自然の流れと言えるでしょう。
受注業務の自動化を阻む壁
受注業務では取引先から届く注文書データのシステム入力や請求書の発行作業などを行います。 定型的に見えがちな業務ながら、受注と請求データの突合せには人手が必要であったり、伝票フォーマットや手続きが取引先毎に異なることも珍しくないなど、受注業務特有の性質や事情のため自動化が難しいとされていました。例外処理や処理パターンが多くなるとシステム化のハードル(特にコスト)が上がってしまうのがその理由です。
検討しては見たものの、下記のような理由で断念したケースも少なくないでしょう。 ☑伝票のフォーマットが増えるとOCRなどを使用しても機械的に読み取ることが難しい ☑取引先毎に手続きが異なり、変更や例外が発生しやすい業務のためシステム化のコストが高い
デジタル技術の進歩により環境は好転
現在では、OCRが進歩し高度な学習機能を備えたAI-OCRが登場したことにより、多種多様なフォーマットの伝票を簡単な設定をするだけで高精度に読み取れるようになってきています。 またRPAの登場によってシステム開発の在り方も大きく変わりました。大規模システム開発は引き続きシステム担当主導による導入・開発が主ですが、ちょっとした身の回りの処理の自動化といった小規模~ミクロなシステム化はRPAで実現することができるようになりました。 システム部門の助けが無くとも、またシステム部門自体が無くとも、業務現場主体で自動化したいことを自分たちのペース・裁量で実現できるようになってきています。 こうしたデジタル技術の進歩によって、以前は人手によって対処するしかないと考えられていた受注業務の自動化への道が拓けてきたのです。
受注業務の自動化に適したツールの必須要件
AI-CORもRPAも世の中には多くのツールで溢れかえっています。 受注業務に適したツールというものがあるのでしょうか?あるのであれば、その要件は一体何なのでしょうか?
受注業務の自動化に適したツールというのは、業務を詳細に知っている現場担当者自らが主導してシステムを作成できるツールです。そして何かしらの変化やパターンの追加があってもすぐにシステムを修正できるツールです。
今回のセミナーでご紹介するAIスキャンロボ(AI-OCR)、RPA(ipaSロボ)は、受注業務の自動化に欠かせない現場でできるシステム開発を見据えた特徴を有しています。
AIスキャンロボ(AI-OCR)の特徴
☑AIが伝票を自動判別し、高精度なデータ読み取り・抽出を実現 ☑読み取り伝票テンプレート登録の操作が簡単になり、一般事務担当者でも設定が可能。 ☑複雑な段組の伝票や手書き文字の読み取りが可能
ipaSロボ(RPA)の特徴
☑現場担当者でもプログラミングなしでロボット(スクリプト)が作成可能 ☑端末1台から、月額利用で始められるRPA。小さく始めて大きく育てることが可能 ☑あらゆる業務アプリケーションの自動化に対応
自動受注システムを作ってみよう
本セミナーでは、ネットスマイルの提供するAI-OCR「AIスキャンロボ」とデリバリーコンサルティングのセルフRPAツール「ipaSロボ」の製品紹介を行うとともに、伝票処理の自動効率化の事例、実践的な導入オペレーションなど、どうやって受注業務をシステム化できるか?をご紹介します。 奮ってご参加ください!
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:10 現場で作れる自動受注システムとは?(デリバリーコンサルティング)
13:10~13:40 AI-OCRで実現する多品種受注伝票のデータ化(ネットスマイル)
AI-OCRの最新トレンドに触れたうえで、ビジネス文書の読み取りに強いAI-OCRで注文書を電子化してそのまま販売管理システムに連携できる仕組みを、デモを交えながらご紹介します。
13:40~14:10 RPAを活用してノンプログラミングで受注業務を自動化へ(デリバリーコンサルティング)
現場部門で運用可能なデスクトップ型RPA「ipaSロボ」を活用した受注業務の自動化について、ロボット作成や スケジュール機能を利用した運用のポイントなどを実際のデモを交えながらご紹介します。
14:10~14:30 質疑応答
主催
株式会社デリバリーコンサルティング プライバシーポリシーURL:https://www.deliv.co.jp/privacy
共催
ネットスマイル株式会社