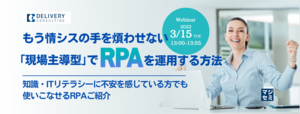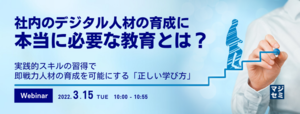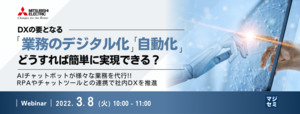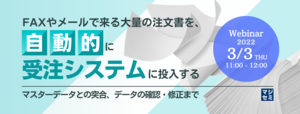業務自動化
Business automation
業務自動化の課題を解決するウェビナー
RPA、AI-OCR、iPaaSなどを活用した業務自動化に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。業界別の活用事例や業務効率化の方法、データ処理の改善についても学べる内容が揃っています。また、業務自動化の市場規模や最新の動向についても紹介しています。
業務自動化・効率化
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
業務自動化・効率化
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
「Webデータベース」「ノーコード」の課題 ~脱Excel、リアルタイムでの情報共有をした...
3.1 リコージャパン
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
テレワークで求められる脱Excel、リアルタイムでの情報共有
新型コロナウイルスの影響で暫定的にテレワークを開始した企業様も少なくないのではないでしょうか?
内閣府の資料によると、2020年の12月に23区内でテレワークを実施した企業は42.8%にもおよびます。
一方で社内情報の共有にExcelを用いていた場合、「ファイルサーバーへのアクセスに時間がかかる」「どのエクセルが最新のものか分かりにくい」などの課題も表面化しています。
そのため、リアルタイムで更新可能なWebデータベースを用いる企業様が増えています。
「Webデータベース」の課題
昨今は、リアルタイムでの情報共有には「Webデータベース」が用いられることが多いです。
一般的にWebデータベースは、「ノーコード」と呼ばれる専門知識不要での構築が可能です。
しかし、理想のデータベースを構築しようとする際には、プログラミングの知識を要求される事も少なくありません。
それによって、Webデータベースの構築が頓挫してしまったというお声もいただいています。
エンジニアがいなくても、簡単に社内情報共有する方法
RICOH Desk Navi は、徹底的に「ノーコード」にこだわったデータベースを採用しています。
社内のファイルサーバーやNASを活用して「ノーコード」でデータベースを活用することが可能です。
そのため、エンジニアが不在でも直感的かつリアルタイムで編集できるデータベースを社内ネットワーク上に構築できます。
今回のセミナーでは、実際に構築したデータベースをお見せするとともに、さまざまな活用方法をご紹介させていただきます。
プログラム
14:45~15:00 受付
15:00~15:05 オープニング(マジセミ)
15:05~15:45 「Webデータベース」「ノーコード」の課題
15:45~15:55 質疑応答
主催
リコージャパン株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
もう情シスの手を煩わせない「現場主導型」でRPAを運用する方法 知識・ITリテラシーに不安...
3.2 株式会社デリバリーコンサルティング
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
RPA導入で情シス担当の負担が増加...
RPA担当がいない状態で導入をすると、情シス担当者は要件定義、開発、オンボーディングに膨大なリソースを取られることになります。 「ゆくゆくは現場主導で...」と思っていても、当面は社員教育に大きなリソースがかかるでしょう。 部門担当としても、できれば情シスに頼らずにRPAを使いこなしたい一方で、複雑なRPAだと使いこなせないジレンマがあります。
約50%の企業が複数のRPAを使い分け
MM総研の調査によると、RPA導入企業の約半数が2つ以上の製品を利用していることが分かりました。 複数利用している理由は、「比較検討・テスト」「互換性・使い分け」「安定稼働・リスク分散」の順に多くなっています。 つまり多くの企業がRPAを比較テストして最善のものを探したり、部門やサービスごとに使い分けをしているのが実態と言えます。 しかし、全社で利用するRPAだけでも運用・保守の負荷が大きいのに、部門利用のRPAのサポートはなおさら難しいでしょう。 どのように運用課題を解決すればよいのでしょうか? (参照: https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=391)
システム担当者の管理負荷を減らし、現場手動でRPAを運用するには?
本セミナーは「RPA導入におけるシステム担当者の負荷を減らし、現場主導で行うRPA運用」をテーマに、RPAの基本情報、情シスの負荷軽減ができる現場主導型RPAの選び方、バックオフィスでの業務自動化の事例紹介、費用対効果の算出方法などを解説します。デリバリーコンサルティングが提供するシンプルなRPAツール「ipaSロボ」の製品デモも行います。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:40 もう情シスの手を煩わせない「現場主導型」でRPAを運用する方法(デリバリーコンサルティング)
<アジェンダ>
■RPA基礎知識 RPA自動化業務とは RPAの対象業務とは 社内への説得方法
■RPA導入事例 1)経理部門の仕訳、請求、経費関連業務 2)購買担当者のFAXからの受注入力 3)他店舗展開における勤務時間の集計 4)サポート部門の問い合わせ業務 5)本部での各店舗からの勤怠、売上情報の収集
■ツール紹介 簡単に現場使えるツール「ipaSロボ」の紹介
■費用対効果 POCを実施する時の作業(業務)時間を測定
14:40~14:55 質疑応答
主催
株式会社デリバリーコンサルティング(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
社内のデジタル人材の育成に本当に必要な教育とは? 実践的スキルの習得で即戦力人材の育成を可...
3.0 NECソリューションイノベータ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。
なぜ、多くの企業・組織がデジタル人材を育てられないのか?
以前から慢性的なIT人材不足が指摘される日本企業。経済産業省が2019年に公表した「2030年には国内のIT人材が79万人も不足する」という試算は、当時大きな衝撃を与えました。また、世界中の社会・経済のデジタル化が加速する中、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を担う人材へのニーズが急激に高まっています。 そうした中、多くの企業・組織ではIT・デジタル人材が「量」「質」に不足しているのが現状です。なぜ、IT・デジタル人材の育成は難しいのでしょうか。
独学や従来型の研修では実践的なスキルが身につかない理由
現在、DX人材の育成を支援するためにさまざまな集合研修やトレーニングが開催されています。また、製品ベンダーが提供する無償のWeb研修や、専門家が執筆した関連書籍を読んで独学で知識を深めることも可能になりました。 ただ、「集合研修を受講して基礎知識を身につけたものの、実践段階で上手く活用できない」「内容がツールの機能説明に終始している」「独学では非効率になりやすく、理解が深められない」という声も多く上がっています。 その理由としては「単に関連知識の習得やツールを使えるだけでは、DX推進に必要な実践的なスキルを身につけることは難しい」点が考えられます。
即戦力となる人材育成に成功した企業の事例を紹介
DXを成功に導くためには、デジタル技術を活用して業務改善を遂行したり、新たなデジタル事業を創出できるスキルに加えて、全社的な企業変革を旗振りするリーダーシップや実践力なども求められます。 本セミナーでは、こうした多くの企業・組織が直面する課題を解決できる「DX推進の即戦力人材」の育成を支援する研修サービスをご提案。 また、「人材育成に悩む企業が抱える課題」をどのように解決できたのか、実際の受講者の声を交えて成功事例をご紹介いたします。RPAの人材育成の課題解決や、総合的な実践力を備えた即戦力人材の育成を可能にする方法にご関心がある方は、ぜひご参加ください。
講演プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 社内のデジタル人材の育成に本当に必要な教育とは?~実践的スキルの習得で即戦力人材の育成を可能にする「正しい学び方」~
10:45~10:55 質疑応答
主催
NECソリューションイノベータ株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
カスタマーサポートを、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットでや...
3.7 株式会社ヴィセント
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
重要度が増す「カスタマーサクセス」
サブスクリプション型のビジネスを始めとして、現在全てのビジネスでお客様との継続的な関係構築が必須となっています。
その時に重要になるのが「カスタマーサクセス」という考え方です。 多くの企業が「カスタマーサクセス」の実現を目指し、取り組んでいると思います。
メールによる、お客様とのコミュニケーションの問題点
その際の顧客接点、お客様とのコミュニケーション手段として、「メール」を使っているケースが多いと思いますが、メールでのコミュニケーションは以下のような問題があります。
・お客様も、カスタマーサポート担当者も、日々大量のメールの中で重要なメールを見落としてしまう ・カスタマーサポート担当者が、どのメールがどのお客様のものか、誰が担当なのか、混乱してしまう ・そもそもお客様が、最近メールを見ないようになっている
チャットボットの問題点
カスタマーサポートの手段として、チャットボットを使用するケースも増えてきています。 確かにお客様からカスタマーサポート担当者に連絡する際には便利なのですが、カスタマーサポート担当者からお客様への連絡には使えません。
SlackやMicrosoft Teamsで、多数の顧客とチャットはできないのか?
最近では、多くの企業でSlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットを導入しています。 これらのビジネスチャットを、カスタマーサポートで利用できないのでしょうか?
その際問題になるのが、当然のことながらお客様企業毎に使っているツールが異なる、ということです。
マジセミ株式会社での活用事例を紹介
マジセミ株式会社も同様の課題がありました。 本セミナーでは、マジセミ株式会社がどのような課題を抱えていたのか、それをどのように解決しようとしているのか、その事例を交えて、お客様側のツールがSlack、Microsoft Teams、Chatworkなどバラバラでも、カスタマーサポート担当者は1つのビジネスチャットで対応できるツール「CHAT-HUB」について紹介します。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:25 【動画配信】カスタマーサポートを、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットでやれないのか?
マジセミ株式会社 寺田雄一 (プレゼン内容) ・マジセミの業務内容 ・マジセミにおける、カスタマーサポートの課題 ・カスタマーサポートを、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットでやれないのか? ・CHAT-HUBの活用
14:25~14:45 CHAT-HUBの紹介
株式会社ヴィセント 森大地
14:45~14:55 質疑応答
主催
株式会社ヴィセント(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
DXの要となる「業務のデジタル化」「自動化」、どうすれば簡単に実現できる? ~AIチャットボ...
3.4 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
本セミナーはWebセミナーです。
ツールはTeamsを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。
本セミナーは、2021年12月に開催したセミナーと同じ講演内容となっています。
多数のご要望により、追加開催させていただきます。
コロナ禍で高まるDX推進への機運だが、日本企業の95%は「いまだ道半ば」
近年、新柄コロナウイルス感染症の影響など、多くの企業のビジネス環境は大きく変化しました。今後の事業成長に欠かせない重要な要素として「DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進する機運が高まってきました。 ただ、経済産業省が2020年12月に発表した「DXレポート2 中間取りまとめ」によると、DX推進指標の自己診断を実施した企業の95%が「DXにまったく取り組んでいないか、取り組み始めた段階」という分析結果が出ています。
DX推進の大きな原動力は「デジタル化」と「自動化」
DXの推進の大前提は「業務のデジタル化」であることは言うまでもありません。さらに「業務の自動化」が加わると、業務プロセスの迅速化によるコスト削減とともに、従業員の働き方や業務改善への効果も期待できます。デジタル化と自動化を組み合わせることで、DX推進のより大きな原動力を生み出すことが可能です。
業務効率化のツール「RPA」「チャットボット」、単体は導入効果に限界も
「RPA」を導入することで、従来人手を介していた一部の作業の自動化が可能になりました。また近年、「チャットボット」によるFAQ自動応答で社内問い合わせ業務の負荷軽減も進んでいます。 しかし、RPAの活用にはデータ作成が必要であり、書類準備が煩雑で手間もかかるなどの課題があります。また、チャットボットの社内利用がFAQに留まるなど、導入効果が限定的なのが現状です。 2つのツールを組み合わせようとした場合、セキュリティ面も課題に挙げられます。
AIチャットボット、LINE、Teamsなどとの連携でさらなる業務効率化を実現
本セミナーでは、業務効率化への新たなアプローチとして、AIチャットボットとRPAを組み合わせたソリューションをご紹介いたします。 また、「どのような業務で利用されているのか」について、LINEやMicrosoft Teamsとの連携など、実際の利用シーンなどを踏まえて分かりやすく解説いたします。DX推進の第一歩を確実に歩みたい方は、ぜひご参加ください。
講演プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 AIチャットボット、LINE、Teams連携で社内DXを推進する方法~DXの要、業務の「デジタル化」「自動化」を実現するRPAの有効活用術~
10:45~10:55 質疑応答
主催
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社(プライバシー・ポリシー) 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社は、2025/4/1から三菱電機デジタルイノベーション株式会社となりました。 三菱電機デジタルイノベーション株式会社:https://www.MitsubishiElectric.co.jp/medigital/
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
DXのゴールはUXなのか?UXの入門解説と、製造業におけるUX 【IT最新動向ぶっちゃけト...
4.2 マジセミ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
ここでしか聞けない、【IT最新動向ぶっちゃけトーク】
本セミナーは、IT業界の「旬」なトレンドをテーマに、毎回ゲストをお迎えし、対談形式で「ぶっちゃけトーク」をお届けするものです。また、毎回参加者からの大量のご質問を頂き、ライブで回答していく、参加型のセミナーです。
DXのゴールは何なのか?
コロナ禍で、ニューノーマルとも言われている現在、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が重要だと叫ばれ続けています。
経済産業省は、2018年9月に公表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」に続き、2020年12月28日に再度「DXレポート2」を、2021年8月31日に「DXレポート2.1」を公表、日本がデジタル競争の敗者になってしまうと警鐘を鳴らしています。
しかし、DXの定義は曖昧で、DXの目的についても以下のような様々な意見があります。
・DXのゴールは、新規事業を創出すること
・DXのゴールは、UX(ユーザー体験)を向上させること
・DXのゴールは、生産性を向上(業務自動化、効率化)させること
・DXのゴールは、時間や場所にとらわれず働けるようにすること
DXのゴールは、UX(ユーザー体験)を向上させること
その中でも、「DXのゴールは、UX(ユーザー体験)を向上させることである」という意見が注目されています。
今回の対談では、まず「DXのゴール」について議論していきます。
UXとは何なのか?マジセミを題材に議論
また、「UX(ユーザー体験)って何?UI(ユーザーインターフェイス)と何が違うの?」という方も多いと思います。
そこで今回は、マジセミのサービスを題材として、
・マジセミのUX(ユーザー体験)とは何なのか?
・UXの向上のため、どのようにDXすればよいのか?
というテーマで議論を進めます。
製造業におけるUX(ユーザー体験)とは?
最後に、今DXが求められている製造業についてのUX(ユーザー体験)とは何なのか、について議論していきます。
今回は、住友金属鉱山株式会社で、自社のDXを推進する 佐藤健司氏をゲストとしてお招きし、DXとUXについてぶっちゃけトークを展開します。
参加者も交えて議論していきます。シナリオがない対談ですので、どこに行くかわかりません。また、時間の関係で全てのテーマについて十分な議論ができないと思います。ご了承下さい。
佐藤健司氏
住友金属鉱山(株)は山から鉱石を掘り、鉱石から金,銀,銅,ニッケル,コバルトなどの地金を製錬し、それらを加工した製品も販売している会社です。ニッケルやコバルトの生産は国内唯一でリチウムイオン電池の正極材も生産しています。 私は工務本部の設備技術開発部に所属しており、世の中に無い設備を作ったり、既存設備に望みの性能を付け足す改造をしたりする部署です。機械,電気,システム設計の能力が有り、何でも作ることができる組織です。情報システム部ではないのがミソです。
その様な組織の中で、 1998年より画像処理検査装置開発を、 2002年よりWeb+DBシステム開発を行い、 2016年からは攻めのIT組織としてデータ解析システムのアジャイル的な開発を進めてきました。 今は、IoTからWebでの見える化を経由して、データ解析モデルを施したレコメンド・システム迄の構築を一気通貫で行っています。 他にもBig-data利用の品質管理システム(2006年)とか、 工場のIoTを強化した生産管理で、リアルタイムな生産計画変更を実現(2014年)させたり、 統計を強化した品質管理でリアルタイムな傾向管理(2016年)を実現させてきました。 最近はデータ解析の仕事が増えています。
寺田雄一
ウェビナー(Webセミナー)の集客・運営サービス「マジセミ」を起業、代表取締役社長。ITやものづくり関連のウェビナーを年間1,000回運営。 野村総合研究所(NRI)出身。NRIでは社内ベンチャーとして、オープンソース・サポートサービス「OpenStandia」を起業。その後、マジセミやクラウドID管理サービス「Keyspider」など次々と新規事業を創出するシリアルアントレプレナー(連続起業家)。
主催
マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
DX時代「タスク見える化」が鍵!急成長ハイパフォーマンスチームの特徴を解説 〜社外共有・チ...
4.1 OrangeOne株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
テレワークと出社が断続的に続いたときに起こるコミュニケーション課題
新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークを導入した中堅中小企業の多くが、出社を再開しつつあることと思います。 そのため、プロジェクトメンバーの一部が在宅勤務、一部がオフィス勤務というシーンも多くなってきました。 物理的な距離感がある中で「円滑なプロジェクト管理がしにくい」「関係者間のコミュニケーションがとりづらい」と感じるプロジェクトオーナーの方々も多いのではないでしょうか。
ガントチャートの機能不全、カジュアルな情報共有が増加
働き方や社会環境の変化に伴い、タスクの進捗管理にも変化が現れてきています。 Excelでガントチャートを作っても、担当者の更新の手間や仕事の仕方の違いにより、徐々に機能しなくなるということがよく起こります。 「その件は、チャットで都度確認しましょう」「会議後にちょっとオフィスで話しましょう」といったカジュアルなコミュニケーションが増え、人によって情報量にばらつきが発生。プロジェクト全体の進捗が見えにくくなっていきます。
社外のベンダーやパートナーが関わってくるとプロジェクトがカオスに...
プロジェクトが始動すると社外ベンダーやパートナーとタスクやファイル共有をするようになります。 Teamsでは社外とタスク共有ができず、Slackだと全体像が見えづらい。。Excelファイルもどれが最新なのかわからず、関係者も増え、カオスな状況になりがちです。プロジェクト遅延、メンバーのモチベーション低下、売上毀損などさまざまなリスクが想定されます。
プロジェクト管理やコミュニケーションの煩雑化を解決できるツールをどう選ぶか?
本セミナーでは、テレワーク環境下でスピーディーで柔軟な情報共有がしづらいと課題に感じている企業様向けに、プロジェクト管理ツールの選び方、monday.comを使ったソリューションを解説いたします。
monday.comはイスラエルのスタートアップ企業で、グローバルに約145ヵ国・10万社が導入しているビジネスプラットフォームです。ヤフー、アディダス、AT&T、Samsung、WeWorkなども利用しています。900円〜/IDで利用でき、プロジェクト管理、CRM、DB、チャットなどの機能を兼ね備え、Excelのような自由度が実現できることが特徴です。
こんな人におすすめのセミナーです
・Salesforce, Slack, Teamsなどを導入しているがプロジェクトの一元管理ができない ・初期設定や操作性が複雑で、使いこなせるまでに時間がかかる ・社外のベンダーとの進捗共有やファイル管理の手間がかかっている ・関係者が多く、働き方も多様なため情報共有が遅くなっている
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:40 DX時代「タスク見える化」が鍵!急成長ハイパフォーマンスチームの特徴を解説
・10分でわかるDX
・ハイパフォーマンスチームの特徴
・monday.com 製品紹介(機能、特徴、導入事例)
・monday.com 製品デモ
11:40~12:00 質疑応答
主催
OrangeOne株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
新しい働き方・デジタルワークシフトを実現するためのSaaS選びのポイント
4.1 ネクストモード株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
レガシー企業でなぜリモートワーク、ワーケーションが定着しないのか?
2021年のクロス・マーケティング社の調査によると、テレワーク実施企業が約40%、ワーケーション率は6.6%という結果となりました。 まだまだテレワークやワーケーションは国内に定着したとは言えない状況です。 その理由の1つが、働き方改革の社内導入が大前提にあるからです。 働き方の多様化が進んでいない企業ほど、働く場所や時間の制約を取り除くことは難しいでしょう。
働き方改革の基盤をつくる「SaaS選び」
働き方改革の導入や定着を妨げる理由には人事制度や労働慣習の他にも、IT環境やセキュリティの問題が潜んでいます。 快適にリモートワーキングを進めるために、インフラ・ツール、特にSaaSの導入は不可欠です。 コラボレーションツール、プロジェクト管理、ビデオ会議、ID認証、VPNなど、DX時代に必須なSaaSをどのように選べばよいのでしょうか?
デジタルワークシフト実践で押さえておくべきポイントとは?
本セミナーでは、これからリモートワーク・ワーケーションを推進していく企業様向けに、新しい働き方・デジタルワークシフトを実現するためのSaaS選びのポイントを解説いたします。現在利用しているSaaSを見直したい方、リモートワークに最適なIT環境を構築したい方のヒントになる内容です。奮ってご参加ください。
プログラム
14:45~15:00 受付
15:00~15:05 オープニング(マジセミ )
15:05~15:25 DX時代のマネジメントとデジタルワーク
登壇者:組織変革Lab 主宰 沢渡あまね氏
15:25~15:35 ワーケーション実践から見えてきたこれからのプロジェクト管理とセキュリティ(ネクストモード)
登壇者:ネクストモード株式会社 代表取締役 里見 宗律
15:35~15:55 クラスメソッド、ネクストモードのソリューション紹介
15:55~16:00 質疑応答
主催
ネクストモード株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
クラスメソッド株式会社(プライバシー・ポリシー) 株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
FAXやメールで来る大量の注文書を、自動的に受注システムに投入する ~マスターデータとの突...
3.6 株式会社インフォディオ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
※2022年1月21日に行ったプログラムが好評でしたため、同内容にて開催します。 ただし、前回よりもさらにお客様の声にお答えしたセミナーにバージョンアップしています。
データ入力は最も「自動化したい」業務
2019年6月にMM総研が1,000社に行ったリサーチ結果によると、51.5%のオフィスワーカーが「最も非効率な業務」として「データの入力・登録」と回答しています。
一方で、国内でAI-OCRを導入している企業は9.6%ですが、85.7%が「データ作成に要する時間を削減できた」、82.1%は「ミスの発生率」を、78.6%は「当該業務に必要な人員数」を改善できた、と導入した企業からは高い満足度が得られています。
注文書におけるAI-OCRは自動化や複数ページや非定型フォーマットなど課題が残る
一方でAI-OCRにも課題は残ります。顧客からの注文書のフォーマットは多岐にわたることが多く、注文書が複数枚で構成されていたり、決まった形式のフォーマットでない場合は、文字データに変換できない場合があります。
また、注文書におけるAI-OCRの場合は、注文書を受けてからデータをスキャンするまでや、スキャンしたデータを格納するまでを自動化処理できないと、本当の意味で「手作業をなくす」ことにはなりません。
そのため注文書の自動化には、AI-OCRだけではなく、RPAまで導入している企業も少なくなりません。
マスターデータとの突合も
注文書革命DXは注文書に特化したAI-OCRです。そのため、注文書を受け取るところからデータを基幹システムに導入するまで一貫した対応が可能で、RPAの導入も不要です。
さらに、マスターデータとの突合を行うことで入力データの正確性を補うことも可能です。
本セミナーでは、これまでのAI-OCRでは対応の難しかった複数および非定型フォーマットをどうやって読み込むのか、
他社と比較して「安い」と言われる理由や、注文書の自動化を注文書革命DXだけでどうやって完結するのか、について解説します。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 FAXやメールで来る大量の注文書を、自動的に受注システムに投入する
11:45~11:55 質疑応答
主催
株式会社インフォディオ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)