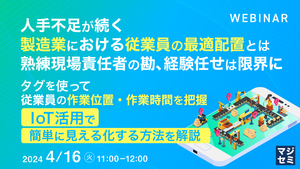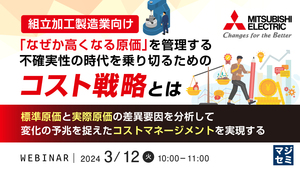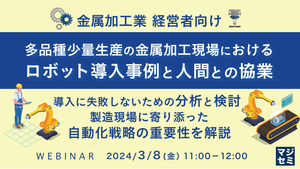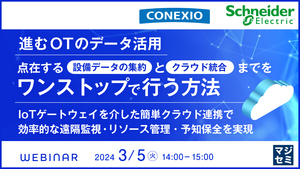製造DX・物流DX
Manufacturing industry
製造DX・物流DXの課題を解決するウェビナー
自動運転、ビッグデータ活用、AI/IoT 導入、サプライチェーン改革...。デジタル化が急速に進んでいる製造・物流業界を対象としたデジタルトランスフォーメーション&ロジスティクス4.0 関連のウェビナー/オンラインセミナー。
製造DX・物流DX
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
製造DX・物流DX
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
【物流・製造業向け】2024年問題はドライバー問題だけではない 荷待ち時間・出庫作業へも影響...
3.8 株式会社ゼネテック
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
ドライバー不足だけではない。2024年問題で変革を迫られる物流・製造業
日本の産業界を大きく揺るがす危機的状況として、警鐘が鳴らされている「物流の2024年問題」。 ドライバーの時間外労働の条件規制適用制限により派生する、ドライバーの荷待ち時間や荷役の問題など、さまざまな面で業務変革が迫られています。 さらにこの問題は、製造業におけるサプライチェーンにも大きな影響をもたらすと言われています。
経験と勘頼りの現場作業では、生産性の向上は難しい
生産性を向上したいと考えてはいるものの、実際の現場は旧態依然としていて、経験と勘に頼った運用を続けているという企業が多いのではないでしょうか。 現場のヒト、モノの流れを分析して最適化したいという悩みはあるものの、何から手をつければよいのかわからないという声も多く挙がっています。
最適搬送・最適導線・最適配置がひと目でわかる。簡単操作の3Dシミュレーション
リスクのない仮想空間で、データを有効活用して現実世界の最適搬送・最適導線・最適配置を求める方法があることをご存知でしょうか? 今どこで誰(何)が動いているのか、従業員や設備の過不足を3Dシミュレーションで見える化し、課題を検出、改善する方法をご紹介します。 物流・製造業での数多くの実績を持ち、倉庫など物流現場のレイアウトや工場の生産ラインを、動いている現場を止めることなく簡単操作でシミュレーションする方法を、導入事例を交えながら、わかりやすく解説します。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 【物流・製造業向け】2024年問題はドライバー問題だけではない 荷待ち時間・出庫作業へも影響が~脱経験と勘頼りの現場作業 3D解析シミュレーションによる最適搬送・最適導線・最適配置とは~
11:45~12:00 質疑応答
主催
株式会社ゼネテック(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。
柔軟性を兼ね備えた”スマートファクトリー”構築のベストプラクティス3選 ~#AWS #Azu...
3.2 株式会社テクノプロ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
進む製造業のDX化と求められるデータ駆動型の意思決定
近年の製造業界では、センサーやカメラを含むIoTデバイスやOTデバイス、AIと機械学習技術の飛躍的な発展などにより、生産性の向上や、品質の改善、イノベーションの加速を目的とした組織内の多様なデータを活用する動きが進んでいます。
このためIT部門では、スマート工場実現に向けた取り組みや、データ駆動型の意思決定を支援するため、組織内のさまざまな部門や工場に点在している様々なデータをクラウド上に集約し、可視化や分析を行うためのデータ基盤の構築が求められています。
製造業のデータ活用には、変化に対応できる柔軟なデータ基盤が必要
しかしながら、製造業のIT部門がクラウド上でこのようなデータ基盤を構築するには様々な課題があります。
製造業では、設計データ、製品の生産・品質データ、工場設備の稼働データなど、多様なソースからさまざまなフォーマットのデータが生成されます。これらのデータは日々蓄積され、継続的に増加していきます。さらに、製造業界は世界的な競争の激化、消費者ニーズの多様化、そして急速な技術革新に直面しています。これらの変化に迅速に対応し、企業戦略を素早く立案し再構築する必要性が高まっています。
このため、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するためのデータ基盤は、多岐にわたるデータフォーマットの一元管理と、日々増加するデータ量に対応する拡張性に加えて、データの種類や分析手法を素早く変更できる柔軟性が必要になります。
これらの課題に対処するため、IT部門は、クラウドサービスプロバイダーが提供する豊富なツールとサービスを活用し、ベストプラクティスに基づくシステム設計を行うことが求められます。
また、ビジネス環境の急激な変化に適用するため、リソースの監視、パフォーマンスの最適化、トラブルシューティングに加えて、システムを柔軟に改善してアップデートする強力な運用体制の構築が不可欠となります。
AWS、Azure、Snowflakeそれぞれの特徴と導入事例を紹介
本セミナーでは、製造業におけるデータ活用の課題に焦点を当て、機械学習を活用したIoTデータ基盤やオンプレミスとのハイブリットシステムの事例、データウェアハウスに特化したSaaSサービス「Snowflake」との連携事例など、AWSやAzureを中心とした豊富なクラウドサービス機能を活用した実例をもとに詳しく解説します。
テクノプロ・デザイン社では、長年製造業で業界最大規模の技術サービスを提供して参りました。 お客様のクラウドを利用したデータ活用に関しても、AWS・Azureなど様々なクラウド環境の導入やオンプレミスからの移行など、ビジネス課題の洗い出しから計画立案・設計・構築・移行・運用保守の継続的な運用に至るまで、幅広いサポートが可能です。
特に ・機械学習も含めたIoTデータ基盤の構築に携わる方 ・クラウドサービスを活用した業務効率化や、部門横断のデータ活用に関心を持っている方 ・様々なクラウドサービスを柔軟に活用する最適解や事例を知りたい方 ・AWS、Azure等を既に活用しているが、何らかの理由で壁にぶつかっている方 などに特におすすめです。
プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 柔軟性を兼ね備えた”スマートファクトリー”構築のベストプラクティス3選 ~#AWS #Azure #Snowflake #BI #機械学習 #分析基盤の構築方法~
10:45~11:00 質疑応答
主催
株式会社テクノプロ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。
求められるローカル5Gへの移行、たった一台でスモールスタートできる「オールインワンの基地局」...
4.0 株式会社iD
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
製造業のDXで求められる高速通信
製造業、建築、物流など多様な業界でデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みが加速しています。
特に製造業では、生産ラインの自動化、リアルタイム品質管理、遠隔設備メンテナンスなどの先進技術の導入が進んでいます。これらの技術を効率的に運用するには、大量のデータを迅速に処理し、素早く転送する強力な通信基盤が必要です。
このような要求に応えるため、「超高速」「超低遅延」「多数デバイスの同時接続」を可能にする5Gネットワーク技術を、特定の施設やエリア内でセキュアでプライベートに構築できるローカル5Gの需要が高まっています。
自社施設へのローカル5G導入は専門知識が必要
ローカル5Gは、基地局と5Gコアネットワーク(5GC)が別々に配置され、システムはセントラルユニット(CU)、ディストリビューテッドユニット(DU)、ラジオユニット(RU)といった複数の要素から構成されます。これにより、企業は自社の特定の業務ニーズに応じて柔軟に設計・構築ができます。
しかしながら、最適化されたネットワークの構築が実現できる反面、ネットワークの設計や導入、運用には専門的な知識が必要になります。 加えて、5Gでは利用される周波数帯域がこれまでの3Gや4Gと比べて直進性が強く、遠距離に届きにくい特性を持っています。
このため、導入する際には、自社の施設内の壁や装置などによる電波干渉や電波遮蔽の影響を慎重に評価し、適切なネットワーク設計を行う必要があります。
さらに、ローカル5Gの設備は高額な初期投資が必要な場合があり、特に小規模な製造業者にとっては大きな負担になるケースもあります。
スモールスタート可能な「オールインワンの基地局」とは
本セミナーでは、ローカル5Gネットワークに必要な機能をたった一台に集約した画期的な基地局製品「NEXASIR(ネクサシア)」を通して、初期投資を大幅に抑えつつ、素早くローカル5Gが導入できる具体的な方法を詳しく解説いたします。
「NEXASIR」は、基地局機能(RU/DU/CU)とコア機能(5GC)を一つのパッケージに統合した製品で、施設内にこの一台を設置するだけで、ローカル5Gネットワークが構築できます。
エリアを拡大する場合は、複雑な設定作業をすることなく「NEXASIR」の台数を増やすことで対応可能です。コア機能を停止するオプションもあり、初期導入時に設置した「NEXASIR」のコア機能を後から追加する「NEXASIR」で共有したり、規模の拡大のためにMVNOやクラウド事業者の5GCサービスを利用する場合は、既存の「NEXASIR」を基地局として継続して利用することも可能です。
これにより、最初は小規模でスタートし、検証しながら段階的かつ効率的にエリアを拡大する運用が可能になります。
ローカル5Gの導入を検討している方で、高額な初期費用に課題を持っている方、まずはスモールスタートして段階的に拡張を行いたい方、などに特におすすめです。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 求められるローカル5Gへの移行、たった一台でスモールスタートできる「オールインワンの基地局」とは
13:45~14:00 質疑応答
主催
株式会社iD(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。
人手不足が続く製造業における従業員の最適配置とは 熟練現場責任者の勘、経験任せは限界に ~タ...
3.5 マルティスープ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
少子高齢化などの影響により、製造業の人手不足はますます深刻化しています
経産省の「2022年版ものづくり白書」によると、製造業における56.3%の企業が、人手不足を問題としています。 工場や施設で人材の募集をかけても、必要な人材を確保できないケースが目立っている状況です。「このまま人材不足が進むとビジネス的な影響も避けられない」と改革が迫られるようになってきました。
限られた従業員で生産性を向上するためには、経験・勘まかせの人員配置では限界に
これまでは、熟練した現場責任者の勘、経験に任せて、従業員を配置していた企業も多いのではないでしょうか。限られたリソース(人・モノ)で生産性効率をアップしたいとは思っていても、その方法がわからないと頭を悩ませている企業も少なくありません。
従業員の作業位置・作業時間をタグで情報収集 IoT活用で見える化する方法とは
名札ケースに入るほどの小さなタグを使って、従業員の作業位置・作業時間を簡単に把握することができるiField。 収集した情報はITの専門家でなくとも分析が可能。PC・スマホ・タブレットで簡単に見える化することができます。 iFieldの導入により従業員の各工程の作業時間や、行程の流れ/停滞の状況を定量的に分析し、生産性向上に成功した実例を紹介しながら、製造業の未来についてわかりやすく解説いたします。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 人手不足が続く製造業における従業員の最適配置とは 熟練現場責任者の勘、経験任せは限界に ~タグを使って従業員の作業位置・作業時間を把握、IoT活用で簡単に見える化する方法を解説~
11:45~12:00 質疑応答
主催
マルティスープ株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー) ※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。
(組立加工製造業向け)「なぜか高くなる原価」を管理する、不確実性の時代を乗り切るためのコスト...
3.7 三菱電機ITソリューションズ株式会社
本セミナーのレポート(記事)を以下で公開しています。ぜひご参考ください。
https://majisemi.com/topics/webinar-summary/5604/
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
複雑化する原価の変動要因
近年の製造業界は、激しい為替変動などのマクロ経済環境の変動や、原材料や物流コストの急激な高騰、AIを含む技術革新の急速な進歩などにより、経営を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。
このような背景から、製品の原価に影響を与える要因は以前に比べてより複雑化しています。そのため、製造業の企業が適切な利益を確保して、持続可能な成長を達成するためには、原価上昇の原因を正確に特定して、素早く対処できる体制を確立することが不可欠です。
原価管理には、高品質データの収集と分析基盤が必要
しかしながら、製造業の原価管理の整備には多くの課題があります。
特に、原材料の使用量、労働時間、機械の稼働時間といった直接費に加え、作業員の効率、使用スペースや、電力消費量などの間接費の管理も非常に重要になります。これらのコストを、製品単位、顧客ごと、各製造工程ごとなど、目的に合わせた様々な視点で詳細に分析できるようにする必要があります。
さらに、原価計算は一度きりの作業ではありません。計画外の受注、従業員の交代、市場の変動など、様々な要因により予測と実績に差が発生します。これらの差異を素早く特定し、適切な対策を立てるためには、高品質なデータの継続的な収集と、そのデータを効果的に管理・分析するシステムの構築が不可欠です。
不確実性の時代を乗り切るためのコストマネジメントの実現方法とは
本セミナーでは、コスト戦略の立案を支援する「mcframe 7 PCM」を通して、自社のデータをどう管理すればよいのか、間接費の配賦をどう設定すれば良いのかなど、原価管理のPDCAを回すための具体的な実現方法を解説します。
「mcframe 7 PCM」は組立加工製造業向けの強力なプロダクト・コスト・マネジメントシステムです。プロダクトライフサイクルとサプライチェーンの両軸を基に、コスト、キャッシュフロー、機会損失、収益性の各視点から、企業全体の原価管理をサポートします。
製造業における原価管理に関わる方で、原価の予測精度向上やコスト削減を目指しているが、どこから始めれば良いかわからない方、複数のシナリオを素早く検討して、収益予測を行いたい方、などに特にお勧めです。
プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 (組立加工製造業向け)「なぜか高くなる原価」を管理する、不確実性の時代を乗り切るためのコスト戦略とは(前半:アットストリームパートナーズ合同会社 / 後半:三菱電機ITソリューションズ株式会社)
10:45~11:00 質疑応答
主催
三菱電機ITソリューションズ株式会社(プライバシー・ポリシー) 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社は、2025/4/1から三菱電機デジタルイノベーション株式会社となりました。 三菱電機デジタルイノベーション株式会社:https://www.MitsubishiElectric.co.jp/medigital/
共催
アットストリームパートナーズ合同会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
【デスクレスワーカー向け】現場データを安全に管理し、有効活用するには? 〜遠隔支援にとどまら...
3.3 AMA Xperteye株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
現場のデジタル化の背景とニーズ
産業や医療現場において、人手不足や熟練者不足、技術の伝承の問題が深刻化しています。 近年では、若手社員や取引先とのサポート、トレーニング、遠隔地との作業などにおいて、遠隔支援が必要不可欠なツールとして活用されています。 これらの現場での作業には、企業のノウハウを含む多岐にわたる知識が必要であり、その場で継承されます。 さらに、品質の向上を目指して、現場での作業のエビデンス化が求められています。 このような状況下で、効率的な遠隔支援システムの構築と現場データの活用がますます重要性を増しています。 しかし、現場データをセキュアに収集・共有し、実際の業務改善に活かす方法は、多くの組織が直面する課題です。
自社AI導入の課題
生成AIのビジネスへの導入が本格化している中、自社がAIを活用するためには、自社のデータが不可欠です。 このデータを利用することで、AIは自社の特定のニーズや業務に適応し、学習していきます。 さらに、現場で蓄積されたノウハウをAIに組み込むことで、効果的な業務支援や意思決定の補助が可能になります。 つまり、生成AIのビジネス導入においては、自社のデータを活用し、現場ノウハウを取り入れることが重要です。
一時的な遠隔支援に留まらず、現場作業のデータをより有効活用するには?
スマートグラスなどの遠隔支援技術は、デスクレスワーカーへの即時的な知識提供と指導に役立ちますが、そのポテンシャルは一時的な問題解決にとどまりません。 重要なのは、現場で収集されるデータを、セキュリティを確保しつつ、長期的な業務改善や効率化に活用することです。 具体的には、AI等を駆使し、データから得られる洞察を実務にフィードバックする手法が求められています。
デジタル証明で安全性を保証しつつ、AI等に有効活用
このセミナーでは、デスクレスワーカーが直面する現場の課題を解決するためのデジタルツールの活用法を紹介します。 セキュリティを考慮しつつ、現場データの収集から分析、活用までの一連の流れを、遠隔支援ソリューションを用いてどのように効率化し、生産性向上につなげるかに焦点を当てます。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 【デスクレスワーカー向け】現場データをセキュアに保存しつつAI等に有効活用するには?〜遠隔支援にとどまらない、デスクレスワーカーのデジタル改革〜
11:45~12:00 質疑応答
主催
AMA Xperteye株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
【金属加工業 経営者向け】多品種少量生産の金属加工現場におけるロボット導入事例と人間との協業...
3.9 FAロボットマネジメント株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
本セミナーは、製造業・金属加工業 経営者様に向けた内容となっております。 他業種からお申込みの場合には、ご参加をご遠慮頂く場合がございます。予めご了承下さい。
中堅・中小製造業・金属加工業における深刻な人材不足と属人化
中堅・中小製造業の人材不足の問題は年々深刻化しています。 特に金属加工業においては、生産工程が属人化していることによる影響が大きく、人材不足がもたらす、後継者不足、技能伝承不足、生産性縮小による経営リスクはこれまでに類を見ないほどになっています。 従業員の高齢化が進む今、事業の見直しを迫られる企業も少なくはありません。
金属加工業において自動化・FAロボットの導入がすすまない要因とは
大規模な生産ラインでこそ、導入のメリットがあると思われてきた自動化。 中堅・中小企業では、ロボットやデジタル技術に対応できる人材がいないと、初めから諦めてしまうケースも。 しかし、現場に寄り添って丁寧にその生産工程を分析することで、中堅・中小企業こそFAロボットを導入するメリットが大きいことがわかってきました。DXへの対応が難しいと思われてきた金属加工業においても、どの工程をロボットに任せるかを切り分けることで、技術力の高い人材にしかできない業務に適切な人員配置が可能となり、トータルとして生産性を向上させることができるのです。
FAロボットによる多品種少量生産が可能な時代が始まっています。
多品種少量生産体制と客先要求による度重なる仕様変更などによる難易度が高いと思われてきた金属加工業。 しかし、ロジックと分析と最新の機器活用によるシステムの検討を行う事で多品種少量生産の自動化は可能です。 現場に寄り添った、人間とFAロボットとの協業が可能となる生産現場とはどのようなものかを解説いたします。 あわせて、自動化・ロボット化を進めていく上で、絶対に抑えなければいけないポイントや注意点など自動化検討のノウハウ、最新の自動化機器や導入事例をご紹介いたします。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 【金属加工業 経営者向け】多品種少量生産の製造現場におけるFAロボットと人間の協業 最初の一歩~導入に失敗しないための分析と検討 製造現場に寄り添った自動化戦略の重要性を解説~
11:45~12:00 質疑応答
主催
FAロボットマネジメント株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
工程間搬送だけじゃない! 自走式ロボットのリモート操作で「自動化」を超える設備導入
3.8 リモートロボティクス株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
ウェビナー概要
工程間搬送や加工機へのワークロード・アンロードの自動化に貢献する自走式ロボット「TRanbo-7」を提供する川崎重工業株式会社から大内哲志さんをお招きして開催します。 自走式ロボット「TRanbo-7」をリモート操作することで、実現できること・解決できる課題をデモ動画を交えてお話します。
こんな方におすすめ
●生産工程で加工機を多く保有され、工程間搬送の人手不足などから生産ロスにお悩みの方 ●ロット始まりの目視確認など不定期に発生する対応事項が要因となる設備稼働率の歩留まりにお悩みの方 ●設備の不具合状況を都度現場まで確認に行く必要があり、ダウンタイムにお悩みの方
現場作業を取り巻く環境
正社員の人手不足企業の割合は52.1%と2社に1社以上が人手不足を実感(帝国データバンク 人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月))するも、人手不足解消としてロボットシステムや生産設備の導入を検討しても、費用面や技術面などが要因で自動化が難しい現状があります。「品種が多く自動化できているのは一部だけ」や「自動化設備を導入してもほったらかしにはできず手がかかる」といった悩みもお聞きしています。 一方、年間226万人もの方が働きたくても働けない状況です。製造業においては、柔軟な働き方の選択肢であるテレワーク普及率は26.0%と非製造業の普及率33.5%に比べて低く、全産業では45.0%まで上昇している女性就業者の数も製造業は30%前後の横ばいが続いています。 リモートロボティクスはすべての人々が社会参加できるリモート社会の実現を目指し、新しいワークスタイルを提案することをパーパスに掲げ、毎日のロボット遠隔操作業務を実現するクラウドサービス「Remolink」を通じて、人手不足に悩む企業と働きたい方々をつないでいきます。
人とロボットの役割分担を実現する「Remolink」とは
リモートロボティクスが提供する「Remolink」はクラウドを経由して現場にあるロボットとリモート環境にいる人がともに働くためのクラウドサービスです。 現場のロボットシステム側でのエラー発生時やロット始まりで目視確認をしなければいけない場合などに、現場ロボット側の画像情報やステータス情報をリモート環境にいる人に伝え、人が状況を判断し、ロボットに対して次の動作指示を行います。 リモート環境だからこそ、一人の人が複数のロボットシステムの”人が担当すべき業務”を行い、人1対ロボットNの働き方が実現できます。
川崎重工が提供する自走式ロボット「TRanbo-7」とは
慢性的な労働力不足の解消や生産性向上を目的とし、工場内の工程間搬送を自動化する自走式ロボットで 川崎重工製小型汎用ロボット「RS007L」に自社開発の走行部を組み合わせたパッケージ商品です。
特長 ●スリムなボディ設計と高い走行性能 JIS規格で推奨される工場通路幅800mmに対応するスリムなボディ設計により、狭い通路も走行できます。また、狭い工場内の移動に不可欠な旋回(進路変更)が可能で、既存の通路の走行を最小限のレイアウト変更で実現することが可能です。 ●サイクル中に自動で充電可能な非接触充電(オプション) 非接触充電もオプションで選択可能です。走行コースの中に充電ステーションを組み込むことでサイクル中に自動で充電することが可能となり、長時間の運用が実現できます。 ●アーム部と走行部を1つのコントローラで制御 1つのティーチペンダントでアーム部も走行部も操作可能です。シンプルな機器構成と低コスト化を実現しています。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング
11:05~11:25 リモートロボティクス:ロボットの限界をリモート操作で超えていく「Remolink」
11:25~11:50 川崎重工:自走式ロボット「TRanbo-7」×リモートで自動化を超える価値提供を
11:50~12:00 質疑応答
主催
リモートロボティクス株式会社(プライバシー・ポリシー)
共催
川崎重工業株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
進むOTのデータ活用、点在する設備データの集約とクラウド統合までをワンストップで行う方法 ~...
3.6 コネクシオ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
進む製造業のOTデータの活用
近年の製造業は、センサやカメラなどIoTやOT向けデバイスの進化や、AIと機械学習の急速な発展、クラウドの普及などにより、設備や装置の稼働データの活用が拡大しています。
これらのデータは、遠隔監視やリソース管理だけでなく、機械学習を用いた予知保全などのデータ駆動型アプローチの実現など、様々な応用が期待されています。
このような背景から、収集されたデータを一元的に集め、リアルタイムでの可視化や分析を可能にするクラウドベースの統合プラットフォームへの需要が高まっています。
OTデータのクラウド化には専門知識が必要
しかしながら、これらのOTデータをクラウドへ統合するには様々な課題があります。
通常、製造設備から得られるデータは、制御やメンテナンスなど特定の目的に合わせて設計されているため、設備ごとにデータフォーマットや通信プロトコルが異なります。そのため、これらのデータをクラウドで一元的に管理し活用するには、各種プロトコルをサポートする専用アダプタの準備や、クラウド側にデータを統合するための変換処理や整合性チェックが不可欠です。
さらに、多くの既存設備は通信機能を備えていないため、通信設備の導入のための互換性やセキュリティ対策なども考慮する必要があります。
OTデータの収集からクラウド化までをワンストップで実現する
本セミナーでは、通信機能を搭載したIoTゲートウェイ「CONEXIO BlackBear」と、クラウドベースのIoTプラットフォーム「AVEVA InSight」を利用して、既設装置からのデータの収集からクラウド化までを、ワンステップで実現する方法を詳しく説明します。
「CONEXIO BlackBear」は、SIMカードを搭載可能で、センサ、カメラ、ECUなど様々なデバイスに対応するインターフェースを備えたIoT専用ゲートウェイです。複雑な通信設定やクラウド設定なしにデータをクラウド上に統合することができます。「AVEVA InSight」はこんな課題を持つお客さまへむけたSaaS型の履歴データ管理活用サービスです。 機械の予兆保全を行いたい。 設備の稼働率監視し、生産効率をあげたい。 AI分析を行いたいが社内にデータサイエンティストがいない。 社内で新たにシステムを構築するリソースがない。 クラウド上で現場の生産現場のデータを一元管理したい。
製造業で設備保全の効率化や現場のDXを実現したい方で、既存の設備データの集約やクラウド化に課題を持っている方、現場データを活用したデータ駆動型アプローチを目指している方、などに特におすすめです。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 進むOTのデータ活用、点在する設備データの集約とクラウド統合までをワンストップで行う方法
14:45~15:00 質疑応答
主催
コネクシオ株式会社(プライバシー・ポリシー)
共催
シュナイダーエレクトリック株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)


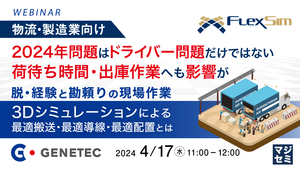
.jpg?1711430422)