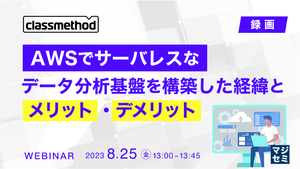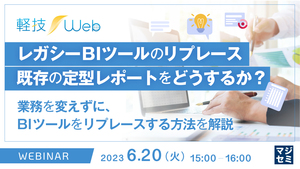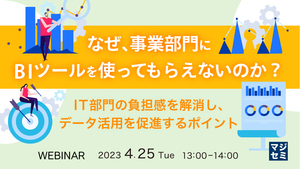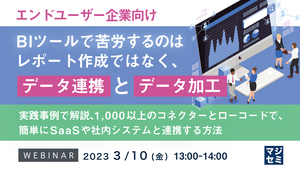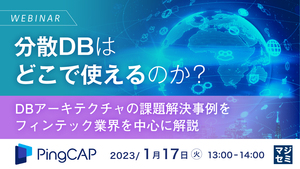データ活用
Data
データ活用の課題を解決するウェビナー
ビッグデータ活用、データドリブン経営、クラウド DWH 構築、各種データ分析・効果検証手法など。データサイエンティストによる実践的なウェビナーや、業界ごとの事例がわかるオンラインセミナーを探せるコーナーです。
データ活用
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
データ活用
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
なぜ、営業ダッシュボードを作ってもアクションにつながらないのか? 〜QuickSightとT...
3.8 クラスメソッド株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
講演は、事前に撮影した録画を配信します。
質疑応答については、司会者のアナウンスに沿い、当日アンケートにご質問をご入力ください。 講演企業から、後日個別に回答させていただきます。 奮ってご参加ください。
営業活動に欠かせない、ダッシュボードによるデータ活用
現代の営業活動では、単なる人間力や経験だけでなく、データを駆使することが求められています。 データ活用において、複雑なデータを一目で理解しやすい形に可視化するダッシュボードは、営業活動の効率化や結果の最大化を実現するための重要な要素となります。
ダッシュボードを作ってもアクションにつながらない
しかしながら、ダッシュボードを導入しても、なかなか具体的なアクションや結果につながらないケースは多いです。
正しいプロセスに基づいてダッシュボードを設計・構築しなければ、データを可視化しても見るだけ
で終わってしまい、そこから具体的な行動を導き出すことはできないのです。
QuickSightとTableauを駆使したダッシュボード構築事例を紹介
本セミナーでは、「Tableau」と「Amazon QuickSight」によるデモを交えながら、正しいプロセスにもとづいた営業分析ダッシュボードの設計方法、データ分析基盤の構築方法について解説します。
こんな方におすすめです
・BIツールの導入を検討している方 ・導入済のBIツールをさらに活用したい方 ・具体的なダッシュボード設計の例を知りたい方 ・ビジネスデータを効果的に活用したい方
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:35 データから行動へ!TableauとQuickSightを使った営業分析ダッシュボードの設計方法
13:35〜13:45 ダッシュボードを支えるデータ分析基盤を手早く構築する方法
13:45〜13:55 クラスメソッド アナリティクス分野での支援について
主催
クラスメソッド株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
予算編成の大問題「Excelのバケツリレー」を脱Excelで実現する ~集計の効率化と正確な...
3.4 ハイテクシステム株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
変化が激しい中で増す業績予測の必要性
現代のビジネス環境は、テクノロジーの進化や市場の変動により日々変化しており、その変化に迅速に対応することが求められます。 そのような状況においては、正確な業績予測によって企業の未来を見据え、戦略的な意思決定を下すことが重要です。
予測どころか集計すらままならない実情
しかし実際には、データの集計に膨大な手間と労力を要しており、業績予測はおろか過去実績の取りまとめすらままならない実情があります。 集計が困難となる理由は、担当者や拠点によってデータのフォーマット・管理方法などが異なっており、統一性が欠けていることが大きな要因として挙げられます。 このような状況下では、全体の業績を一元的に集計する際に、データの整合性を取る作業が非常に複雑となります。
使い慣れたUIを保持しつつ、データ集計・業績予測を可能にする
本セミナーでは、データ集計の効率化と正確な業績予測を同時に実現する方法として、使い慣れたExcel式のUIを保持しつつ、断片化や複雑化したデータを一元的に集計・管理するソリューション「Board」を紹介します。 経営企画部・財務経理部で、複数の支店や担当者間での業績データの断片化や集計・管理の困難に頭を悩ませている方はぜひご参加ください。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 予算編成の大問題「Excelのバケツリレー」を脱Excelで実現する~集計の効率化と正確な業績予測で、経営管理DXを実現~
14:45~15:00 質疑応答
主催
ハイテクシステム株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
大量のマーケティングデータがあるのに、なぜ活用できていないのか? 〜有効なデータを、Tabl...
3.3 株式会社ウフル
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
施策のPDCAには、横断的な検証が必要
LTV最大化のための企業のマーケティング活動は多岐に渡り、多くの情報を把握しなければなりません。施策のPDCAに必要な顧客行動、商品の売上動向、サイトアクセスなどのデータは分散していることも多く、タイムリーで横断的な検証は容易ではありません。
Excelだけの検証はすでに限界
データ活用によるOne to Oneマーケティング、顧客の嗜好や行動に対応したパーソナライゼーションのニーズにともない、考慮すべきデータ量はますます大規模になっています。このように多様で大量のデータをリアルタイム性をもって分析するにはTableauのようなBIツールの活用が有効です。今後のAI活用も視野に入れると、データ分析基盤の検討が必須といえるでしょう。
顧客行動の可視化をスピーディーに実現
本セミナーでは、データが十分に活用されていない原因を整理したうえで、それら課題へのTableauのアプローチを解説します。マーケティングデータ活用に有効なBIツールTableauを紹介しながら、RFM分析を例にとったデモと、その他マーケティング部門で抑えておくべきダッシュボードを紹介します。
該当する業種・部門、次のようにお考えの方、ぜひご参加ください。
・B to C企業のマーケティング部門
・BIの導入を検討している
・マーケティングのDXに興味がある
・データを積極的に活用したい
プログラム
15:45~16:00 受付
16:00~16:05 オープニング(マジセミ)
16:05~16:45 大量のマーケティングデータがあるのに、なぜ活用できていないのか?〜有効なデータを、Tableauを用いてどのように見つけ出すか〜
16:45~17:00 質疑応答
主催
株式会社ウフル(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
【ユーザー企業向け】データを"見るだけ"で終わりにしない、成果へ直結する業績ダッシュボードの...
3.4 NDIソリューションズ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
経営判断・意思決定に欠かせないデータ活用
現代のビジネス環境は刻一刻と変化し、その中で常に効果的な経営判断や意思決定を求められます。 そのためには、リアルタイムでのデータ分析による意思決定の迅速化や効率化、データの可視化による情報共有が必要です。
データを集計・可視化するだけではアクションや成果につながらない
データを見て経営判断・意思決定を行う経営者や経営企画部の方々が感じているであろう課題の一つが、データを見るだけ
で終わってしまうということです。
データを集計し、ダッシュボード等で可視化したところで、具体的なアクションにつながらず、経営上の成果に結びつかなければ、それは本当の意味でのデータ活用とは言えません。
ビジネス効果を最大化する業績ダッシュボードの作り方
本セミナーでは、リアルタイムにデータを分析・監視・トラッキングし、ビジネス効果を最大化するための具体的なアクションを導き出す業績ダッシュボードづくりのポイントをご紹介します。 BIプラットフォームDomoを用いた実際のデモや、簡単に業績可視化ができるDomoクイックスタートテンプレートのご紹介も交えながら解説いたします。
・ダッシュボード等で可視化されたデータを見ても、具体的なアクションにつながらず、経営上の成果に結びつかない
・Excelの集計だとリアルタイムに数値を確認・監視・トラッキングできない
・以前BIツール導入にチャレンジしたが、うまくいかなかった
上記のようにお考えの経営者や、経営企画、経理、財務に関わる方はぜひご参加ください。
プログラム
14:45~15:00 受付
15:00~15:05 オープニング(マジセミ)
15:05~15:50 データを見るだけ
で終わりにしない、アクション成果へ直結する業績ダッシュボードの作り方〜臨機応変かつリアルタイムな経営判断が求められる時代に適したBIツールとは〜
15:50~16:00 質疑応答
主催
NDIソリューションズ株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
AWSでサーバレスなデータ分析基盤を構築した経緯とメリット・デメリット
3.8 クラスメソッド株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
講演は、事前に撮影した録画を配信します。
質疑応答については、司会者のアナウンスに沿い、当日アンケートにご質問をご入力ください。 講演企業から、後日個別に回答させていただきます。 奮ってご参加ください。
データ分析基盤の必要性
現代のビジネス環境では、データが組織の成功を左右する重要な要素となっています。 しかし、データは多くの場合、様々な場所に散在しています。これらのデータを個別に活用するだけでは、全体像を把握することは難しく、データ間の相関関係から新たな知見を得ることは一層困難となります。そこで必要となるのが、これらを一箇所に集約するデータ分析基盤です。
データ分析基盤の構築・運用は複雑で時間もかかる
データ分析基盤の構築は非常に複雑な作業であり、高度な専門知識を要します。 さらに一度構築した後も、データ量の増加やビジネスニーズの変化に対応するための継続的なメンテナンスとアップデートが必要となります。
サーバーレスなデータ基盤構築の事例を解説
本セミナーでは、Amazon Redshift Serverlessへの移行によってサーバーレスなデータ基盤を構築した株式会社ホンダトレーディング様の事例を紹介します。Amazon Redshift Serverlessへの移行を判断した経緯から、移行中に直面した課題とその解決方法、移行して良かった点や悪かった点をお話します。 データ分析基盤の構築に課題を抱える方はぜひご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:35 AWSでサーバレスなデータ分析基盤を構築した経緯とメリット・デメリット
13:35~13:40 AWS総合支援サービス「クラスメソッドメンバーズ」のご紹介
13:40~13:45 データ分析基盤かんたん構築「CSアナリティクス」の紹介と機械学習の進め方
主催
クラスメソッド株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
レガシーBIツールのリプレース、既存の定型レポートをどうするか? ~業務を変えずに、BIツ...
3.9 富士電機ITソリューション株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
BusinessObjectsなどの「レガシーBIツール」をリプレースしたい
近年、現場でのBIツールの活用が増える一方で、既存のBIツールのレガシー化(時代遅れ)が問題になっています。 毎年増加する高額な保守費用や、高額なバージョンアップ費用など、課題は尽きません。 また、昨今、社内横断的に情報を活用するニーズが高まり、現場で情報分析・レポート作成する「セルフBI」のニーズが増えてきました。 しかし、レガシーBIでは現場での自由度が乏しくユーザの要求に対応できていないのが実情です。 BusinessObjectsを始めサポート終了するレガシーBIツールもあり、多くの企業ではBIツールのリプレース検討をされています。
Tableauなどのツールには、既存の定型レポートを移行できない
しかし、いざ新たなBIツールの選定を進めると、そこには大きな壁が存在します。 多くのレガシーBIツールは定型的な帳票/レポートを数多く抱えており、それらのレポートは部門の業務と密接に繋がっているのです。 その為、定型帳票/レポートに基く現行業務の踏襲を重視したBIツールを求める場合、それらを出来る限り並行的に移行できることが肝要です。 Tableauなど多くのBIツールには、既存の定型レポートの並行移行が困難であるという問題点があります。 これはレイアウト自在な表の作成や、複雑なクロス集計を苦手とし、紙媒体での帳票出力を想定した書式設定が自由にできないツールが多いためです。
さらに現在の業務を大幅に見直す必要がある
これらのツールでは、これまでの数字をチェックするためのレポートが作成できなくなるため、現在の業務を見直す必要性もあります。 さらに多くのBIツールではユーザー課金であるため、利用者の増加にともないコストも上昇します。
業務を変えずに、BIツールをリプレースする方法を解説
本セミナーでは、現場ユーザー向けセルフBIツールである「軽技Web」を活用することで、これらの課題を解決する方法を解説します。
プログラム
14:45~15:00 受付
15:00~15:05 オープニング(マジセミ)
15:05~15:45 レガシーBIツールのリプレース、既存の定型レポートをどうするか?
15:45~16:00 質疑応答
主催
富士電機ITソリューション株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
なぜ、事業部門にBIツールを使ってもらえないのか? 〜IT部門の負担感を解消し、データ活用...
3.6 ドーモ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
全社的なデータ活用が求められるビジネス環境
データ活用による変革が急務と言われる現代ビジネスにおいて、部分的なデータ活用に留まらない、全社的なデータ活用が求められます。 これに伴い、全社的なデータの管理・統括を担ってきたIT部門に対し、全社でのデータ活用の推進する重責の期待がかけられています。
IT部門が提供したBIツールを事業部門に使ってもらえない
しかし、全社的なデータ活用を目指してBIツールなどを導入したものの、データ活用が定着しないと課題を感じている方が多いのも事実です。 事業部門では、結局Excelを使用し個別に集計を行っていたり、ダッシュボードを作成しても事業部門からダメ出しを受けるなど、IT部門の努力が報われない現状があるのです。
要望へのスピーディな対応、詳細な事業部門の業務知識のない中でデータ活用の促進を担う負担感
一般的にIT部門は事業部門の詳細な業務知識を持っているわけではないため、事業部門が求める可視化した情報やダッシュボードの提供が困難なのは自然なことです。 人手不足に加え多岐にわたる業務に追われる中、スピーディな対応や改善が求められるなど、IT部門は大きな負担感を抱えています。
活発なデータ活用を実現するポイントを実例をもとに解説
本セミナーでは、事業部門での活発なデータ活用を実現しつつ、IT部門の負担も解消する方法について、データ活用の壁を乗り越えた実例とともに、成功の鍵がどこにあるのかを解説します。
・事業部門が積極的にBIツールを使ってくれない、なぜ活用されないのか分からない
・実業務をよく知らないのにダッシュボードの作成を担わねばならない
・情シス人手不足により、スピード感をもって要望に応えられない
上記のようにお悩みの、事業会社におけるIT部門、データ活用を促進する立場の方はぜひご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 なぜ、事業部門にBIツールを使ってもらえないのか?〜IT部門の負担感を解消し、データ活用を促進するポイント〜
13:45~14:00 質疑応答
主催
ドーモ株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
【エンドユーザー企業向け】BIツールで苦労するのは、レポート作成ではなく、データ連携とデー...
3.8 NDIソリューションズ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
DX推進に不可欠なBIツール
VUCAと言われる時代、企業の経営判断にスピードが求められています。 また、通商産業省が「DXレポート2.1」で指摘するように、競争力の高い企業へと変革するためには、データやデジタル技術を駆使することが要求されています。 このような中で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を推進するにあたって、企業のデータを活用し、業務効率化や経営改善につなげる「BI(Business Intelligence)ツール」の重要性は高まっています。
一般的なBIツールの課題、データのつなぎこみが大変、取り込み前の加工が大変
市場では、多くのBIツールが提供されており、「簡単にレポートが作成できる」と謳っています。 しかし、企業のDX担当者や、データ活用の担当者が困っているところは、「レポート作成」ではありません。
テレワークの普及によって増え続けるSaaSについて、すべてBIツールにデータ連携する必要があります。 また、それらのデータフォーマットは統一されているわけではなくバラバラで、すべて加工してからBIツールに取り込む必要があります。 当然ながら、従来の社内システムとの連携も必要です。
多くのBIツールは、レポート作成、データ可視化に重点が置かれており、これらのデータ連携やデータ加工については、専門知識やプログラミングが必要となります。 このような状況から、データ連携、データ加工の作業が、DX担当者やデータ活用担当者の大きな負担となっており、本来行うべき「経営のためにどのようにデータを活用するべきか?」という検討に時間が割けなくなっています。
ローコードで実現可能なデータ連携・加工の手法を解説
本セミナーでは、これらの課題を解決するため、データ連携やデータ加工をドラッグ&ドロップなどローコードで実現する方法について解説します。 自社の事例とデモを交えてクラウド型BIプラットフォーム「Domo」をわかりやすくご紹介する内容となっています。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:50 BIツールで苦労するのは、レポート作成ではなく、データ連携とデータ加工 ~1,000以上のコネクターとローコードで、簡単にSaaSや社内システムと連携する方法~ <デモも併せてご覧いただきます。>
13:50~14:00 質疑応答
主催
NDIソリューションズ株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
分散DBはどこで使えるのか? 〜DBアーキテクチャの課題解決事例をフィンテック業界を中心に解説〜
3.8 PingCAP株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
デジタル化の加速で増加の一途をたどるデータ・アクセス量
デジタル化の急激な進展により、デジタルチャネルの生成するトランザクションとともに、企業が保有するデータ量も増加の一途をたどっています。またデータサイエンス、AI/MLなどの発展により、それらの膨大なデータを分析・活用し、ビジネスに生かす手法も浸透してきました。 しかしながら、それら大量のデータを適切に管理しつつ、高速かつタイムリーに処理・分析しなければならないDB基盤については、ニーズの高まりとは裏腹に大きく変わっていません。
急増するトランザクション、シャーディングなどによる負荷分散には運用コストがかかる
DBにおいては、処理すべきトランザクション数が一定水準を超え、単体でのスケールアップに限界が見えると複数のDBを利用してシステムをスケールする必要が生じます。 スケーラビリティ獲得の手段として従来はシャーディングという負荷分散手法が主に使われてきましたが、テーブルを物理的に複数のDBに分割することから改修が困難になったり、複数のテーブルをまたがるためクエリが複雑化するなど、管理・運用面で様々な課題があります。 シャーディングを効率的に行うためのツールも作られてきましたが、抜本的な解決には至っていないのが実情です。
高まるリアルタイム分析の必要性、OLTP用と分かれる従来のアーキテクチャに課題
また、データ分析の進展とともに、よりリアルタイムに近いデータを分析したい要望が増加していますが、従来のDBアーキテクチャでは実現が難しいという課題もあります。 業務用のトランザクション処理(OLTP)を担うRDBとは別に、データ分析処理(OLAP)を行うDWHを用いる従来の方法では、同期をとるためのタイムラグが課題となります。 タイムラグが起きないよう基盤を統合する手段もあるのですが、アーキテクチャが複雑になる、データ量が多いと著しく性能が低下するなどの問題が生じてしまいます。
DBアーキテクチャの課題解決事例を金融、フィンテック業界を中心に解説
本セミナーでは昨今のオンライン決済推進の流れに伴い、前述のようなDBのスケーラビリティやリアルタイム分析の必要性がより一層高まっている金融、フィンテック業界の事例を中心に解説します。 分散処理技術によって柔軟なスケーラビリティを実現し、トランザクション性能とデータ分析性能を両立した「HTAP(Hybrid Transaction Analytical Processing)」によりリアルタイム分析を手軽かつ高性能で実現した、PingCAP社が提供するMySQL互換のデータベース「TiDB」についても紹介する予定です。
・データ量増加に伴うDB高負荷に柔軟に対応できるアーキテクチャになっておらず、スケールアウトに課題を抱えている
・ビジネスサイドからリアルタイムに近いデータを要求されるケースが増えているが、現在のデータアーキテクチャがその要求に応えられていない
・現在のDBのの性能に課題があり、新技術での解決方法に興味がある
上記のようにお悩みのCTO、システムアーキテクト、DB管理者、アプリ開発者の方は、ぜひご参加ください。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 分散DBはどこで使えるのか?〜DBアーキテクチャの課題解決事例をフィンテック業界を中心に解説〜
13:45~14:00 質疑応答
主催
PingCAP株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)




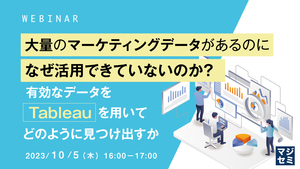
.jpg?1690962317)