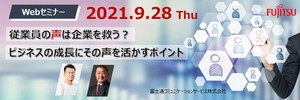ビジネス
Business
ビジネスの課題を解決するウェビナー
デジタルトランスフォーメーション(DX)、カスタマーサクセス、UX/CX、新規事業立ち上げ、ビジネス戦略、ITベンダーの事業戦略など、経営や事業運営に関する考え方や成功事例、ツールに関するウェビナーを探せます。
ビジネス
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
ビジネス
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
企業利用のSlackやMicrosoft Teamsと、取引先やパートナー企業のチャットと...
4.1 株式会社ヴィセント
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
ビジネスチャットの普及
テレワーク環境における、日常のコミュニケーション手段として、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットは広く普及しました。 現在では、業務を進める上で、必須のツールになっています。
社外とのやりとりでは、Slack、Microsoft Teams、Chatwork、Mattermostなど、バラバラ
ビジネスチャットは様々なものがあります。 SlackやMicrosoft Teams、ChatWorkなどが人気ですが、オープンソースのMattermostを使っている企業も多いでしょう。 通常、企業内では単一のツールを使っていることが多いと思います。 しかし、取引先やパートナー企業など社外とのやりとりでは、相手先のツールに合わせざるを得ないケースも多く、結果として複数のツールを同時に使っている企業がほとんどではないでしょうか。
メッセージの送受信を、特定のチャット(例えばMicrosoft Teams)に統合する
本セミナーでは、そのような課題をお持ちの企業に対して、Slack、Microsoft Teams、Chatwork、Mattermostなどのメッセージの送受信を、特定のチャット(例えばMicrosoft Teams)に統合するツール「CHAT-HUB(チャットハブ)」をご提案します。 ユーザーは単一のチャット(例えばMicrosoft Teams)を使いながら、取引先やパートナー企業が使っているチャット(例えばSlack、ChatWork)とメッセージの同期が可能です。
監査やバックアップ
さらに、複数のチャットツールを使っている場合、メッセージの保存ができなかったり、後から監査できない、という課題もあります。 本セミナーでは、ビジネスチャットアーカイバーとして本ツールを導入し、社員が社外とやりとりしているメッセージを全て一元化、バックアップ、監査を可能にする方法についても解説します。
デモンストレーションも
実際の操作感などを体感していただくために、デモンストレーションも予定しています。 また、現在β版としてご評価頂ける企業様を募集中です。 ぜひご参加下さい。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:45 企業利用のSlackやMicrosoft Teamsと、取引先やパートナー企業のチャットとを連携する「CHAT-HUB(チャットハブ)」~ビジネスチャットの一元化、監査、バックアップ~
13:45~14:00 質疑応答
主催
株式会社ヴィセント(プライバシー・ポリシー)
【カスタマーサクセス担当向け】ヘルプデスク・問い合わせ管理・FAQツールの製品比較、スモー...
3.9 OrangeOne株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
対応チャネルが増え続けるユーザーコミュニケーションをどう対応していくか?
WebサービスやECサイトに訪問するユーザーからの問い合わせの管理に苦慮している担当者多いのではないでしょうか? 問い合わせフォーム、メール、チャット、SNS、電話などチャネルが増えていく中で、迅速かつ正確な対応が求められます。 実際に、2021年の株式会社ネオマーケティングの調査結果では、顧客サポートを受けたユーザーのうち、約9割が再度購入したいと思っていることがわかりました。顧客サポートのスピードや質が、顧客獲得に大きく影響していると言えます。
問い合わせ管理、ヘルプデスクツール選びの課題
多くの企業様がすでに無料・有料のさまざまなカスタマーサポートツールを導入されているかと思います。 その中でも下記のような課題があるのではないでしょうか?
・申し込みしても、すぐに導入ができない ・チャットツールを導入したが、迅速対応ができない ・会話のセッションが無効になってしまったり、顧客IDが管理できず、コミュニケーションが分断されてしまう ・問い合わせを減らすためにFAQページを構築しているが読まれない ・網羅性が高いヘルプデスクツールは、初期費用・ランニングコストが高い
これらの課題を解決できるツール選びおよび運用体制づくりが重要になってきます。
ヘルプデスク製品比較のポイントとは?
さらに、製品導入前に下記のチェックリストも吟味して、製品比較を行うことが重要です。
・社内のチーム内で問い合わせ内容や進捗を共有できるか ・自社の業務フローとの相性はいいか ・自社の対応チャネルと連携できるか ・必要な機能が網羅されているか ・案件管理がシンプルにできるか ・ツールのサポート体制は十分か ・ユーザー数が増えるほどコストが上がるのか
しかし実際には、これらを総合的に網羅しているツールを探し出すことは難しいものです。 現実的には、どのようにツールを選んでいくことが最適なのでしょうか?
新規サービスやスタートアップ界隈で利用が増えているFreshdeskを徹底解説。
今回のセミナーでは、ヘルプデスクサービスの製品比較、ツールの選び方を解説いたします。そのうえで、インド発のユニコーン企業であるfreshworks社が提供し、世界で5万社が導入するFreshdeskの機能・特徴紹介、利用シーンごとの具体的な使い方(製品デモ)を行います。新規サービスの責任者、カスタマーサクセス担当などの方におすすめの内容です。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:40 ヘルプデスク・問い合わせ管理・FAQツールの製品比較、スモールにはじめられるツール紹介
・ヘルプデスク・問い合わせ管理・FAQツールの製品比較 ・「Freshdesk」機能・特徴紹介、ユースケースごとの使い方 ・「Freshdesk」製品デモ
13:40~14:00 質疑応答
主催
OrangeOne株式会社(プライバシー・ポリシー)
循環経済(サーキュラーエコノミー)超入門と、ITの役割【IT最新動向ぶっちゃけトーク】株式...
4.1 マジセミ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
循環経済(サーキュラーエコノミー)とは
従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行型の経済システムではなく、これまで廃棄されていた製品や原材料などを新たな資源と捉えるなど、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、資源を循環させる経済の仕組みのことを指します。
なぜ今、循環経済が重要なのか?
世界的な人口増加・経済成長に伴い、資源・エネルギー・食料需要の増大、廃棄物量の増加、温暖化・海洋プラスチックをはじめとする環境問題の深刻化は限界を迎えつつあり、従来型の大量生産・大量消費・大量廃棄型の線形経済モデルでは、持続可能な社会を実現することはできないという問題があります。
これを解決する取り組みが循環経済です。
経済産業省も2020年5月、循環経済への移行に際して今後日本が進むべき方向性についてまとめた「循環経済ビジョン2020」を公表しました。
循環経済に対する疑問
しかし、循環経済はまだ十分に認知されおらず、誤解されていることも多いのが実情です。 例えば、以下のような疑問があると思います。
・我々の業界に関係あるのか?(エネルギー、リサイクルなど一部の業界の話しではないか?)
・SDGsと何が違うのか?どういう関係にあるのか?
・必要性は分かるが、企業にとってメリットがあるのか?
・ITやDXはどう関連するのか?SIerにはビジネスチャンスはあるのか?
企業はどのように循環経済に取り組むべきなのか?どのように始めるべきなのか?
今回は、循環経済の専門家である株式会社メンバーズの数藤雅紀氏をゲストにお迎えして、初心者にもわかりやすく循環経済について「超入門」として解説し、上記の疑問に答えるとともに、企業がどのように循環経済に取り組むべきなのか、またどのように始めるべきなのか、などについて議論していきます。
ITは循環経済にどのように貢献できるのか?情シスやSIerはどのような提案をするべきか?
また、循環経済とITにはどのような関係があるのか?ITは循環経済に貢献できるのか?情シスやSIerは経営に対してどのような提案をするべきか?などについて議論していきます。
ぶっちゃけトークを展開
また、参加者も交えて議論していきます。シナリオがない対談ですので、どこに行くかわかりません。また、時間の関係で全てのテーマについて十分な議論ができないと思います。ご了承下さい。
数藤雅紀氏
株式会社メンバーズ シニアプロデューサー 兼 デジタルトレンドラボ所長 サーキュラーエコノミープランナー
大手証券会社、世界大手調査会社を経てメンバーズ入社。新規事業、国策案件、未踏案件など先例の少ない難易度の高い案件に魂を燃やすタイプ。DX、X-Tech、SDGs/ESGなどをカバー。 ケンブリッジ大学経営大学院「持続可能性&循環経済プログラム」修了認定。現在サーキュラーエコノミーのビジネス化に邁進中。 得意分野:金融、デジタル、循環経済、錆付いた英語トーク サーキュラーエコノミーに関するコラムを多数執筆。
寺田雄一
ウェビナー(Webセミナー)の集客・運営サービス「マジセミ」を起業、代表取締役社長。IT関連のウェビナーを年間600回運営。
野村総合研究所(NRI)出身。NRIでは社内ベンチャーとして、オープンソース・サポートサービス「OpenStandia」を起業。その後、マジセミやクラウドID管理サービス「Keyspider」など次々と新規事業を創出するシリアルアントレプレナー(連続起業家)。
主催
マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
ウィズコロナ時代のIT資産管理リソースの課題〜PC・デバイスのキッティング、障害対応、予備...
3.5 JBサービス株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
ウィズコロナで、テレワーク環境構築やオフィス閉鎖・開設が増加傾向に
感染症対策および働き方改革の推進により、オフィスや店舗を柔軟に閉鎖・縮小したい企業は従来よりも増加しています。 2020年のスペースマーケット社の調査では、企業の約4割が「家賃減額やフリーレント交渉」「オフィスを一部解約して縮小」を検討していると回答しました。一方で、経済状況を見ながら、新しい店舗を出店検討している企業も多くいます。
PC、デバイスなどIT資産管理をどうするか?(スマホ、タブレット、モニター、TV会議システムなど)
その際に、「PCや周辺機器を一時的にどのように管理、運用していくか」が課題になってきます。これらを預けて管理する場所も、管理する人員もいないケースが多いのではないでしょうか。情シス内で管理者を定めたとしても、膨大な数のデバイスを管理・メンテナンスする工数を考えると現実的に難しいです。また、セキュアな環境でデバイスを管理・保守できるわけではありません。 今後、感染拡大と縮小を繰り返すリスクを考慮すると、柔軟にIT資産を預けたり、取り出せる機能が必要になってくると予想されます。
キッティング、障害対応、保管、輸送までをワンストップで行うには?
今回のセミナーでは、「ウィズコロナ時代のIT資産管理リソースの課題」をテーマに、IT機器の受入、障害受付、MDM、キッティング、配送をワンストップで行うサービスをご紹介します。オフィスの縮小や開設を検討する中で、デバイス管理にお困りの企業様は奮ってご参加ください。
こんな方におすすめ
・コロナ禍でオフィススペースの縮小や変革を検討している(コワーキングスペースなど) ・情報システム部門の働き方改革を検討 している ・コロナ禍でテレビ会議システムなどを一時的に外部保管したい ・店舗ソリューションを展開・検討している
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ )
13:05~13:40 ウィズコロナ時代のIT資産管理リソースの課題
・ウィズコロナ、アフターコロナにおけるビジネス環境の変化 ・PC、スマホ、タブレットなどの管理の課題 ・JBサービスが提供する「IT Asset運用サービス」の特徴、ユースケース紹介 ・申し込み特典のご案内
13:40~14:00 質疑応答
主催
JBサービス株式会社(プライバシー・ポリシー) ※お申込みいただいた方は、プライバシーポリシーに同意頂いたとみなします。
【動画配信】ウェビナー配信ツールの比較~Zoom、Teams、Google Meetの比較...
4.1 マジセミ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
事前に録画した映像を配信するセミナーとなっております。
本ウェビナー(Webセミナー)の対象者
本セミナーは、以下のような方を対象としています。 ・IT業界や製造業で、営業・マーケティングをご担当されている方 ・その中で、ウェビナーの開催を検討されている方
拡大するウェビナー
昨年から、リアルなセミナーやイベントは開催が難しい状況が続いています。 そのような中、注目されているのがウェビナーです。 マジセミでも、昨年から100%ウェビナーに切り替えており、今年は約600回のウェビナーを運営しています。
ツールは何がよい?Zoom?Teams?それともGoogle Meet?
ウェビナーを開催するとき、配信ツールは何がよいのでしょうか? Zoomが人気ですが、最近はTeamsも急速に普及しています。 また、Google Meetもあります。 どう違うのでしょうか?
oViceなど仮想空間でのウェビナーは?
また、最近ではoViceなど仮想空間でウェビナーを開催するケースも出てきました。 Zoomなどのウェビナーとどう違うのでしょうか?
ツールの比較を解説
本セミナーでは、上記のようなウェビナー配信ツールについて、その違いを解説します。
プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 【動画配信】ウェビナー配信ツールの比較
10:45~11:00 質疑応答
主催
マジセミ株式会社
【動画配信】いまさら聞けない、ウェビナー入門 ~運営実務の入門解説と、集客の課題~
4.1 マジセミ株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
今回は事前に録画した映像を配信するセミナーとなっておりますが、 是非皆さまからのリアルタイムでのご質問などお待ちしております。
重要性が高まる「ウェビナー」
コロナ禍でリアルセミナーが開催できなくなり、この1年でウェビナーが大幅に増加しました。 その結果、「リアルセミナーよりも参加しやすい」「全国どこからでも参加できる」といったウェビナーのメリットが認知され、コロナ後も多くのセミナーはオンラインでの開催を継続すると思われます。 また、ウェビナーはデジタルマーケティングの顧客接点のひとつとしても重要性が高まっています。
でも、やり方が分からない?
このような背景から、今後ウェビナーを積極的に開催したいと考える企業は多いと思います。 しかし、まだウェビナーを開催したことがなく、ウェビナーの開催の仕方、運営方法が分からないという方も多いではないでしょうか。
ウェビナー運営の実務についての入門解説
そこで本セミナーでは、年間600回のウェビナーを運営するマジセミ株式会社が、ウェビナー運営の実務について、初心者向けに解説します。
ウェビナーをやってみたけど、申込者が少ない、集客できない
また、実際にウェビナー運営をやってみると、「申込者が少ない」「集客できない」といった課題にぶつかると思います。 本セミナーでは、年間20,000人を集客するマジセミ株式会社が、なぜ集客が難しいのか、どうすれば集客できるようになるのかについて、解説します。
プログラム
9:45~10:00 受付 10:00~10:05 オープニング 10:05~10:55 (動画配信) いまさら聞けない、ウェビナー入門 ~運営実務の入門解説と、集客の課題~ マジセミ株式会社 代表取締役社長 寺田雄一 10:55〜11:00 クロージング
主催
マジセミ株式会社
契約書、約款、規定等のWord文書の新旧対照表を簡単に作成する~提出、配布用の新旧対照表の...
3.6 株式会社ヒューリンクス
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。
社内では日々さまざまな文書が作成されています。特にページ数の多い文書の場合、改定を重ねていくうえで、どこが変わったのかを簡単に知ることが重要です。Microsoft Wordには、校正機能が備わっていますが、あくまでも改定の履歴を管理するものです。最終的にコミット(変更の承認)してしまった変更は失われます。実際の業務では、新旧対照表を作成する場合、あるいはPDFで出力したものと比較するような場合も出てきます。実務で役立つ、文書の旧版と新版の比較について解説します。 本セミナーでは、広い範囲での文書の比較ではなく、新旧対照表について絞って話を進行していきます。
Microsoft Wordの変更履歴の限界について
Wordの「校閲」メニューで「変更履歴の記録」を有効にすると、その文書の編集の履歴を記録することができます。これは、ファイルを編集している間(1人であっても、多人数で同じファイルを順番に編集する場合でも)は、他のソフトを使わずに記録できる点は便利です。しかし、いったん確定してしまって履歴をなくした場合、あるいは、別々のファイルを自社と取引先で別々に編集をしている場合にはこの機能はうまく機能しません。 また、顧客、取引先、官公庁に提出する場合の添付書類として「新旧対照表」が必要な場合には、手で表を作成する必要があるかもしれません。
新旧対照表を作成する必要がある現場とは?
導入の実績が多い例として、次の2つの業界を挙げて説明します。 【金融・保険業界】 ・官公庁への提出書類に添付する新旧対照表を作成する ・顧客に約款などの変更を示すために新旧対照表を作成する(例:生命保険契約約款変更) 【製薬業界】 ・官公庁への提出書類に添付する新旧対照表を作成する(例:医薬品等製造販売変更申請) 他にも、行政機関などは、関係各所に規定などに変更があった際には新旧対照表をつけることが通常でしょう。
新旧対照表の作成スタイルは提出先、目的で変わる
新旧対照表のスタイルは使用目的によって変わります。 ・1文字単位で修正箇所を示す ・単語単位で修正箇所を示す ・文章単位で修正箇所を示す その示し方にも、下線で示す、文字色を変えて示す、などがあり、また、「新文書」と「旧文書」の左右の配置や、備考欄に「修正」「削除」などの注意を入れる場合もあります。 このような、様々なスタイルを作成するには、専用のソフトウェアが必要になります。 例えば、企業の法務部門で契約書を比較するために使う場合を考えると、 ・文字単位で比較する ・相違のある個所は下線で示すと同時に画面でわかりやすくするために赤い字で表示 ・修正のある条項だけを抜き出したい というニーズに合致する必要があります。
Word内の表や図形をどうするか?
契約書等は文字のみになる場合がほとんどですが、社内規定集、運用ルール集などの文書の場合は、表や図形が多用されます。 このような場合、結果の表示方法、レイアウトなど、考慮しなければならい項目が増えます。また、文字のスタイルも標準、太字、斜体などが変更されたものを「変更」ととらえるのか、ヘッダーやフッターはどうするのかなども考えられるかもしれません。
「新旧文書 Word版」のデモンストレーション
ここまで、述べてきた様々な課題とその解決方法を「新旧文書 Word版」ではどのように解決できるかをご覧いただきます。
付録:「新旧文書 Excel版」の紹介
Microsoft Wordだけでなく、Microsoft Excelでも比較を行うことができます。新旧対照表のような比較表を作成でき、セル内の文字の変更だけでなく、行・列の挿入、削除、異動などを検出することができます。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング
13:05~13:40 プレゼンテーション・デモンストレーション
13:40~14:00 質疑応答
主催
株式会社ヒューリンクスプライバシー・ポリシー
当日会場アクセスに関するお問合せ
セミナー事務局
従業員の声は企業を救う?ビジネスの成長にその声を活かすポイント
3.1 富士通コミュニケーションサービス株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
こんな方におすすめのセミナーです
・事業責任者、新サービスのPO/PMO、マーケティング責任者 ・従業員エンゲージメントやEXという言葉は知っているが、もっと詳しく知りたい方 ・人事や労務部門ではないが、サービスの事業成長に従業員エンゲージメントが重要だと考えている方 ・CXとEXの関係性について学びたい方
働き方改革やコロナ禍で、労働環境が急激に変化する中での社内コミュニケーション
働き方が多様化する現代社会において、企業と従業員が良好な関係を築くためには従業員エンゲージメントの向上が重要です。 一方、働き方改革やコロナ禍でテレワークが普及し、対面コミュニケーションの時間が減少している企業も多いのではないでしょうか? 2020年の厚生労働省の調査結果では、社員が感じるテレワークのデメリットとして「同僚、部下とのコミュニケーションがとりにくい」「上司とのコミュニケーションがとりにくい」が50%以上を占めています。社内コミュニケーションの質・量の低下と共に、 従業員エンゲージメントの低下リスクがある状況といえます。
ビジネスの成長に、なぜ従業員の声が重要なのか?
従業員エンゲージメントは 「従業員が会社に対して抱く愛着心や信頼度」のことを言い、終身雇用が当たり前だったこれまでの日本では、維持することが比較的容易でした。しかし、働き方が多様化する昨今、心身ともに良好に働ける環境づくりが重要となります。このようななかで、従業員の声に耳を傾ける企業が増えてきていることも事実です。 さらに企業の顔として顧客接点の最前線にいる従業員は、顧客体験価値(CX)を大きく左右することから、従業員の声を収集し、ビジネスに活かすことが重要と考えます。さらにサービスや顧客体験価値の向上・戦略の実行度の向上などにも大きな影響があるといえます。従業員の声を収集し、ビジネスに活かすということは、事業開発・マーケティング責任者の方にとっても軽視できないテーマです。
顧客の声は把握しているが、従業員の声は・・・
商品/サービスの提供者としては顧客体験価値を重視しがちですが、果たしてそれだけで十分なのでしょうか? 加えて、従業員エンゲージメント向上に必要な“従業員の声”を収集し、経営にフィードバックしていくことが求められます。
従業員の声をどのように探り、どのようにフィードバックするのか?顧客体験価値との関係性は?
実際に従業員の声を収集するとなると、具体的実行が難しいものです。従業員満足度調査を実施するだけでは、職場環境の改善やベースアップの助言しか集められません。また、さまざまな職場環境改善のツールや研修ばかりを試してみても上手くいかず、躓いてしまう企業も少なくありません。では、どのように行えばよいのでしょうか?
本セミナーでは、テレワーク時代の永続的な事業成長のために従業員の声をどのように収集し、社内に展開・フィードバックしていくか、事例を交えて紹介します。株式会社wevnal取締役COOの西田氏に登壇いただき、対面コミュニケーションのエピソードも交えつつ、現在、そして近未来に渡って、従業員の声の収集・展開・フィードバックが、顧客体験価値の向上とどのように関係するのか?サービスの作り手として知っておくべきEXの考え方とは?を対談形式でお伝えします。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ )
13:05〜13:50 従業員の声は企業を救う?ビジネスの成長にその声を活かすポイント
13:50〜14:00 質疑応答
登壇者
於久 佳史(富士通コミュニケーションサービス株式会社)
ゼネラルマネージャー、(営業本部長)、エグゼクティブサービスデザイナー 富士通(株)入社 国内製造業のアカウント営業及びSCM/ERPの拡販。 中国における広報・プロモーション、マーケティング部門にて ロイヤルティ向上 施策を企画立案し実践。 現在は、デジタル技術を活用しCX/EXを向上させ、ロイヤルティを高めるサービスの企画/マーケティング/営業活動を実践中。
西田貴彦氏(株式会社wevnal 取締役COO )
2009年 有限責任監査法人トーマツ 入社 2011年 株式会社エス・エム・エス入社 2018~2020年 ベンチャー2社 管理部 所属 2020年 12月wevnal入社 wevnelジョインから9ヶ月後の2020年9月には、共同創業者の3名以外で初となる4人目の管理統括の取締役に。監査法人や事業会社の経営企画などに務めた前職までの経験を活かして、2021年4月からはビジネス領域にて、セールスやマーケティング、カスタマーサクセス、広告代理店業などを含めた総勢約40人のメンバーを統括する取締役COOに。自称「チーフスルーされるおじさん」。
主催
富士通コミュニケーションサービス株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社wevnal(プライバシー・ポリシー)
AWS依存から脱却するために、Oracle Cloudを併用する理由 ~AWSとOracl...
3.8 株式会社スマートスタイル
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
AWS依存から脱却する必要性
クラウドサービスとしてAWSを利用している企業は多いですが、リスクや負荷の分散という観点から、単一クラウドへの依存は危険であるとの考え方が広まっています。
AWSと並んで注目を集めるのが、Oracle Cloud
AWSと並んで注目を集めているクラウドサービスに、Oracle社が提供する「Oracle Cloud」があります。 クラウド上で OracleDB、MySQL を利用する場合の性能向上やコスト削減が可能であることから、多くの企業で採用されているクラウドサービスです。
クラウド間連携、マルチクラウドの課題
AWSとOracle Cloudを連携できれば、単一クラウドに依存しない環境を比較的低コストで運用していくことができます。 しかし、導入時に回線調達や設計見直しなどに多くの時間と労力を要するため、高いハードルがあります。 さらに、導入後にクラウド間のネットワーク遅延によって、パフォーマンスが劣化する可能性も考えられます。
クラウド間の閉域接続サービスを利用することで、手軽にAWSとOracle Cloudの連携を実現
そこで本セミナーでは、クラウド間の閉域接続サービスを利用することで、手軽にAWSとOracle Cloudの連携しマルチクラウド環境を実現する方法をご紹介します。 サービス初期費用が不要で従量課金、即日~数日で導入が可能なMegaport社のクラウド接続サービス「Megaport Cloud Router」を活用した、 マルチクラウド事例やユースケースを含め紹介しますので、ぜひご参加ください。
プログラム
9:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 AWS依存から脱却するには?クラウド間の閉域接続サービスで手軽にマルチクラウドを実現
10:45~11:00 質疑応答
主催
株式会社スマートスタイル(プライバシーポリシー)