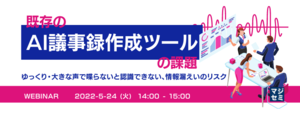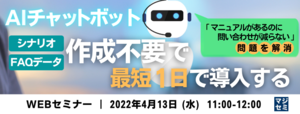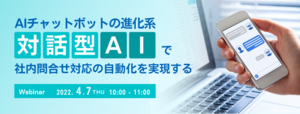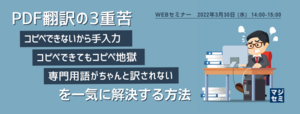先端技術
Advanced technology
先端技術の課題を解決するウェビナー
AIやディープラーニングの業界別活用事例、IoT、自動運転、AR/VR、メタバースやスマートグラス関連など、先端技術の市場規模や最新動向、さまざまな事例・ノウハウがわかるウェビナーやバーチャル展示会を掲載しています。
先端技術
最新&人気ウェビナー
該当するセミナーはありません
先端技術
ウェビナーアーカイブ
(動画・資料)
既存のAI議事録作成ツールの課題 ~ゆっくり・大きな声で喋らないと認識できない、情報漏えい...
4.0 株式会社ロゼッタ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
負担になっている議事録作成、WEB会議の増加でさらに負担が増すケースも
会議の内容を正しく共有するために欠かせない議事録ですが、WEB会議が浸透した昨今でもその必要性は変わりません。 むしろ、移動に時間を要することなく会議を開催できるため全体の会議数が増加し、それに伴い議事録の作成機会も増加する傾向にあるため、議事録作成の負担は以前より増していると考えられます。
メモに集中すると発言ができない、会議後に議事録を作るのは面倒
議事録を正しく作るには、会話内容を正確にメモすることが必要になります。 しかし、メモを取ることに集中するとなかなか発言できなくなりますし、会議の進行役をしているとメモをとること自体が困難です。 後から録音データを聞き返して文字起こしする方法もありますが、そうすると会議後に余分な稼働をかけることになってしまいます。
多くの文字起こしツールは、音声の認識精度が低い、またはセキュリティの問題で使えない
議事録作成を効率化するため、会話内容を文字起こしするツールもいくつか出回っています。 しかし、音声認識の精度が低いため、通常よりゆっくり大きな声で喋らないと正しく文字起こししてくれず、利用にストレスがかかるものが多いです。 また、AIの学習データとして利用され会話内容が漏れるなどセキュリティ上のリスクもあるため、そもそも利用が憚られるサービスも多いのが実態です。
音声認識の精度とセキュリティを兼ね備えた音声認識文字起こしツールで、議事録作成を自動化する
そこで本セミナーでは、音声認識の精度とセキュリティの問題をクリアして議事録作成を効率化する方法について解説します。 高い精度で音声を文字起こしでき、リアルタイム翻訳も可能なロゼッタ社の音声認識文字起こしツール「オンヤク」についても紹介する予定です。 議事録作成を自動化したい、他の文字起こしツールを使っているが音声認識精度に不満がある、とお考えの方はぜひご参加ください。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 既存のAI議事録作成ツールの課題~ゆっくり・大きな声で喋らないと認識できない、情報漏えいのリスク~
11:45~11:55 質疑応答
主催
株式会社ロゼッタ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
外国語会議の音声を自動で翻訳&文字起こし 〜シームレスな翻訳ツールで「言葉の壁」を取り除く〜
3.8 株式会社ロゼッタ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
海外企業との取引、吸収合併などにより社内外問わず外国語が必要になるケースが増加
グローバル化の進展に伴う海外企業との取引、または買収や吸収合併などにより、社内外問わず外国の方と話す機会が増えました。 それに伴い、会議や日々の会話で外国語の理解が求められるケースが急増しており、今後もこの流れは加速していくことが予想されます。
外国語を理解できない、または理解に時間がかかり会話が円滑に進まない
外国語を理解するには、一定の語学スキルが無いと困難です。 理解に時間がかかったり、そもそも理解が出来なかったりするとコミュニケーションにならないため、当然ながら会話は円滑に進みません。 また、翻訳スキルをもった社員が同席していても、翻訳に時間を要すれば会話のテンポは悪くなります。 さらに、翻訳者が業務内容に関する専門知識を持ち合わせていなければ会話内容を正確に理解できないため、翻訳してもうまく伝わらず話が噛み合わなくなるといった問題が起きることもあります。
音声翻訳ツールの多くは、デバイスが限られるため使える場面が限定的
このような外国語会議の問題を解決するために、音声翻訳ツールがあります。 しかし、多くのツールはインストールできるデバイスが限られています。 特に多いのが、PCにしか対応しておらずスマホにインストールできないといったケースです。 そのため、社内の会議では使えるものの出先や対面の会話などのシーンで使えないなど利用できるシーンが限られてしまっています。
シームレスな翻訳ツールでシチュエーション問わず「言葉の壁」のないコミュニケーションを実現
そこで本セミナーでは、デバイスを問わず使うことができるロゼッタ社の会議音声翻訳ツール「オンヤク」を紹介します。 外国語での会話に悩みを抱えており、自社に合ったツールを見つけられていない方は、ぜひご参加ください。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 外国語会議の音声を自動で翻訳&文字起こし〜シームレスな翻訳ツールで「言葉の壁」を取り除く〜
14:45~14:55 質疑応答
主催
株式会社ロゼッタ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
既存のAI議事録作成ツールの課題 ~ゆっくり・大きな声で喋らないと認識できない、情報漏えい...
3.9 株式会社ロゼッタ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
負担になっている議事録作成、WEB会議の増加でさらに負担が増すケースも
会議の内容を正しく共有するために欠かせない議事録ですが、WEB会議が浸透した昨今でもその必要性は変わりません。 むしろ、移動に時間を要することなく会議を開催できるため全体の会議数が増加し、それに伴い議事録の作成機会も増加する傾向にあるため、議事録作成の負担は以前より増していると考えられます。
メモに集中すると発言ができない、会議後に議事録を作るのは面倒
議事録を正しく作るには、会話内容を正確にメモすることが必要になります。 しかし、メモを取ることに集中するとなかなか発言できなくなりますし、会議の進行役をしているとメモをとること自体が困難です。 後から録音データを聞き返して文字起こしする方法もありますが、そうすると会議後に余分な稼働をかけることになってしまいます。
多くの文字起こしツールは、音声の認識精度が低い、またはセキュリティの問題で使えない
議事録作成を効率化するため、会話内容を文字起こしするツールもいくつか出回っています。 しかし、音声認識の精度が低いため、通常よりゆっくり大きな声で喋らないと正しく文字起こししてくれず、利用にストレスがかかるものが多いです。 また、AIの学習データとして利用され会話内容が漏れるなどセキュリティ上のリスクもあるため、そもそも利用が憚られるサービスも多いのが実態です。
音声認識の精度とセキュリティを兼ね備えた音声認識文字起こしツールで、議事録作成を自動化する
そこで本セミナーでは、音声認識の精度とセキュリティの問題をクリアして議事録作成を効率化する方法について解説します。 高い精度で音声を文字起こしでき、リアルタイム翻訳も可能なロゼッタ社の音声認識文字起こしツール「オンヤク」についても紹介する予定です。 議事録作成を自動化したい、他の文字起こしツールを使っているが音声認識精度に不満がある、とお考えの方はぜひご参加ください。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 既存のAI議事録作成ツールの課題~ゆっくり・大きな声で喋らないと認識できない、情報漏えいのリスク~
14:45~14:55 質疑応答
主催
株式会社ロゼッタ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
【製造業向け】「専門用語の翻訳精度が低い」問題を月額4,900円で解決する
3.5 Xtra株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
海外企業との取引急増に伴い、外国語文書の翻訳シーンも急増
グローバル化によって、海外企業と取引をする機会が増加しました。 それに伴い外国語文書を扱うケースが増えましたが、翻訳作業に工数がかかるという課題が浮上しています。
無料の翻訳サービスは、専門性の高い原稿の翻訳精度が低い。PDF などファイルの翻訳も困難
無料で使える翻訳サービスも多数ありますが、これらは専門用語を含む専門的な翻訳となると精度が期待できない可能性が高くなります。また、二次利用(運営会社が学習データとして利用)される可能性があり、情報漏洩リスクが高まります。 さらに、特に製造業において仕様書やマニュアルなどの PDFファイルの翻訳となると、原稿をコピー&ペーストしようとしてもできないケースも多々あります。コピーできたとしても、何回もコピー&ペーストを繰り返してようやく翻訳できる……など、翻訳の準備だけで膨大な時間がかかってしまうこともあります。
精度とコストを両立した翻訳サービスがない
無料の翻訳サービスの弱みを補った有料の翻訳サービスもありますが、比較的高額で、導入のハードルが高いものも多々あります。 翻訳精度とコストパフォーマンスを両立した翻訳ソリューションがあまりないのが現状です。
専門用語に対応した高精度翻訳を月額4,900円でで実現する
そこで本セミナーでは、専門用語でも高精度で翻訳できるツールを安価に導入する方法として、産業翻訳で定評の高いロゼッタ社の翻訳サービス 「T-4OO」 の汎用エンジンを採用し、より安価なサービスとして提供するXtraのAI自動翻訳「Qlingo(クリンゴ)」をご紹介します。 リーズナブルな価格で専門用語の自動翻訳を実現したいとお考えの製造業の方は、ぜひご参加ください。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 【製造業向け】「専門用語の翻訳精度が低い」問題を月額4,900円で解決する
14:45~14:55 質疑応答
主催
Xtra株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
外国語会議の音声を自動で翻訳&文字起こし 〜「言葉の壁」を取り除いて会議の生産性を上げる〜
3.8 株式会社ロゼッタ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
海外企業との取引、吸収合併などにより社内外問わず会議で外国語が必要になるケースが増加
グローバル化の進展に伴う海外企業との取引、または買収や吸収合併などにより、社内外問わず外国の方と話す機会が増えました。 それに伴い、会議で外国語の理解が求められるケースが急増しており、今後もこの流れは加速していくことが予想されます。
外国語を理解できない、または理解に時間がかかり会議が円滑に進まない
会議で飛び交う外国語を理解するには、一定の語学スキルが無いと困難です。 理解に時間がかかったり、そもそも理解が出来なかったりするとコミュニケーションにならないため、当然ながら会議は円滑に進みません。 また、翻訳スキルをもった社員が同席していても、翻訳に時間を要すれば会議のテンポは悪くなります。 さらに、翻訳者が業務内容に関する専門知識を持ち合わせていなければ会話内容を正確に理解できないため、翻訳してもうまく伝わらず参加者間で話が噛み合わなくなるといった問題が起きることもあります。
音声翻訳ツールの多くは、音声そのものの認識精度が低く、翻訳精度以前の問題を抱えている
このような外国語会議の問題を解決するために、音声翻訳ツールがあります。 しかし、多くのツールは音声認識の精度が低いのが実態です。 音声翻訳は、音声認識→翻訳というプロセスで行われるため、音声を正しく認識できなければ当然ながら正しく翻訳をすることも出来ません。 音声を正確に認識してもらうためには、通常よりも大きな声でゆっくり話さなければならず、余計なストレスを抱えることになってしまうのです。
外国語も含めた会話内容を自動で翻訳&文字起こしして、会議の生産性を上げる
そこで本セミナーでは、会話内容を高精度で認識して自動文字起こしを行い、さらに議事録の作成も可能なロゼッタ社の会議音声翻訳ツール「オンヤク」を紹介します。 外国語会議に悩みを抱えており、自社に合ったツールを見つけられていない方は、ぜひご参加ください。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 外国語会議の音声を自動で翻訳&文字起こし〜「言葉の壁」を取り除いて会議の生産性を上げる〜
14:45~14:55 質疑応答
主催
株式会社ロゼッタ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
アナログメーターに後付するだけで「IoT化」する方法を、実物で解説 ~製造業向けIoTがい...
3.8 マジセミ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
製造業向けIoTでは、実際の機器を見てみないとわからないことも多い
製造業向けIoTは、ソフトウェアの製品やサービスとは異なり、既存の設備に設置できるのか、接続は大丈夫なのか、など、画面だけではわからないことも多くあります。
例えば、アナログメーターに後付するだけでIoT化できる「Salta(サルタ)」は、既存のメーターにどのように設置できるのか?
例えば、アナログメーターに後付するだけでIoT化できる「Salta(サルタ)」という後付IoTセンサユニットがあります。 これを、既存のメーターにどのように設置できるのか、設置できないケースがあるのか、どのようにIoT化(デジタルデータへの変換)ができるのか、などは、実物を見てみないとイメージできない部分も多いと思います。
製造業向けIoTがいろいろ試せる「IIoT-Lab」をバーチャル視察
そこで今回は、積乱雲プロジェクトが運営する「製造業向けIoTがいろいろ試せる IIoT-Lab」にカメラを入れて、バーチャル視察を行います。
積乱雲プロジェクトとは
積乱雲プロジェクトは、2013年12月関西で発足し2016年6月にはその動きが関東にも波及。卓越した技術を持つ中小企業が連携することで、センサと機器の接続から安全対策、クラウド整備まで一貫したソリューション開発を可能としました。センサからクラウドまで顧客の要望に応じて柔軟に対応できる体制を整えています。幅広いIIoT市場に向けマーケティング活動を通じ、ビジネスモデルおよび技術を模索し、新たな付加価値創造に向けチャレンジを続けていきます。
プログラム
12:45~13:00 受付
13:00~13:05 オープニング(マジセミ)
13:05~13:25 IIoT-Labのご紹介と、本日のデモ内容について
13:25~13:40 アナログメーターに後付するだけで「IoT化」する(IIoT-Lab浜松町から)
13:40~13:55 多種のセンサーのデータを「IoT化」する(IIoT-Lab恵美須町から)
13:55~14:00 質疑応答、アンケート
主催
マジセミ株式会社
共催
株式会社ベルチャイルド(プライバシー・ポリシー) 東亜無線電機株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
AIチャットボット、シナリオやFAQデータ作成不要で最短1日で導入する 〜「マニュアルがあ...
3.5 ペネトレイト・オブ・リミット株式会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
社内DXの必要性
DXの必要性が提唱されはじめて久しいですが、着実にその歩みを進められている企業はまだ多くはありません。 そこでDX推進のフェーズを細分化し、まずは社内の不便・非効率な業務を改善することで生産性向上やコスト削減を実現することを目指す『社内DX』の推進が注目されています。
マニュアルやFAQがあるのに問合せ対応に追われてしまう
社内DX実現の方向性の1つとして、社内問い合わせ対応の改善が挙げられます。 問い合わせ対応の課題として、まず問合せを受ける側としてはマニュアルやFAQに載っていることを聞かれるために問い合わせ数が膨大になり、対応に追われている現状があります。 一方、問合わせを行う側からは、知りたい情報がどこに載っているかわからないため問い合わせざるを得ないといった意見が出ています。 このように、問合せを受ける側・行う側の双方が不満を抱えているのが実情です。
シナリオ作成などの事前準備がネックとなりAIチャットボットの導入に踏み切れない
上記の課題を解決する手段としては、AIチャットボットの導入が考えられます。 しかし、導入時のシナリオやFAQのデータ作成に時間を割けないことがネックとなり、導入に二の足を踏んでいる企業も多いと思われます。
既存のファイルやマニュアルを活用して最短1日でAIチャットボットを構築する方法
そこで本セミナーでは、社内で保有している既存のファイルやマニュアルを活用することで簡単にAIチャットボットを構築できる方法を紹介します。 ペネトレイト・オブ・リミット社が手掛ける、シナリオやFAQデータ作成不要で最短1日で導入できるお手軽次世代ヘルプボット「amie」についてもご紹介する予定です。ぜひご参加ください。
プログラム
10:45~11:00 受付
11:00~11:05 オープニング(マジセミ)
11:05~11:45 AIチャットボット、シナリオやFAQデータ作成不要で最短1日で導入する
11:45~11:55 質疑応答
主催
ペネトレイト・オブ・リミット株式会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
AIチャットボットの進化系"対話型AI"で社内問合せ対応の自動化を実現する
3.7 Kore.ai Japan 合同会社
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
リモートワークにより社内問合せ対応の問題が発生
リモートワークの普及が進んだことにより、自宅やシェアオフィスで勤務をする形式が一般的になりました。 しかし物理的に離れた場所で仕事をすることに伴い、社内問合わせの対応において問題が生じています。
社員側、受付側の双方から様々な不満が噴出
問合せをする社員側としては、聞きたいことを気軽に質問できない、誰に聞けば良いかわからない、マニュアルが見つからない等の要因により、致し方なく社内ヘルプデスクへ問合わせをせざるを得ないケースが増えました。 そして受付側としては、増加した問合せを受けきれない、マニュアルや社内掲示板等に書かれてあるにも関わらず問合せがくる、といった意見が出ています。 このように、問合せをする側、受け付ける側の双方から様々な不満が噴出しているのが実情です。
従来のチャットボットは設計が困難でインテント(意図)認識率が低く、導入後の運用にも課題
社内の問合せ対応を効率化する代表的な手段として、AIチャットボットが挙げられます。 しかし多くのAIチャットボットは、設計が難しく外部委託が必要になってしまう、インテント(意図)認識の精度が低いために対応を自動化できない、導入後の運用が煩雑で管理コストがかかる等の様々な問題があり、導入しても効果を得られないといった課題を抱えています。
社内コミュニケーション自動化の事例を紹介
そこで本セミナーでは、設計が容易でインテント認識率も高く、導入後も高いパフォーマンスを発揮できる社内コミュニケーション自動化ツールの作り方や導入事例について紹介します。 また、ノーコード設計が可能で、問合せを受けるだけではなくその後の処理の実行も自動化でき、2022年ガートナーマジッククアドラントのエンタープライズ会話型AIプラットフォーム部門のリーダーに選ばれたKore.ai Japan社のソリューション「Kore.ai Platform 9.0」についても紹介しますので、ぜひご参加ください。
プログラム
09:45~10:00 受付
10:00~10:05 オープニング(マジセミ)
10:05~10:45 AIチャットボットの進化系対話型AI
で社内問合せ対応の自動化を実現する
10:45~10:55 質疑応答
主催
Kore.ai Japan 合同会社(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)
PDF翻訳の3重苦「コピペできないから手入力」「コピペできてもコピペ地獄」「専門用語がちゃ...
3.0 株式会社ロゼッタ
本セミナーはWebセミナーです
ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認下さい。
海外企業との取引急増に伴い、外国語PDF資料の翻訳シーンも急増
グローバル化によって、海外企業と取引をする機会が増加しました。 それに伴い外国語のPDF資料を扱うケースが増えましたが、翻訳作業に工数がかかるという課題が浮上しています。
一般的な翻訳ツールが抱える3つの課題
翻訳作業を効率化するために翻訳ツールがよく使われますが、一般的な翻訳ツールは以下に示すような課題を抱えています。
1. コピペできない場合、手入力が必要
文字列の選択ができないPDFファイルの場合、コピペして翻訳ツールに入力することができません。 文章量が少ないならまだしも、文章量が多い場合は気の遠くなるような入力作業が必要になってしまいます。
2. コピペできても、何度もコピペ作業が必要
仮にコピペができたとしても、全文をそのままコピペすると意味不明な訳や訳抜けが見られるケースも多いです。 こま切れにして翻訳していかないといけないため、何度もコピペ作業が必要になり膨大な時間がかかってしまうのです。
3. 専門用語の翻訳精度が低い
巷の翻訳ツールは一般会話向けに作られているものがほとんどであるため、専門用語の翻訳となると精度は著しく落ちます。 また、同じ単語でも業界によって意味やニュアンスが異なるものもあるため、業界の文脈に合わない不自然な翻訳になってしまい、結局自分で翻訳し直さないといけないというケースも多いです。
外国語のスキルがあっても、属人化によりリードタイムがより長時間化
「外国語のスキルに長けた社員がいるから、翻訳ツールに頼る必要はない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、スキルのある人材に依存をしてしまうとその人に負荷が集中し、作業の属人化により翻訳作業が停滞してリードタイムが伸びてしまいます。 つまり、翻訳ツールの課題を解決しない限り翻訳業務にかなりのリソースが割かれることは免れないのです。
一般の翻訳ツールが抱える課題を一気に解決し、翻訳業務にかかるコストを大幅削減する方法
そこで本セミナーでは、一般の翻訳ツールが抱える課題を一気に解決し、翻訳業務にかかるコストを大幅削減する方法を紹介します。 ビッグデータとAIの技術を駆使して外国語PDF文書の自動翻訳を実現しているロゼッタ社のAI自動翻訳ツール「T-4OO」についても紹介します。 ぜひご参加ください。
プログラム
13:45~14:00 受付
14:00~14:05 オープニング(マジセミ)
14:05~14:45 PDF翻訳の3重苦「コピペできないから手入力」「コピペできてもコピペ地獄」「専門用語がちゃんと訳されない」を一気に解決する方法
14:45~14:55 質疑応答
主催
株式会社ロゼッタ(プライバシー・ポリシー)
協力
株式会社オープンソース活用研究所(プライバシー・ポリシー) マジセミ株式会社(プライバシー・ポリシー)